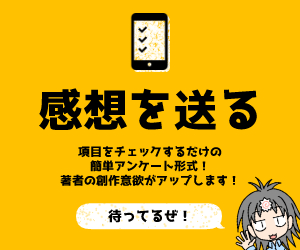ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第十四話の続きになります。
第十四話までのあらすじは以下のような感じです。
新たな任務を言い渡されランピャンにやってきたシシィたちは、冒険者登録とランクアップを目指して、魔物が出没する狩り場へと向かう。難易度が低いこともあり、狩り自体はスムーズに進むが、フューリの好感度アップを目論むティクトレアとヒーゼリオフの邪魔が入り、無駄な時間が過ぎていく。なんとか魔族の存在を有効活用したいシシィは上手いこと二人を丸め込み、移動の足にすることに成功した。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下十五話です。
【シシィ 四】
ティクトレアの提案で、転移ではなく飛行で運ばれることになった私たちは、モンチョラ山へ向けて一直線に空を横切っていた。魔力の少ない私には空を飛ぶのは初めての体験だった。空気の川を流されているみたいで、かなり楽しい。眼下に広がるランピャンの景色も最高だ。
迎賓館のある都市部、その周囲の農地、リンボル草原とそれを二分する大河に、流れに沿って生い茂る森。飛べない私には本来一つ一つしか見れない光景だけど、今はそれらを全部一度に眺められる。初めは転移のほうが早いのにとか思ったけど、体験してみるとこっちのほうが断然良い。飛び始めて一分もしないうちに、フューリとルゥと私は、飛行魔法と眼下の光景に大はしゃぎしていた。
「わー、早いね、すごいね! 見て! 変わった山がいっぱい!」
「楽しいでしゅー! あ、あの山、よく見ると、所々に岩肌が見えましゅよ!」
「ホントだ! 土の山じゃないんだな!」
フューリが向かう先に見えてきた山を指し、私たちは声を上げた。草原からは竜の背びれみたいに見えていた山々が、近付くにつれ輪郭がはっきりとして、切り立った岩で出来ていることがわかる。木が生い茂ってはいるけど、山というよりは塔とか砦っぽい。ヒーゼリオフが雨水や地下水で岩が侵食されてできた地形だと説明してくれた。イラヴァールも砂漠地帯でなければ、周辺にある岩に植物が芽生えて似たような具合になるらしい。魔法でもない自然の水が岩の形を変えるなんてとても信じられないけど、魔族が言うならたぶん本当なんだろう。世界ってヤツはホントに不思議だなと、ほっぺたがムズムズした。
あっという間にモンチョラ山に到着し、私たちは麓の森へと降り立った。
「じゃあすぐ獲ってくるね!」
着地するやフューリはパッと姿を消して三日月猪を狩りに行く。私たちは休憩だ。
三日月猪は名前は魔物っぽいけど、吻部の上下に突き出した牙が三日月型をしているというだけのただの猪だ。脅威度もついていないし、武器や防具に向いた素材が手に入るわけでもない。秒で狩ってきたフューリは肉質の良さを喜んで「みんなは狩らないの?」と首をかしげるけど、まぁ、要するに冒険者の獲物ではないのだ。
私は首を振って「そいつがベーコンになったら食わせてくれ」と笑うと、ルゥにティクトレアやヒーゼリオフも食べたいと言い出したので、フューリは追加で五頭狩って解体を済ませてしまう。到着してからここまでで十分とかかっていないのだから恐れ入る。
それに比べてガーティレイとヴィオレッタときたら、飛行魔法が怖かったらしく、着地してからもずっと青い顔をして震えているし、フューリが猪狩りを終えて、氷平陸魚の生息する山頂に転移すると、今度は転移に酔ったようで、ぐえぐえと嘔吐きだすのだからなんとも頼りない。
「ガーさんもヴィさんも大丈夫っすか?」
「ももも、問題ないわ……。うぶ……」
「ななな、なんともないとも……。おげ……」
二人は強がるが、青とも紫とも付かないひどい顔色をしていた。
「誰かなんかシャキッとなる薬とか持ってねぇ?」
私はなんとか体調を回復させられないかと、みんなを振り返る。私も薬はいくつか持ってきているけど、この手の症状に効くものの持ち合わせはない。ルゥのいい匂いのする霧を使えば多少スッキリさせられるだろうけど、山賊猿戦を控えている今は魔力は温存したい。
「うーん、草でも生えてれば良いんだけど……」
フューリが困った顔で辺りを見回す。植物なら味と匂いさえ用途にあっていれば、解毒して食べさせれば効くだろうけど、山頂付近のこの場所は真っ白な雪景色で、なにも生えていそうにない。
「ヒー様、ティク様。魔法でなんとかならないっすか?」
私はさり気なく魔族たちの後ろに立って耳打ちした。
「はぁ? 一応これ訓練でしょ? 自分たちでなんとかしなさいよ」
「他人に親切なところを見せるってのは、好感度アップに効果的っすよ」
「おふん、おふん! ま、まったく、だらしないわねぇ。ティク、回復してあげて」
「そ、そうねぇ。このままじゃ戦えないものね」
一発で手のひらを返したヒーゼリオフに促されて、ティクトレアは二人の青ざめた額に手をかざす。淡い紫色の光が一瞬で二人の身体を包み飛散する。光が消えると二人の顔色はすっかり元に戻っていた。
「む? なんだ? 急に調子が良くなったぞ」
「今まで回っていた視界が嘘のようだ。閣下! ヴィオレッタ、このご恩は必ずお返し致します!」
「あら、良いのよ。魔族には造作もないことだから」
「わぁ。回復魔法ってすごいんですね!」
元気になったガーティレイとヴィオレッタを見て、フューリが目を丸くした。ティクトレアはそれはそれは嬉しそうに「大したことじゃないのよ」なんて言ってるけど、実はこれは非常に恐ろしいことだったりする。
通常、物体の内部で魔法を行使するのは難しい。魔法は魔力を送った先の魔力濃度を上回らないと顕現しないが、物体はどんなものでも表面より内部のほうが魔力濃度が濃いからだ。例えば、空気中に炎を発生させるときに必要な魔力を一とした場合、地中や水中は十以上の魔力を送らないと顕現しない。
さらに意識や自我を持つ生命は、体内に魔力が送られるとその場所の魔力濃度を上げて顕現化を防ぐ免疫機能を持っているため、その体内に魔法を行使するとなると、必要な魔力量は数百や数千にも膨れ上がる。そのため治癒魔法や毒魔法など、身体に作用する魔法は、空中で有効な成分を生成してぶつけるという使い方をするのが普通だ。
「なぁ、ルゥ。あの魔法に必要な魔力量ってどんくらいだと思う?」
「ルゥの全魔力の十倍は軽く超えてると思いましゅ……」
「うへぇ。やっぱ魔族、パネェな……」
私は無邪気に回復魔法の効果にはしゃぐ三人を白い目で眺めつつ、身体の中に毒を作られる場面を想像して身震いした。
「ま、ガーさんと、ヴィさんが回復したことだし、フューリが氷平陸魚狩ってる間、私たちは山賊猿と一戦交えようぜ! ってことでフューリ、猿っぽい匂いするのはどっちだ?」
まだ腕に鳥肌が立っているけど、魔族がおっかないのは今に始まったことじゃない。それに今は「好感度上げに良いですよ」って魔法の言葉があるし、都合の良い方向に利用できるだろう。私は気を取り直して、フューリに索敵を頼んだ。
「うーん、あっちとそっちにいるけど、数が多そうだよ? 僕も手伝ったほうが良くないかな?」
「山賊猿は脅威度Hだし平気だって! なんてったってこの新兵器が付いてるからな!」
心配そうに尾根を指すフューリに、棒状の魔術武器を掲げてみせる。そりゃあいてくれたほうが心強いけど、フューリはだいぶ過保護だから、ちょっとでも危険と判断すると、すぐに割って入って獲物をかっさらってしまう。自分でなんとかできるレベルの狩り場では、離れていてくれたほうがありがたいのだ。
「それに危なかったら、ティク様とヒー様がなんとかしてくれますよね?」
「なによ。このヒーゼリオフ様にアンタたちのお守りをしろっていうの?」
「手出しをするのは、かえって邪魔にならないかしら?」
「このままだとフューリは私たちを心配して狩りに行けないんで、「任せろ」って言っといたほうが株が上がりますよ」
「「まぁ、確かに数は多いから、気にかけておくようにするわ」」
魔族たちが面倒くさそうな顔をしたので、私は二人の首にがっしり腕を回し甘言を弄して、フューリが単独行動をするよう仕向ける。フューリは二人が見ていてくれるならとしぶしぶ頷き、「じゃあさっきみたいに釣ってくるね」とわずかに腰を落としたが、ヒーゼリオフが「ちょっと待ちなさい」とそれを止めた。
「アイツらは基本集団で来るし、仲間呼ぶし、連携し合うし、奪った物で武装もしてるのよ。そんな装備じゃ心許ないわ」
「そうねぇ。山賊猿って名前も、人間の山賊も顔負けってことでついたんだもの。いくつか術式を乗せたほうがいいかもね。みんな一度装備を見せてくれる?」
さっきの「他人に親切なところを見せると好感度が上がりますよ」ってセリフが効いているのか、魔族たちは私たちの装備をグレードアップさせると言ってくれた。これはとてつもない僥倖だ。私は急いですべての装備を外し、魔族らの前に並べた。ルゥも「ありがとうございましゅ!」と歓声を上げて、外した装備を並べる。フューリは私とルゥの行動に戸惑ったような顔をしつつも、防具を外して同じように並べる。ヴィオレッタもそれに倣うけど、格好をつけてゆっくりと外していた。ガーティレイだけは腕組みをして突っ立ったまま動かない。半裸でいるものだから寒くて動けないんだろうけど、「私には不要だ」と強がりを言っている。
「どれどれ。ふーん。さすがはイラヴァール製の装備ね。なかなか良い式が入ってるじゃない。で? フューはどう強化したいの?」
「今の式は、注入式の強度アップと、火耐性、温度変化耐性だけだから、全吸式に変えて、筋力強化を加えるのはどうかしら?」
魔族らはまずフューリの隣に陣取って外した装備品を眺めた。ヒーゼリオフの問いにフューリが首をかしげると、すかさずティクトレアが変更案を助言する。ヒーゼリオフとティクトレアの間には火花が散っているけど、フューリはそれにはまったく気付かず、ティクトレアが言った言葉の意味について尋ね、筋力強化の変更を丁重にお断りした。ただでさえ最近、力のコントロールが上手くいかないから、装備で増減するとますます加減ができなくなりそうで不安なのだそうだ。
全吸式の筋力強化術式が施された装備なんて世界レベルの秘宝なんだが、まったく理解できていないらしい。魔法と魔術の勉強が足りないって、今度オルナダにチクってやろう。
ヒーゼリオフとティクトレアは競い合うようにして強化案を提案したが、結局フューリは、防具に元の式の強化と、全吸式化、軽量化、衝撃遮断、愛用の山刀とナイフに腐食防止効果だけを付与してもらい、礼を言って氷平陸魚を狩りに出発した。ちなみにオルナダからもらった盾、もとい、フライパンのほうは、すでに完璧な状態の術式が施されていたため、手を付けることができなかった。
「はぁ。フューくんって、ホントに無欲な子ね……」
「魔族を二人も捕まえて、リクエストする術式があんななんてビックリよ……。鍋に至っては、オルのお手製で手の出しようがなかったし……」
「その……、なんかウチのバカがサーセン……」
残念そうにフューリを見送る二人の後ろ姿があまりに気の毒で、思わず謝ってしまった。幼い頃、町の流行り病を沈めてくれた旅のホビットに礼をしようとした母を思いだす。可能な限りのご馳走を用意したのに修行中の身だからと水しか受け取らなくて、コックと一緒にガッカリしてたっけな。
「まぁ、ここはひとまず気を取り直して、こっちに取り掛かってもらっても良いっすかね? お二人の魔術テクがどんだけ凄いかは、あとで私がパワーアップした装備にはしゃぎつつ説明するんで。それにあいつ、自分のコトより他人のコトので喜んだりするんで、たぶん私たちの装備を凄くしてもらったほうが効果ありますから」
「ホントでしょうね?」
「嘘でも本当になるまで説明してもらったら良いわ。まずはアップグレードを済ませちゃいましょ」
フォローを入れつつ作業を促すと、ヒーゼリオフは頬を膨らませて、ティクトレアが寒気のするような笑顔を浮かべて、私たちの装備を拾い上げて状態確認を始めた。
へそを曲げてはいるものの、魔族らの仕事は確かなもので、それぞれの特性に合った機能をいくつも提案して、こちらの希望や、機能同士の相性も考慮して、ベストと思われる術式に変更してくれた。基本機能を全吸式に変更するのはもちろんのこと、取り込んだ魔力の余剰分を蓄積し、一時機能の発動に使えるようにもしてくれた。
最大級の強度アップと、軽量化、各種耐性を基本に、私とヴィオレッタの防具には衝撃遮断が、ルゥのローブには魔力注入と自動防壁生成が付与された。私はそれに加えて、半面に熱探知機能を、ベルトに筋力強化と身体強化機能を付与してもらった。もちろん全吸式で、常時発動にしてもらった。ヴィオレッタもほしがったけど、この機能は体力を消耗するため、一定以上のスタミナがないと、逆に弱体化を招くらしい。
「微弱な魔力を流せば、機能の有効無効を切り替えられるようにしたから、戦闘時以外は切っときなさい。ヴィオレッタも筋力強化つけたいなら武器のほうに一時でつけたげるわ」
「はっ! ありがたき幸せにございます!」
「うっわ、すげ! 身体も鎧も軽っ! 痛み少なっ! ありがとうございます! マジ、パないっす、コレ!」
「あらあら、シシィくんたら、戦闘時だけにって言われたばかりなのに」
早速装備を身に着けた私は、ベルトの効果を試した。その場で垂直に跳んでみると、ジャンプ力は体感二倍くらいにアップしていた。軽くつねってみた腕は、皮膚が普段より硬い感触になっていて、痛みもあまり感じなくない。戦闘力で考えると五倍くらいにはなっているはずだ。これは今日中にランクE、いや、Dまでいけるかもしれない。
一刻も早く実践でこの効果を試したい! 腹の底からうずうず感が湧き上がって、手足の先までビリビリとしびが広がって、居ても立っても居られなくなってきた。
「うふふ。はしゃぐのは良いけど。フューくんが戻って来たときのために温存しておいてね?」
「う。はい……」
「うんうん。じゃあ今度は武器を貸してくれる?」
「よ、よろしくお願いいたします」
ティクトレアに釘を刺されて一気に熱が冷めた私は、神妙な顔を作って棒状の魔術武器を手渡す。
「あら。変わった武器ね。どこで見つけたの?」
「あぁ、これは武器庫の隅っこにあった試作品の部屋にあったんすよ」
「なるほど、通りで……」
ティクトレアは両手に持った棒をしげしげと眺めて、ぐっと手首を捻る。棒がカチッと小気味の良い音を立てた。表面に刻まれた術式が緑色に発光し、両端に仕込まれていた刃がジャギっと飛び出す。もう一度捻ると棒は真ん中で分かれて、柄の長い二本の短剣のようになる。戻して逆方向に捻ると、元通り、インパクトの瞬間に刃が飛び出すようになり、さらに捻ると刃が飛び出さなくなり、さらにもう一度捻ると、今度はしゅんと縮んで小型のナイフほどのサイズに縮んでしまった。
案内人はこんな機能があるなんて一言も言っていなかった。たぶん試作品だからということで、性能を完全には把握していなかったんだろう。
「それ、オルの試作武器でしょ? まぁまぁ面白いじゃない」
「そうでしょうね。きっと酔っ払った勢いで作って飽きて捨てたのを、誰かが拾って倉庫に移したんでしょうね。式がめちゃくちゃだし、未完成だわ」
「え? コレ、オル様が作ったんすか!? てか作れんすか!?」
ヒーゼリオフがティクトレアの手元を覗き込んで、衝撃の発言をした。
「アンタなに言ってんのよ。武器作りはオルの趣味でしょ?」
「オルは色々と変なものを作るけど、特に好きなのは武器よね。イラヴァールで魔術の研究が盛んなのもオルが新しい武器に目がないからなのよ?」
二人は市民なら知ってて当然だろうと言いたげな口調で肩を竦めた。
私が心の中で大絶賛した武器が、まさかあのバカ飼い主のオルナダの作品だなんて。いや、そりゃ、魔王と呼ばれる魔族である以上、なにができてもおかしくはないんだけど、なんというか、こう、ショックだ。
「ムカつくけどさすがはオルの武器ね。あんまり手を加えるトコないわ」
「そうねぇ。元々ヒューマー向けの作りになってるし、ぐちゃぐちゃのトコ整えて、完成させるだけで十分そう」
「じゃあ、とりあえずこの重複してる部分はまとめちゃうわね」
「ちょっと、あなたはそんなに魔術は得意じゃないでしょう。私に任せてくれない? その記述だと処理が重くなるわよ?」
「このくらいは普通にできるし、武器は速度より式自体の強度が優先だからこうしてるの! ていうかアンタこそ武器向きの術式ヘタクソなんだから黙ってなさいよ!」
ティクトレアとヒーゼリオフは棒を奪い合いながら、元々表面に書き込まれている術式を魔法でうねうねと動かして、別の式に書き換えていく。ああでもないこうでもないという言い合いの中、行ったり来たりする棒を眺めていると、下手すりゃ劣化するんじゃないかという不安が沸き起こった。
やがて二人は「こんなところで良いでしょう」と争うのを止め、私に棒を投げてよこした。
棒の見た目はや重さに変化はない。さっきティクトレアがやっていた変形も試してみたけど、これもなにも変わってないように見える。軽く振るってみても、筋力強化等がかかっている感触もない。
「えーと、これってどういう仕様の武器だったんすかね? 私、刃が出る棒としか聞いてないんですけど」
「あら、そうなの? まぁ、試作品だったものね。なかなか多機能よ。まずはさっきも見せたように、真ん中を捻って有効術式を変えることで、双頭槍モード、分解モード、飛び出し槍モード、棒モード、収納モードの、五つの変形ができるでしょ」
「さらに、双頭槍モード、分解モード時は、ちょっと魔力を流してやれば、刃の形が変わるのよ。こんな感じで」
変更箇所の検討がつかなかったので、仕様を尋ねると、二人は喜々として解説を始め、ヒーゼリオフは私から棒を取り上げて実演をしてみせた。
刃の形状は、飛び出しモードで出てくるダガーのような細身の刃、矢じりを片手剣サイズにしたような底辺が真ん中で凹んだ三角形の刃、ほとんど斧なんじゃないかと思うほど大きな波型の片刃、細長く先の尖った棒が三叉に分かれていて真ん中の棒が長い形状の四種類。最初の二つはまぁ普通だけど、斧サイズのは持ち手のほうまで大きく刃が伸びていて、双頭槍モードではほとんど両剣、分解モードでは重片手剣最後のようなフォルムになっている。最後のに至ってはもはや刃ですらない。
「これ、実用性としてはどうなんすかね?」
「別に悪くないでしょ。扱いが難しい形状もあるから、完璧に使いこなすなら相当訓練しないとだけどね」
ヒーゼリオフはひゅんひゅんと音をさせて棒を振り回しながら、次々に形状を変えて実演をしてみせた。その動きはどの形状であっても洗練されていて、達人級の腕前であることがわかる。極拳の魔王なんて呼ばれるくらいだから、得意なのは格闘なんだろうけど、武器の扱いにも長けているらしい。
「それから棒の部分は、硬度や大きさ、重さを変えられるのよ」
「そうそう。魔力流し続ければ、その間はどんどん伸びたり、重くなったりするわね」
ティクトレアが口を挟むと、ヒーゼリオフは空に向かって棒を伸ばしてみせる。あっという間に先端が見えなくなった棒は、直後に私の三倍ほどの太さになり、一瞬で元の大きさに戻ってから、ロープのようにくにゃくにゃになった。
「この通り、自由自在よ。名付けて『如意槍』ってトコかしらね。一応、戻すときは一回流すだけにしたりとかして、限界まで消費量削ったけど、ヒューマーはそもそも魔力量ないから使い所は見極めて使いなさいよ」
「あとは所有者登録して、シシィくんしか使えないようにしたら完成ね。そしたら発声コマンドで呼んだら飛んでくるようになるから」
ヒーゼリオフがふにゃふにゃになった棒を私に手渡し、ティクトレアが魔法で仕上げを施した。どうやらこれでこの棒、もとい、如意槍は私専用になったらしい。
「こんな高機能・高性能な武器を専用にしてもらっちゃっていいんすか……?」
「良いと思うわよ。試作品庫って実質オル用のゴミ箱だし。オルにはわたくしから言っておくから、遠慮なく使って」
「性能的にも市民に与える武器としてはゴミだしね。兵士は色々できるヤツより、剣なら剣、槍なら槍を極めてるヤツのほうが使いやすいし強いもの」
「な、なるほど。そういうことならありがたく使わせていただきます」
私はヘニャヘニャの如意槍を強く握り、魔力を流して元の形状に戻して、軽く振るってみた。
ぶるぶるっと足元から武者震いが起こる。ヒーゼリオフの言う通り、扱えるようになるにはかなりの鍛錬が必要になりそうだけど、これを使いこなせれば、C、いや、Bランクにも手が届くかもしれない。武器も防具も、戦闘力を引き上げられるものを手にするのは、地道にコツコツ頑張って、うんと金を貯めてからになると思っていたから、これで私の人生設計は確実に十年は前倒しになったと言って良い。命がけで参謀を買って出た甲斐があったというものだ。
「戻りましたぁ。あれ、シシィ、その武器どうしたの?」
「おう、おかえり。なんかこの棒、変形するヤツだったらしい。未完成だったんだけど、ティク様とヒー様が完成させてくれてこうなったんだよ。ほかもヤベェぞ、ほら!」
私は魔族らに約束した通り、戻ってきたフューリに装備を見せびらかして、思い切りはしゃいでみせた。ジャンプして筋力強化の効果を見せ、軽く攻撃を受けてもらい、武器と防具を一つずつ持たせ、そこに施された魔術が如何に素晴らしいかを語る。語るうちにテンションが上って、自分のだけでは飽き足らず、ルゥとヴィオレッタの装備についてまで解説してしまった。それほど魔族らの魔術は素晴らしかった。もちろん如意槍が元々はオルナダの作品だってことを伏せるのも忘れない。
「お前がもうちょっと魔法と魔術勉強してれば、この感動を共有できんのになぁ~」
「ご、ごめん……。で、でもすごいのはわかったよ。シシィのパワーが倍になってるし、このお面も内側から見ると透明で視界を妨げないし、スライムがついてるし……」
「イラヴァールじゃ、そういう面とか兜系の防具は、透過の術がかかってんのがデフォだって……。内側についてるスライムで目を保護するのもな。それよりこの熱探知のがすげーだろ。ほら、熱源の輪郭が見えるから、物陰に隠れてる敵がいてもわかるんだぞ! これってのはつまりさ……」
「普通に術式を書くとこうなんでしゅけど、この術式はこの通り読み取りづらくなっていて、さらに、トラップが仕込んであって、そのまま書き写しても動かないようになってるんでしゅよ! 万一盗られても複製され難くなっていて……」
「殿下の装備にも全吸式化も当たり前のように施されていますが、通常の魔法が自分の魔力と取り込んだ魔力を練り合わせて放つものであることからもわかるように、術式の発動に必要な魔力をすべて取り込むということ自体非常に高度な……」
いまいちピンと来ていないフューリがもどかしくて、ついつい熱い語りを始めると、ルゥとヴィオレッタも同じように語りだした。普段よりも神妙な顔をして話を聞いたフューリは、無茶苦茶すごいということだけは理解したようで、目をまんまるにして魔族らに「やっぱり魔族ってすごいんですね」なんて声をかけた。その反応に、ティクトレアとヒーゼリオフは満更でもない顔をする。フューリも尊敬の念を深めたようだし、とりあえず約束は果たしたと言って良いだろう。
私はルゥとヴィオレッタの話に相槌を打つフューリを横目に、すすすっとティクトレアとヒーゼリオフの間に移動して「獲物のコト聞いてみてください」と耳打ちする。
魔族たちはピクリと耳を動かし、
「「ところで氷平陸魚は獲れたの?」」
と、すかさず問いを投げかけた。
「は、はい! たくさん獲れました! 美味しかったです! 魚なのに本当に足が生えていてビックリしたんですけど……」
フューリは魔族たちを振り返り、ピンと耳を立てて饒舌気味に語りだす。ティクトレアが語る氷平陸魚や、ヒーゼリオフが語る保存法や食べ方に興味深げに相槌を打って、ふりふりとしっぽを揺らした。私の思惑通り会話は弾んで、三人とも楽しそうだ。約束以上の働きをしたわけだから、これで私の評価はぐっとアップしたはずだし、如意槍の礼にもなっただろう。
「さぁて、じゃあそろそろ私らは猿狩りに行きますか」
私は如意槍を掲げて、ルゥとヴィオレッタに目配せをする。二人は頷いて山賊猿がいる方向へ歩きだす。ガーティレイは突っ立ったまま動かない。よく見ると全身鳥肌だらけだし、肌が紫色に変色している。
「えっと……。ガーさん、大丈夫っすか?」
「もももももももももも……」
たぶん問題ないと言いたいんだろうけど、どうみても問題でしかない。きゃっきゃうふふしてるお魔族様方の邪魔をするのは気が引けるけど、装備に温度調節かなにかつけて貰わないと、出発できなさそうだ。
私は振り返って魔族たちに声をかけようとしたけど、その瞬間にガーティレイの全身がパッと紫色の光に包まれた。光が消えるとガーティレイは「あれ? 寒くないぞ?」みたいな顔をして、何事もなかったかのように斧を担ぎ上げ「早くしろ、行くぞ」と先頭に立って、のしのしと歩きだした。
第十六話公開しました。
ギミックが凝った変な武器とかワクワクするよね。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!