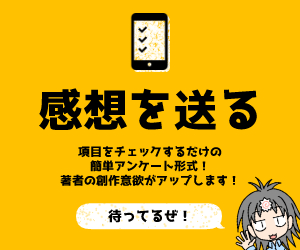ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第二十四話の続きになります。
第二十四話までのあらすじは以下のような感じです。
単身遠征をなんとか阻止したいフューリはシシィに相談し、ヒーゼリオフとティクトレアに相談する機会を作ってもらった。しかしそれは相談に乗るという名目でフューリとデートをするための時間であった。そんなこととは知らないフューリはヒーゼリオフと共にイラヴァールの市内を散策し、デートの終わりに有用な対策を約束してもらい、ティクトレアの元へ向かった。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下二十五話です。
【フューリ 二十四】
震えるオルナダ様を抱き、背中を撫で続けること数時間。
雷鳴はすっかり聞こえなくなり、ロスノー洞の底からでも、星や月が見えた。
『いや、実に見事な戦いぶりだったぞ。扱いの難しい魔装でデカイ剣を作って、こうズバッと首を刎ねてな』
「ほほう。それは見物だったろうな。よし、データを全部よこせ。俺が再現映像を作ってやろう」
オルナダ様とミニナダ様が、魔法で浮かせた僕のお腹の上で楽しげにおしゃべりをしながら、地上を目指し大穴をふわふわ上っていく。
オルナダ様がやられてしまったかもしれないと聞かされたときは、本当に生きた心地がしなかったから、こうして笑顔のオルナダ様を眺めていると、目からジャブジャブと幸せを注がれるような感覚になる。こうしているだけで、痛みと疲労がどこかへ押し流されていく気がする。もう指一本動かせないし、全身が内側から突き刺されているみたいにジクジクするけど、血や汚れは取り除いてもらいサッパリしていたし、僕はとても良い気分だった。
「しかし、俺やヒーゼリオフが苦戦した蛇に勝つとは。戦闘が苦手ってのは、やっぱり大嘘だったな」
「ええ!? う、嘘じゃないですよ? 負けたことはないってだけで、苦手は苦手で……。あ、あの蛇だって、一撃で仕留められなくて、無駄に苦しませてしまいましたし……。解体もちゃんとできなかったので、きっと肉も内蔵もダメになってますし、皮だっていっぱい傷をつけちゃって、その上、切り分けてしまいましたし、駆除が目的だったとしても、狩人としては二十、いえ、十点のくらいの仕事で……」
話せば話すほど、頭の中に「もっとこうしていれば」という思いが湧いて、段々と声が小さくなった。
そもそも狩りの範疇を超えた、命懸けの戦闘に身を投じた時点で、狩人失格。母さんなら容赦なく零点をつけるだろう。それもお説教のおまけ付きで。
『意外と自分に厳しいヤツだな、お前』
「ふっ。職人気質というやつか。狩人としてどうかは知らんが、俺の犬としては上出来だ。誇っていいぞ、フューリ」
「は……、はい!」
僕の上に寝そべったオルナダ様が、笑って頭を撫でてくれた。
頭の中で怒りまくる母さんが一瞬で消えて、胸がじんとなる。
「死骸を引き上げてイラヴァールに戻ったら、盛大な宴を開かないとだな。なんてったって、俺の飼い犬が魔族も手を焼くレベルの厄災を、単身で退けたんだ。対処に招集した連中にも、うんと自慢を……」
「あ……。えと、オルナダ様、そのことなんですが……。あの蛇はオルナダ様か、キャサリーヌ教官がやっつけたことにしていただけませんか……?」
「うんうん、そうだな。飼い犬の手柄は、飼い主が掻っ攫……、って、なにぃ!? なぜだ!?」
『そうだ、なぜだ!?』
胸にぺとんと頬をつけていたオルナダ様と、ふわふわ飛んでいたミニナダ様が、ガバッと僕を覗き込む。
「そ、その……、あの蛇を一人で倒したなんて知られたら……、僕、魔族の方と同じくらいの戦闘力があるとか、思われそうで……」
「それがどうした? 事実だろう?」
「だ、だとしても……。僕はオルナダ様やほかの魔族の皆さんと違って、身体も大きいですし……。し、市民の皆さんを怖がらせてしまうんじゃ、ない、かなと……」
「おうとも。大いにビビらせてやると良い。舐めたヤツがいなくなるぞ」
「ぼ、僕は、怖がられるよりは、舐められていたほうが良いです!」
「む……。そうなのか?」
僕が答えると、わははと笑ったオルナダ様が、むーんと唇を尖らせる。
「ぬー……。しかし、こんな大活躍は滅多にないぞ? お前にとっても名誉なことだと思うが……」
『そうとも。称号つけてやっても良いくらいだぞ』
「オルナダ様に飼われる以上に名誉なことなんて、ないと思いますけど……」
「そ、それはそうだが……。だが……。だが俺はお前と凱旋用の竜車に乗って、市中を練り歩きたい!」
「あ、それはもちろん、お供します。飼い犬ですから!」
『んなとこで、キリッとするな!』
「ったく、しょうがないヤツだ。俺とキャサリーヌも一緒に戦ったことにしてやるが、あくまで共闘だからな!」
「はい、ありがとうございます! あ、割合はオルナダ様が九で、僕は一でお願いします!」
「はぁ!? お前が九に決まってるだろ!?」
「そ、それはちょっと……。八二ではどうです? 僕が二で……」
『ダメに決まってるだろ!』
「がー、もー! なら五五だ! これ以上は譲らんぞ!」
「えと……、七三では……?」
「譲らんと言ったろうが! この、この、こうしてやる!」
『そうだ、やってやれ、本体!』
「わ、わはっ! オ、オルナダ様、くすぐった……、あた、いた、痛いですっ! あははっ!」
しつこく交渉する僕を黙らせようとしたのか、オルナダ様が脇の下辺りをつついてくるので、僕は身を捩るほど笑ってしまった。全身の魔力系にビシビシと痛みが走ったけど、なんだか楽しい気分だった。
程なくして、僕たちは蛇の残骸の散らばる地点に到着した。
先に着いていたキャサリーヌとティクトレアが飛ばしたらしい光る球体が、付近を明るく照らしていた。
「あぁ、フューくん、会えて良かった!」
僕らの姿を見るなり、ティクトレアが小走りに駆け寄ってきた。
「怪我はない? 回復魔法かけましょうか?」
「魔力系がダメになってるから、回復は受け付けないぞ。血みどろだったが外傷もなかったしな」
「オルに聞いてないんだけどな?」
「えと、閣下こそ、お怪我はなかったですか? その、内蔵ごと投げたりして、すみません……」
「そんなの良いのよ。わたくしを助けるためにしたことですもの。あんなに身体を張ってくれて、感激よ!」
ティクトレアは仰向けに浮いた僕の頭を、ぎゅっと抱きしめて、ほっぺたに唇を寄せ、触れるかどうかというところで目の前から消えた。
「ふぅ……。危なかったわ」
「ヒ、ヒーゼ!? あなた、よくも……!」
「つーか、今、俺ごと蹴飛ばす気だったろ、おい」
首を反らして声のほうを見ると、オルナダ様が呆れた顔でヒーゼリオフの横に立っていた。
奥にいるティクトレアが赤くなった鼻を抑えているから、たぶんヒーゼリオフに顔面を蹴り飛ばされたんだろう。なんでそんなことしたんだろうか、と僕は困惑したけど、三人がわいわいと騒いでいるのを眺めていると、しみじみと事態の収拾を実感して、すぐにどうでも良くなった。
程なくして基地から続々と部隊がやってきた。
大蛇討伐のための編成になっているのか、大砲のついた大型の乗り物がいくつも連なって、先頭ではブゥプが指揮を取っていた。その乗り物の一つからシシィたちが飛び降りて、僕のところへ走ってきた。
僕は抱かれた赤ん坊か、首根っこを掴まれた猫のような姿勢で浮いたまま、無事を報告した。
「てか、無傷かよ!」
「フューしゃん、丈夫過ぎでしゅ……」
「さすがでございます、殿下!」
「いや、魔力系が全滅で、もう動けないから無傷ってわけじゃないよ」
傷を自己回復し、オルナダ様に血や泥を落としてもらっていた僕は、ちょっと制服が破れているだけで身体は完全に無傷だったので、みんなはちょっと驚いた様子だった。でもガーティレイだけはいつも通り不服そうに鼻を鳴らして「あの蛇は私の獲物だったのだぞ」と凄んできた。
「あー……。蛇は僕じゃなく、オルナダ様がやっつけたので……」
「そ、そうか! ふふん、まぁ、当然そうだろうな! おい、オルナダ。貴様、私の獲物を横取りした落とし前をどうつけるともりだ?」
「あれは俺じゃないぞ。キャサリーヌに言え」
「む。あの老いぼれがか……。ぬぅ……」
僕がオルナダ様を指すと、ガーティレイはなぜか嬉しそうに目を輝かせ、オルナダ様の返答を聞くと、今度は苦虫を噛み潰したような顔をした。たぶんキャサリーヌに同じように絡んだら、容赦なく引っ叩かれるからだろう。それでも結局「やい!」と絡みに行くのだから、ある意味尊敬する。
「ま、さすがに倒すまではいかないしても、結構活躍したんだろ? 還元、がっつりできたんじゃないか?」
「どうだろ? 害獣駆除なんて、別にやりたいことじゃないし。それにあの蛇もあんな状態にしちゃったし……」
シシィにポンポンと肩を叩かれた僕は、ちらりとバラバラになった大蛇の身体を見る。
光の下で改めて見ると、鱗には大量の傷が付いてるし、ぶつ切りにしたせいで肉の旨味が流れ出てしまっている可能性が高い。やっぱり狩人は、狩れる範囲の獲物を狩らないとダメだな、と僕はため息を零した。
同時に「還元したいなら自分のやりたいことで」という要求のハードルの高さを改めて感じた。
「ったく、生真面目なヤツだな……。てか、あの人、そんな細かいこと気にするタマじゃないだろ」
「そ、そうかな?」
「聞いてみりゃ良いだろ。オル様~! 今回のフューリの活躍って、十分還元になってますよね?」
シシィが手を上げて声をかけると、ブゥプを始めとした指揮官らしい人々と事後処理について話していたオルナダ様がこっちを向いて親指を立てる。
「ほらな。ドーンと胸張っとけよ」
『そうだぞ、フューリ』
「そうでしゅ」
「我も同感であります」
「よくわからないけれど、わたくしもそう思うわ」
「よくわかんないけど、ヒー様もよ!」
「え……。で、でも、オルナダ様がつけた条件だし、そんなはず……」
ミニナダ様を含め、みんながシシィの意見に同調したので、僕はちょっぴり困惑した。
もしも本当に「やりたいことで」という条件がないのなら、ここ最近、思い出しては悩んでいた、あの時間はなんだったのかという話になる。自然と眉間にシワが寄った。
そのままうんうんと唸っていると、オルナダ様が「面白い顔になってるぞ」と僕のおでこを突いた。
「どうした? キレイに仕留められなかったのが不満か?」
「あ、はい。それもあるんですけど……。その、僕、蛇の駆除はやりたくてやったわけじゃないんですけど、本当に還元できたことにしてもらって良いんですか?」
「なにを言ってるんだ、お前は。なにで還元しようが、還元は還元だろ」
「え? で、でも、やりたいことで還元しろって、オルナダ様が……」
「ふーむ、言葉が足りなかったか……。あのな、お前は俺の飼い犬だから、俺にはお前を、少なくとも不幸ではない状態に保つ義務がある。これは還元云々以前の大前提な。なのにお前が、周りの期待に答えようだのなんだのして、やりたくもないことに躍起になって、精も根も尽き果てたりしてみろ。俺が困るだろ。やりたいなら、やりたいことでってのは、そういう意味だ。そもそも気にしなくて良いと言ったはずだが?」
オルナダ様が困ったように頭を掻いたのを見て、僕は唖然としてしまった。
思わず首をぎぎぎと回して、同じく飼い犬を持つ、ヒーゼリオフとティクトレアを見る。
「信じられないんでしょうけど、マジよ」
「うちもそれのおかげで手を焼かされてるわ」
二人が頷くと、シシィが「チート職つーか、もうペットじゃん」と呟くと、オルナダ様たちは「だから飼い犬って名前なんだ」と肩を竦めた。
どうやら僕の悩みは、本当に完全な無用の長物だったらしい。
魔法で浮かされていなかったら膝から崩れ落ちているところだ。ものすごく深くて、長いため息が零れた。
だけど同時に、通り抜けた夜風が、胸のつかえや、全身の強張りをさらっていった気がした。
「さてと、動ける部隊は粗方集まったようだし、一度回復かけるか。ティク、頼む」
「了解。はーい、じゃあ回復が必要な子たちは、できるだけ近くに集まって。フューくん、見ててね。いくわよー!」
オルナダ様は僕が肩の力を抜いたのを見て、パチパチと指を鳴らした。
指示を受けたティクトレアは、なぜか僕にウインクをしてから、上空に巨大な魔法陣を描き出す。魔法陣から地上へ向かって筒状に光が下り、その表面を呪文の帯が、文言を変えながらぐるぐると回った。
やがて文言の書き換えが終わり、ティクトレアが「そぉれ!」と声を上げた。
負傷者の身体が紫色の魔力光に包まれ、光が消えると、皆それぞれに感嘆の声を上げ、傷のあった箇所をしげしげと眺めたり、ぐりぐりと身体を捻ったりして、回復具合を確認する。シシィたちも疲労が消えたようで「相変わらずやべぇな」と笑い合っていた。魔力系の損傷で回復対象から除外された僕は、それがちょっぴり羨ましかった。
「あとは基地に置いてきた重症者だな。パパッと転移して治療しといてくれ」
「はいはい。まったく、オルは人使い荒いんだから」
「お前の飼い犬の不始末のせいなんだから当然だろう」
「は? あなたが階層を増やしたり、転移門を放ったらかしたりしたのが原因でしょ?」
「俺はちゃんと結界張ってたし、転移門だって隠してた!」
周囲が喜びで沸く中、オルナダ様とティクトレアは言い合いを始めた。話の内容はよくわからないけれど、子猫がじゃれ合っているようで、可愛らしい。
うっとりと眺めていると、ふと、空気中に漂う魔力の匂いが、少しずつ濃くなっている気がした。
「う、うわああああああああああっっっ!!」
叫び声を振り返ると、ぶつ切りになった大蛇の胴体が紫色に発光していた。
魔装だ。
首を刎ねたときと同じように、魔装同士が繋がって、大蛇はずるりと起き上がり、耳を劈くような咆哮を上げる。
「どぅおわあああ!!」
オルナダ様が声を上げ、右手を大蛇に突き出す。
パァンと乾いた破裂音がして、辺り一面にドザーッと血肉が降り注ぐ。
僕を含め、その場にいた市民たちは、ほとんど全員が血塗れになってしまった。
「あー、ビックリした」
「ち、ちょっと、オル! 申請通ってるからって、こんなレベルの魔法撃つことないでしょう!」
「そうよ! みんな血だらけじゃないの!」
「ついうっかりだろうが、そう目くじらを立てるな。大体、撃てるときに撃っとかんと、もったいないだろう」
「「全然うっかりじゃないじゃない!!」」
悪びれる素振りもないオルナダ様に、ティクトレアとヒーゼリオフが怒鳴り声を上げた。
僕は呆然として、三人のやり取りと、元の形が想像できないほど細かい挽肉になった大蛇の残骸を見つめ、
「なんてことを!!」
と大声で叫んでしまった。
その場の全員が僕らに視線を集め、オルナダ様は小さく「すまん」と呟いた。
【フューリ 二十五】
スタンピード事件によって、文字通り指一本動かせない状態になった僕は、絶対安静を指示され、丸々一週間も寝込むことになった。魔力系の損傷が酷く、魔法で治癒できないということはともかく、回復を早めるために、魔力を含む食事や、オルナダ様の〝食事〟のお相手を禁止されたのは、とんでもなく辛かった。
寮で寝ている間、みんながちょくちょく、肉料理を持ってお見舞いに来てくれたけど、生の肉や内臓を貪り食いたい衝動は強まるばかりだった。オルナダ様の上下の唇が恋しい気持ちも。
ということで、ようやく動けるようになった僕は、早朝から狩りに出掛けて、食べられるだけ獲物を食べ、昼前にイラヴァールへ戻り、うきうき気分で中央区の鐘塔にやってきた。回復具合をオルナダ様に伝えたらお呼びが掛かったのだ。
ランチか、ディナーか。
できれば、ディナー、いや、両方でお願いします! とドアに願を掛けてから、中に入った。
室内は昼間だというのに怪しく薄暗く、薄手のローブを着たオルナダ様がベッドに横たわっていた。
んだったら良かったんだけど、訪ねた部屋は、ロスノー洞の調査結果報告会が行われた会議室と同じような、長テーブルと装飾品があるだけの部屋だった。中にいた人物も、オルナダ様だけじゃない。ユミエール、ブゥプ、キャサリーヌ、ティクトレア、ヒーゼリオフも一緒だった。ほかにも胸に徽章をずらりと並べた、いかにも偉い人、といった風防の人々が数名、難しい顔をして席に着いていた。
「さぁて、主役が到着したぞ!」
部屋に入ると、オルナダ様はぴょんと椅子を飛び降りて、僕の手を引き、自分の隣の椅子に座らせた。
「それじゃ、フューリちゃんも来たことだし、この都市の新たな主戦力のPRプランについて……」
「前置きは良い! 俺が夜なべして作った傑作を見ろ!」
ユミエールが議題の説明をしようとするのを遮って、オルナダ様はパチンと指を弾く。
部屋のカーテンが一斉に締まり、照明が消えて、長テーブルの中央に四角い魔光板が現れる。魔光板にはスタンピード発生前のロスノー洞を上から眺めているような場面が映し出された。
入り口があった場所から、紫色の光の柱が上がり、ぽっかりと穴が空いたかと思ったら、現地にいた作業員の人々が逃げ惑う光景に切り替わる。『一体なにが起きたんだ!?』と叫び混乱する人々を次々と映し、続いてイラヴァールでオルナダ様が対応を指示する様子に変わる。そんな具合で場面がぽんぽんと切り替わり、あの日の出来事を細切れにして、ぎゅっと縮めたように進んでいく。
やがてオルナダ様が雷に打たれるショッキングな場面が映り、そして魔光板にあの日の僕らパーティの姿が映し出される。
『オルナダが倒れた今、もうお主がやるしかありませんわ』
魔光板の中のキャサリーヌが、隣りにいる人物の肩に手を置く。
短く『はい』と答えて立ち上がった人物は、僕だった。
『イラヴァールの平和は、僕が守ります!』
僕は言った覚えのないセリフを吐き、二本の大剣をカッコよく構えて、大蛇に向かって行く。そして復活したオルナダ様、キャサリーヌの支援を受け、あっという間に大蛇を倒してしまった。
「どうだ。なかなか良い出来だろう?」
「ままま、まぁまぁね! もっと画質の高いヤツがあるなら、買ってあげても良いわ!」
「わ、わたくしは、編集前のマスターデータも含めて、買い取りたいですわ!」
「そうねぇ。じゃあこのくらいでどう?」
「ユミエール、俺の作品を安売りしようとするな」
魔光板が消え、室内に明かりが戻ると、どういうわけかヒーゼリオフとティクトレアが、ユミエール相手に値段の交渉を始めた。
状況がさっぱり飲み込めない僕は、目をぱちくりとさせて、オルナダ様を見つめた。するとオルナダ様はニヤリと笑って、
「カッコよくできてるだろ? この間は大活躍だったからな、こうしてあのときの様子を映像にしてみたってわけだ」
と、得意げに胸を張る。
「あのときのって……。で、でも僕、あの、さっきので、身に覚えがないことをしたりしてたんですけど……」
「それは脚色ってヤツだ。お前の希望も取り入れないとだったし、事実をそのままってのも味気ないだろ?」
「は、はぁ……」
「この映像をステボに載せて流して、お前の勇姿を広く世に知らしめてやるんだ。いやぁ、楽しみだな!」
「よ、良かったですね!」
はっはっはっと楽しそうに笑うオルナダ様に、思わず頷いてしまったけど、ステボに載せて広く世にってもしかして……。
「あ、あの……、オルナダ様……。さっきの映像って、まさかステボを使える人はみんな見れるようになったりとか、はしないです、よね?」
「なにを言ってるんだ。ステボの有無に拘わらず、見られるようにするに決まってるだろう。ひとまず市街の至るところに映像出力用の魔術器を設置して……」
「は……? え……? ダ、ダダダ、ダメですよ、そんなの!!」
「照れるな、照れるな。最高にかっちょいい二つ名も考えてあるんだ! 人呼んで『イラヴァールの青い怒鎚』!! 魔族もビビる雷の名をつけたんだ、痺れるだろ?」
「わたくしはどうかと思うけど……」
「そうよ! もっとカワイイのなかったわけ!? べ、別にどうでも良いけど!」
「オルのセンスはともかくとして、フューリちゃんが新たにイラヴァールの主戦力に加わったことを、近隣諸国にアピールするのは良いことね」
まったく意味がわからない。
だけど、寝込んでいる間に恐ろしい計画が進んでいた事だけは確かなようだ。
「ででで、でも! 僕、全然言ってないこと言ってましたし、知らない武器を振り回したりもしてて! そ、それに身体も一回りくらい大きくなってるような気もしますし……!」
「おう。ちょこっと盛ってみた。いい塩梅だろ?」
「だ、だとしても、こんなのみんなに見せるなんて……。その、とても、い、嫌です……」
「な、なに! なぜだ!?」
「だ、だって、強いと怖いと思われるじゃないですか!! ぼ、僕はイラヴァールの皆さんと仲良くしたいので、その……」
オルナダ様はたぶんきっと僕のために、あの映像を作ってくれたんだろうけど、あんなのを見られたら、僕があの大蛇を倒せるくらい戦闘力が高いと思われてしまう。それが本当のことだとしても、知られれば、故郷にいた頃と同じように恐怖の対象になってしまうに違いない。今まで普通に接してくれていた街の人達も、姿を見るなり逃げ出すようになってしまうかも。
そうなれば僕はまた、友達の一人も作れなくなってしまう。
オルナダ様には申し訳ないけれど、映像の公開はなんとしても避けたい。
「お前は舐められやすい顔をしているんだ、ビビらせたほうがこの先楽だぞ!?」
「だ、だとしても、嫌です!」
「なんだ、どこか気に入らんとこでもあるのか? なら修正してやるぞ」
「じ、じゃあ、僕のところ全部消せますか!?」
「んなっ! 消したら意味ないだろうが!!」
「う、ううう……。じ、じゃあ、やっぱり嫌です……」
「なぜだ!?」
堂々巡りの問答がしばらく繰り返された。
オルナダ様は色々な提案をしてくれたけど、公開自体、御免被りたい僕はただただ「嫌ですぅぅぅ!」と首を振るしかなかった。ひたすら拒否し続けたけど、オルナダ様はなかなか折れてくれない。
追い詰められた僕はつい、
「そ、そんなのが公開されたら……。ぼ、僕は、ふ、不幸になる、かもしれませ……ん……」
なんて口を滑らせてしまった。
オルナダ様は僕が不幸になったら困ると言っていたから、こう言えばやめてくれるかも、と思ったのだけど、どう考えても、さすがに言葉が過ぎる。
「あ、いえ、その……。も、もちろん、オルナダ様の飼い犬でいられることは、最上級に幸せなんですけど……。だ、だからこそ、そこに水を差されたくないというか……。あ、み、水といえば、最近、僕、ずっと寝込んでいて、あんまり会えなかったですし、なんというか、二人で、水入らずで、ディナーとかどうかなとか……」
なんとか自然に話題を逸らせないかと言葉を繋ぐけど、だいぶ不自然だった上に願望が漏れてしまった。
オルナダ様は腕組みをして、「むーん」と眉間にシワを寄せる。
「ふー……。仕方ない、この件は一旦保留としよう……」
「ほ、本当ですか!?」
「あくまで保留だぞ。良い落とし所を見つけたら、また交渉するからな」
「は、はい! ありがとうございます! 嬉しいです!!」
僕はオルナダ様の前に両膝をついて、細い身体をぎゅっと抱きしめた。
顔の横でぶぅぶぅと不満を言われたけど、久しぶりに味わうオルナダ様の体温や肌の匂いが愛しすぎて、甘い囁きのように感じられる。背後で室内にいた人々が次々に立ち上がり、ゾロゾロと出ていったけど、まるで気にならなかった。
「えーと、取り込み中ごめんね、フューくん。さっきの映像だけど、わたくしが個人的に見るのは構わないかしら?」
「え?」
「さすがにそのくらい構わないだろう? あの力作が誰の目にも触れずに丸ボツではあまりに可哀想だろう、俺が」
僕は気が進まなかったけど、オルナダ様にこう言われては、頷くしかない。
「は、はい。じゃあ、ほかの人が見ないなら……」
「な、ならヒー様も買い取るわ! い、一応、ヒー様の活躍シーンもあったしね!」
「自分が無様にやられるトコが見たいのか? 変なヤツだな」
「うっさいわね、別に良いでしょ! 大体、無様にやられたのは、アンタも一緒でしょ!」
「あの雷じゃしかたないだろうが! ほぼ直撃だったのに、こうして生きている凄さのほうが……」
「はいはい、そこまで。映像公開の可否はともかく、フューリちゃんの能力は、今後もイラヴァールのために広く活用させてもらいたいんだけど、その点はどう?」
ヒーゼリオフが話に加わり、オルナダ様と言い争いを始めると、ユミエールが割って入った。
広く活用ってなにをさせられるんだろう? ユミエールにはついこの間も僻地に送られそうだったし不安しかない。
「え、と……、僕はただの狩人ですし……。狩りと料理と素材の加工と、あとは最近覚えたマッサージくらいしかできることがないので、イラヴァールのために広く、なんてとても……」
「なにを言う! この際はっきり言っとくが、お前は魔族相手でも良い勝負ができるくらいの戦闘力がある! おまけに多芸だ! 冒険者で言うならトリプルSランクパーティと同等くらいのレベルなんだぞ?」
「あ、あはは……。褒めていただけるのは嬉しいですけど……、それはさすがに欲目じゃないかと……」
「なに言ってんのよ! 客観的に見てもアンタはそのくらいでしょ! なんか狩人ってとこで卑下してるみたいだけど、狩人は冒険者の上位互換職だって知らないわけ? べ、別にヒー様の知ったことじゃないけど!」
「え……? いやいやいや、そんなはずないですよ。食べくだけで、ろくに稼げない底辺職でしたよ?」
「それはきっと環境のせいね。ヒューマーの土地は絶妙な位置にあるから……」
「そ、それは、どういう……?」
「レゼリ山岳地帯で取れる素材は、魔導圏やほかの種族の土地では価値があるが、ヒューマーの土地ではほぼ無価値ということだ。交易が少ないせいで売ることもできんし、加工も無理だろう。犬や猫に宝石をやっても喜ばんみたいな話だな」
そんなバカな。
と思いつつ、みんなの顔を見回すと、誰もが気の毒そうにうんうんと頷いた。
「ちなみにお前がトリプルSランクパーティと同じくらいって評価も妥当で、ちっとも欲目じゃないぞ。実際、パーティを組ませたときも、前衛、後衛、盾、指揮、索敵、陽動、解体と、あらゆる役割をこなせたろ? おまけに飯が作れて、応急処置も完璧だ。あの蛇に噛まれたあとの処置は見事だったしな。まさに一騎当千。さすがは俺の犬ってトコだな!」
「そ、そうですか? どれも狩人なら普通のことですよ。えへへ」
「だから上位互換職だと言ってるだろ。ともかく、お前は使えるヤツだってことだ。イラヴァールのために広く活用ってのも、なんなくこなせるはずだぞ」
「ということで、この前相談させてもらった、鉱石の採掘を頼みたいんだけど……」
オルナダ様に褒められて、ちょっぴり浮かれ気分になったところに、ユミエールがするりと仕事の話を滑り込ませる。オルナダ様まで「俺もあの鉱石はほしいんだがどうだ?」なんて言うものだから、うっかりOKしそうになる。
「えぇ~と……、その、ぼ、僕は魔法と武術との訓練を優先したいな~と……」
「なんだ、嫌なのか?」
「はい……」
さっきまで嫌嫌言ってたせいで、つい、ぽろっと本音が出てしまった。慌てて訂正しようとしたけど、それもなんだか今更な気がして、「はい、嫌です」とオルナダ様を抱いていた腕を放し、僕はその場に正座した。
「僕、オルナダ様と、いつも一緒にいたいです……。離れているのが辛くて、ランピャンに行ったときなんか、寂しくて、正直、本当に死にそうでした。だ、だから、その……、僕を使うなら、どうかオルナダ様の側で使ってください」
僕はぺこりと、深く頭を下げた。
オルナダ様は「ふむ」と考えるように鼻を鳴らし、
「なら、お前のパーティに俺も加入しよう」
名案と言わんばかりの笑顔で頷いた。
「「「は、はああああああああああああああああああああ!?」」」
その場にいた全員が、素っ頓狂な声を上げた。
「そうすれば、お前は寂しくないし、俺はお前の活躍を生で見れる上に、仕事もサボれる。最高だろ?」
オルナダ様はからからと笑って、僕の耳をもしゃもしゃと揉む。
ユミエールを始め、みんなが「さすがにそれは」と止めにかかる。
だけどオルナダ様は「これは決定だ」と、まるで聞く耳を持たない。
本気で末端の一パーティの任務に同行する気みたいだった。
王様みたいな立場のオルナダ様は、きっと本当は飼い犬に構ってる時間なんてないだろうに、僕を寂しくさせないためだけに、こんな提案をしてくれるなんて、なんだかイラヴァールの人全員に申し訳ない気がした。でもそれ以上に、胸がじんわりと暖かくて、たまらずオルナダ様を抱きしめた。
「お、なんだ、感動したのか? ふふん、可愛いヤツだ」
オルナダ様は僕を抱き返して、頭をなでてくれる。しっぽがバタバタと激しく揺れた。
「ま、俺に任せておけ。魔族が入ったらパーティランクはつかなくなるが、そんなコト問題にもならないくらい、ぶっちぎりでトップのパーティに育ててやる」
このまま抱き上げて、攫ってしまいたいなんて思っていたら、不穏な発言が飛び出した。
雲行きが怪しい。
「手始めに未攻略のダンジョンを片っ端から攻略するぞ。並行してランクアップ試験をこなす。お前ならSも一発だ。それから……」
「はぁ……。オル、そういう方向で行くなら、イラヴァールの利益になる活動もしてほしいんだけど?」
「おお。なら研究者連中がほしがってるレア素材でも取るか。ちょいちょい戦争仕掛けてくるアホ国家潰すってのも良いな」
「わたくしたち魔族は戦争への介入は禁止でしょ。潰すなら近隣の野党とかにしたらどうかしら?」
「それもそうだな。よし、フューリ、お前を人間を狩る狩人にしてやろう」
「良いじゃない。フュー無双動画が撮れるわね! べ、別に興味ないけど!」
「いや、僕、人を食べるのはちょっと……」
どんどんと話が物騒な方向へ行くので、これはマズイと口を挟むけど、誰一人として止まらない。
「トップ帯にいるパーティを、片っ端から負かすってのも良いな!」
「冒険者パーティ同士で競うようなものなんてないでしょう」
「冒険者パーティ格付けグランプリみたいなイベントを、催したらどうかしら!」
「良いわね。冒険者なんてどいつもこいつも血気盛んだから絶対乗ってくるわよ!」
「あのぅ……」
「確かに開催はできそうね。となると予算と収益は……」
「トップ帯を招集するならば、少しは楽しめそうですわね。ワシも人肌脱ぎますわ」
「殿下ならば優勝間違いなしでございますから、グッズなど用意しておけば飛ぶように売れるのではないでしょうかっっっ!」
「み、みなさん……?」
魔族御三方のみならず、ユミエール、キャサリーヌ、ブゥプまでが話に乗りだす。僕は完全に蚊帳の外だ。
オルナダ様は僕の腕から抜け出て、みんなと一緒にあーでもないこーでもないと意見をぶつけ合う。
ちょっぴり寂しいけど、もう何週間も離れ離れの任務に行かされることはなさそうだし、オルナダ様が楽しそうにしているのを見ていると、自然と肩の力が抜けた。
「わはは。きっと大活躍して、俺の次くらいにモテモテになるぞ、フューリ」
「あはは。僕はオルナダ様の側に居られたら、それで十分ですよ」
「そう言うな、お前がモテれば俺も鼻が高い。それに仲良ししたいんだろ? いくらでもできるようになるぞ」
オルナダ様はふわりと浮かんで僕の腕に収まり、ニヤリと笑った。
「え、えと……。そ、そうなんですか?」
「おうとも。お前と仲良ししたいヤツが列を作るはずだ」
「そ、それは、嬉しいです」
「むふふ。そうだろう、そうだろう。ほかにも良いことがいっぱいあるぞ」
わしゃわしゃと撫でられて、立ち上がったしっぽがパタパタ揺れた。
魔族に飼われる者はすべてを手にする。
この格言でいうところの〝すべて〟が、なにを指すのかはわからない。だけどこうして腕の中で笑うオルナダ様を見ていると、きっとその〝すべて〟には、僕が望む以上のものが多分に含まれているんだろうなと思った。
洗われる犬ってカワイイですよね。猫も。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!