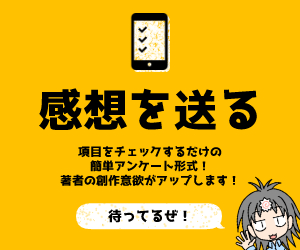Kindleにて出版予定のオリジナルの百合小説です。
価格は未定。7万文字くらいのボリュームにしたいと思っております。
出版開始後に本文は削除するので、今のうちにお楽しみいただけたらと思います。
あらすじは以下のような感じです。
姉を魔王の生まれ変わりと敬愛する、聖麗(ひじりうらら)は、ある夜、性行為中と思しき姉の姿を目撃してしまう。姉に対する幻想を打ち砕かれ、悲しみに暮れる麗に、友人の木下晴(きのしたはる)が、麗の姉が本当にそこまで進んだ交際をしているかを確かめようと提案し……。
以下、本文。
一
思春期に経験したくない出来事、堂々の第一位といえば、親の性行為の目撃である。
聖麗もまた、その衝撃的な体験により、トラウマを負うこととなった。これだけでも十分不運と言えるが、麗の場合、直後、それを上回るショッキングな出来事を目撃してしまったのだから、泣きっ面に蜂も良いところだった。
もうこの世には、一点の希望もない。悲嘆に暮れた麗は、長い、絶望の夜を過ごした。
それでも太陽は無慈悲に昇る。だが家族の顔など、見たくはなかった。早朝、朝食も取らず、逃げるように家を出た。春はまだ先、冷え込んむ校舎が心情に馴染む。冷たい椅子に座り、顔を伏せて、おいおいと泣いた。
麗はひそり静かに悲しんでいるつもりだったが、周囲にとってはサイレンに等しかった。その激しさは、登校して来た生徒たちが、火事を疑い職員室に駆け込むほど。教師さえ近づけず、その嘆きは麗の数少ない友人、木下晴が登校するまで続いた。
「よーし、もう一周行ってこーい」
「うああああああああん! なんで校庭なんか走らねばならんのだあああああ!!」
「あんたが大音量で泣きわめくからっしょー! 叫ぶ元気があるなら、もう二、三周追加だぞー!」
「ああああああああああ!!」
晴に首根っこを引きずられた麗は、校庭へと引っ張り出されていた。そして、たっぷり十周はグラウンドを走らされた。走る間も涙が止まらず、結構なボリュームで泣き叫んでいたが、それも一周毎に小さくなった。麗の鳴き声が、くすんくすんとなってようやく、晴は事情を聞いてくれた。
「それはショックだろうけど、まあ、おかげで通り名が一つ増えたんだし、良かったじゃん」
「よくない! 荒ぶる火災報知器なんて、われには似合わんのだ! われは魔王の実弾なのだぞ!」
晴に連れられてやってきた非常階段。麗は声が響くのもお構いなしに叫んだ。
「……実妹?」
「それ!」
麗は首を捻る晴の鼻先に、指を突きつける。だがすぐに引っ込めて、濡れた目を、茶色いブレザーの袖で拭った。くりくりとしているはずの麗の目は、昨夜から散々こすったせいで、真っ赤に腫れ、普段の半分くらいしか開かなくなっていた。
晴は困った様子でため息をつく。色の薄い髪の毛を、二度ほど指に巻付け、鞄から菓子パンの袋を取り出した。「とりあえず、なにかお腹に入れな」と、パンを半分千切って麗へ押し付ける。麗はもうヤケクソという気分でそれにかじりついた。
麗がもそもそと菓子パンを咀嚼するのを確認し、晴ももう半分のパンを口に入れる。食べながら、晴は麗の背中をゆっくりと撫ぜる。
「アンタもついてないよね」
晴が神妙な顔つきで、慰めを口にした。触れる手の平の暖かさに、麗は少しだけ、気持ちが和らいだ。
お礼を言わなくては。そう思い顔を上げると、晴の表情が口元からムズムズと歪んでいくところだった。麗が眉を寄せたところで、晴はもう耐えきれないとばかりに、噴き出してしまった。
「ぐ、ふふ……。お、親がヤってるトコ見た後、魔王のお姉さんがヤってるトコ見るなんて……。ぶふふ……、ヤ、ヤバすぎて……。ぷはははっ」
昨夜の目撃事件の後、パニックになった麗は、助けを求めて姉の部屋に飛び込んだ。そして、つい先程目にしたのと全く同じ体勢でいる姉と、その友人の姿を見てしまったのだ。
姉を魔王の生まれ変わりと崇拝する麗にとって、それはそれは耐えがたい出来事だった。だが信じがたいことに、麗にとってのこの悲劇的大事件は、晴には噴き出すほどに笑える話らしかった。
慰めてくれたと思っていた友人が、口元を抑えて笑いだしたのを見た麗は、キリキリと赤い目を釣り上げる。品の無い表現をされたことも手伝って、麗の嘆きは見る間に怒りに変わっていった。「なんにも面白くない!」と怒鳴り、晴を睨みつける。
「この世界の! 唯一の希望が! 失われようとしているのだぞ!」
「アンタはいっつもおかしいけど、姉さんがヤってたくらいで”世界の終わり”は大げさすぎ」
「まったくちっとも大げさではない!」
麗は立ち上がり、余った袖から手をいっぱいに伸ばして、大仰に語りだす。
「姉ちゃんはいつか、このクソッタレな世界を征服する、または、滅ぼすお方! だから人間と仲良くするなどということは、断じてあってはならぬ!」
「アンタとお姉さん、家でどんな会話してんのよ」
「そういう話はしないが、魔王がすることといえば、征服か、殲滅なのだ! だから恋愛なんてくらだらないことにうつつを抜かすなど、あるまじき所業なのだ! なのに、あああ、それなのに姉ちゃんは……! われは、われはもう、なにを信じて生きればいいのか……、う、うぅぅ……、うああああーーー」
捲し立てるように語った麗は、肩まで伸ばした黒髪を掻きむしり、また泣きだしてしまった。晴は両耳に人差し指を突っ込んで、「あー、もう、そんなに泣くなってぇ……」と天を仰ぐ。
「てかさぁ、お姉さんたち、裸だったわけじゃないんでしょ? 麗の勘違いなんじゃん?」
「あああああーーー……、…………そうかも」
叫声がピタリと止まる。
麗は昨夜目にした光景を、よくよくと思い出してみた。
直前に目にした両親とは違い、姉の雅は濃い青色のパジャマを着ていた気がする。その脚の間に座った、姉の友人、夏那多もジャージ姿だった。そういえば両親の部屋は、オレンジの常夜灯が点いているだけだったが、姉の部屋には煌々と蛍光灯が灯っていた。
知る限り、そういった行為に及ぶ際は、照明は落とすことになっていたはず。両親の部屋だって、それなりに暗かった。
そうか、なるほど、そうに違いない。きっと全て、自分の勘違いなのだ。
麗はほっと胸を撫で下ろした。
「ま、点けてする人たちも、いるらしいけどね」
「この世の終わりなのだあああああ!!」
「いや、人類滅亡の方が、よっぽどこの世の終わっぽいけど?」
「人間という汚物を消毒しなくては、世界は糞溜めのままなのだあああああ!! あああああ!! すまない地球! すまない生き物たちいいい!!」
「はいはい、人間はバイキンね……」
晴が呆れた視線を送る。まるで舞台に立ったかのように、大仰な手振りで嘆く麗を、頬杖をついて眺めた。ミミズやオケラにまで述べられる謝罪を聞き流しながら、何事か思案するように頭を傾ける。やがて、妙案が浮かんだとばかりに両手を合わせ、口の端を持ち上げた。
「ねぇ、麗。お姉さん、ホントにその人とヤってたのかどうか、調べてみない?」
「みんなみんな生きているのにいいいいいーーー……、…………しらべる?」
「だって麗の話じゃ、お姉さんが友達と二人で、ベッドにいたってことしかわかんないじゃん。尾行して、デートしたり、イチャイチャしたりしてないか確かめるんだよ」
「……お、おおお、なるほど。晴は天才なのだ!」
パッと麗の表情が明るくなる。赤い目を煌めかせて、晴の手をぎゅっと握る。
「晴を姉ちゃんの身辺調査隊隊長に任命するのだ! 良い報告を期待しているぞ!」
「報告て……。なんで私一人で調査することになってんの? アンタが自分で行って確かめなよ」
「で、でも、姉ちゃんのプライバシーを侵害するなんて、万死に値する大罪だし……。それに、目の前でイチャイチャなんてされたりしたら、われは不幸のずんどこに叩き落されてしまうのだ」
「ドン底ね。だけどこのままじゃ、ず~っと、もうなにを信じて良いかわかんない~って、モンモンメソメソすることになるんじゃない? それすごい鬱陶しいんだけど?」
「うう……」
しおしおと、麗の頭が下がっていく。
勘違いだということを証明して、安心したい気持ちはある。けれど、もし、万が一、本当に姉がそんな、低俗な行為に身を投じている確信を得てしまったら。想像しただけでも、目の前が真っ暗になってしまう。とても、確かめるなんて、できそうになかった。
また、目に涙が滲む。見かねた晴が、「私も付き合うからさ」と、頭を撫でるが、麗は「やだやだむりむり、歯医者さんにキュイーンてされる方がマシ!」と、晴の腕にしがみつく。
「そんなビビらなくても、大丈夫だって」
「大丈夫なわけないのだ! われは目撃の瞬間に、ショック死する自信があるのだぞ!」
「生きてるじゃん……。まぁ、ともかく、アンタはお姉さんが黒を白って言ったら、パンダもシロクマに見えるじゃん? なら、お姉さんが『恋愛サイコー』って言ったら、アンタも恋愛がくだらないなんて思わなくなるよ」
「うむむ……。姉ちゃんが絶対言わないことランキングのトップに来そうなセリフだが……。もしそうなったときは、晴を、われと姉ちゃんの目を覚まさせる兵団の団長に任命するのだ」
「謹んで、お断りさせていただきます」
晴は弧を描いた手を胸へ当て、麗をからかう。麗は頬を膨らませ、涙目のまま睨むが、面白そうにニタニタと笑われてしまった。
「じゃあ、決定! 放課後、お姉さんのデート覗き見大作戦!」
えいえいおーと拳を上げる晴につられ、麗も小さく手を上げた。
抵抗感が消えたわけではない。でも、こうなったら是が非でも、姉が今も変わらず、崇拝に値する存在である確信を得てみせる。目尻に残る涙を拭いつつ、麗はそう、決意した。
二
麗の姉、雅の通う高校は、麗たちの通う中学からさほど遠くなかった。
授業が終わるやいなや、麗は一度帰宅し、晴と共に早足に高校の前にやってきた。正門前に喫茶店を見つけ中に入る。門が見渡せる位置にある席を陣取り、コーヒーを二つ注文した。
「われ、オレンジジュースが良い……」
「ちょいちょい、今の私達は探偵でしょ? ブラックコーヒーで決めなきゃじゃん」
正面に座る晴が、肩をすくめる。
麗は晴の理論に納得がいかなかったが、黙って従った。一人で姉の尾行をするなど、麗にはとてもできそうになかった。
「けど、お姉さん、西高って意外だなぁ」
まだ人の出入りがない校門を見つめた晴が、頭の後ろで腕を組んだ。言葉の意味を汲めず、麗は首をかしげる。
「や、だっていつも、お姉さんのことベタ褒めしてるからさ、てっきり超頭良いのかと……」
西高は地区の中では、中の上程度の公立校だった。悪くはないけど、優秀というわけでもない。そんなイメージの高校だ。
やれやれ、所詮は晴も人間だな。麗は鼻を鳴らして、首を振った。
「いいかい、優れた者はどこにいても優れているのだよ。姉ちゃんに学校教育なんて必要ない。ランクで見栄を張る必要もない。だから拘束時間の短さと安さで学校を選んだのだ」
「安さ?」
「あー……。そ、その……、わ、われが、私立に行けるように…………」
「……私立行ける成績だったっけ?」
「じゅ、受験までにはなんとかするのだ……」
調子に乗っていたところに水を差され、麗はきゅっと小さくなる。身体ごと左側にある窓の方を向き、晴から視線を反らした。晴もそれ以上追求することはせず、黙って校門の監視を始めた。
注文したコーヒーが出された頃、帰宅部が一斉に下校を始め、二人が苦い苦いと言いながら、ようやく半分ほど啜ったところで、麗が「あ、出てきた!」と声を上げた。
「え! あれ? マジ?」
「うん」
「うっそ! 全然似てな……、ってか、クッッッソ美人じゃん!」
「うん」
麗はドッキリ大成功! といった顔で頷いた。
姉の雅は、道を歩けば誰もが振り向くほど、美しい容姿をしていた。パーツの一つ一つから、その配置に至るまで、全てが完璧。長く艷やかな黒髪は絹のようで、肌は降り積もったばかりの雪のよう。国宝級の人形師にでも作らせたかと思うほど見事な造形だ。
味気ない白タイのセーラー服も、雅が着るとドレスに早変わり。校門によりかかり、スマートフォンを眺める姿も、名画のように感じられる。
麗は晴の狼狽ぶりに、その感覚が自分だけのものではないことを確認し、雅への敬愛を深めた。
「……ん? あれ? お姉さん、なんかデカくない?」
「ふはは。恐れ入ったか、姉ちゃんは百八十近くあるのだ」
「わーお、アンタの倍じゃん……」
「そこまでチビじゃないのだ!」
「あ、相手の人ってアレ?」
晴の冗談に、麗が食ってかかろうとすると、晴は窓の向こうを指差した。
青みの強いブレザーを来た人物が、手を振り、小走りに雅に駆け寄っていた。
「うっわ、青城の制服じゃん! お相手さん、頭良いんだ?」
「全然そんなことないのだ」
青城は地区で一番の進学校。西高と違い、エリートのイメージがあった。
「てかあの人、お姉さんよりさらにデカくない?」
「夏那多さんはトドの大木というヤツなのだよ。姉ちゃんには全然釣り合わないのだ。まあ人間は全員釣り合わないけど……」
「ウドね。確かに見た目は、制服以外パッとしない感じよね。うーん、言っちゃ悪いけど、だいぶダサ寄りのダサの気配」
晴は「これは確かに釣り合わないわ」と額に手を当てた。麗は改めて夏那多を見る。
普通の顔、普通の体型、服装も普通。短目のくせ毛がわさわさしている以外は、これといった特徴は感じなかった。正直、なにがどうダサいのか解らない。だがクラスメイトの中でもおしゃれ度の高い晴が言うならそうなのだろう。麗は「やっぱりそうだよね」と大きく頷いた。
「てか、あの人達本当に付き合ってる? そこから疑わしくなってきたんだけど……」
「ほ、本当か!? それなら安心なのだ! ふはははは、人間どもめ首を洗って待つが良い……って、あああああ!!」
「え? なになに? どした?」
得意げに鼻を鳴らしたうららが、突き破る勢いで窓に飛びつく。晴が慌てて校門へ目をやると、ちょうど二人が歩き出したところだった。
「もう、これからデートなんてわかってたじゃん。ビックリさせないでよ……。って、なにそれ……」
財布を取り出した晴が顔を上げると、麗は大砲のようなレンズの付いたカメラを構え震えていた。
「あうぅ……。撮り損ねてしまった……」
「アンタ、まさか、それ取ってくるために一回帰ったの?」
「だ、だって、普段は見れない姉ちゃんの写真が撮れるかもしれないのだよ……? 実際、さっきはちょびっとだけど笑ってたのだ。笑ってる姉ちゃんは、パンダ並みに貴重なのだぞ!」
「お姉さん、アイドルかよ?」
「神だが?」
「真っ直ぐな目で言うなし……」
晴がげんなりした顔で、目元を覆うので、麗はむっと唇を尖らせた。
三
雅、夏那多の二人は、図書館で少し勉強をした後、スーパーへと入っていった。
といっても、勉強しているのは夏那多だけで、雅は夏那多を教えながら、本を読んだだけだった。
見るからに難解そうな分厚い本を、まるで漫画みたいにパラパラと読んでいく雅と対象的に、難しい顔で教科書とにらめっこする夏那多を見た麗は『やっぱりこの人と姉は釣り合わない』という思いを強くした。だが同時に、他者と交流を持ちたがらない雅が、放課後わざわざ時間を取って、勉強を教えている事実が、二人の親密さを示すようで、不安がこみ上げた。
陳列棚の影でカメラを構えたまま、晴に、「付き合ってる? 付き合ってない?」と、何度も尋ねては、「知るか、それしまえ」と窘められた。
「てかさ、友達と図書館で勉強なんて別に普通じゃん」
「バカ言うな。姉ちゃんは異常なのだ」
「アンタよりは普通に見えるけど?」
呆れた顔をする晴に、麗はため息を返す。
「図書館で姉ちゃんが手袋をしてたのを見ただろう。人間を下等生物と考えている証拠なのだ。お鍋も食べないから、我が家は、すき焼きも、しゃぶしゃぶも滅多に食べないのだぞ」
「それは気の毒だけど、ただの潔癖症でしょ」
「違う! これはワンコと同じ皿でご飯は食べないみたいな話なのだよ! どんなに愛らしくても、ワンコは人間と対等じゃないし、友達にもなれないのだ。姉ちゃんと夏那多さんもそう!」
「犬は人間の最良の友って言うけどね」
「人間はワンコを便利に使ってるだけなのだ。爆弾を背負わわれて、敵陣に突撃されられる可愛そうなワンコもいるのだぞ! は! そうか、姉ちゃんも夏那多さんを爆弾に……?」
「お姉さん、なにと戦ってんだよ……。てか、バター犬とかのが可能性高くない?」
「バター……?」
「おっと……。な、なんでもない、忘れて! あ、ヤバイ。気付かれたっぽいよ」
晴の言葉にパッと振り返ると、麗に気付いた夏那多が、手を振り小走りに近付いて来ていた。
「麗ちゃん、ちょうど良かった。ブロッコリー食べられる? そっちはお友達?」
夏那多がカゴから取り出した、大きなブロッコリーを振りながら尋ねた。顔を見合わせたうららとはるは、とりあえず頷く。
「だから、ほうれん草が入るなら、ブロッコリーはいらないって言ってるじゃない」
「でもブロッコリーは栄養価高いし、今日特売ですごく安いよ?」
後からやって来たみやびが、じっとりした目で不平を言う。
麗は尾行がバレ、姉に叱られるのではないかとヒヤヒヤしていたが、大丈夫そうで安堵した。一方、晴は、今の状況を今ひとつ飲み込めていなかった。
「ねぇ、麗の家って、おやつが野菜だったりする? それかお姉さんとお相手さんはベジタリアンとか?」
「今日は両親が家にいないから、夏那多さんがご飯作ってくれるのだ。ちなみにグラタン。われの好物。先週リクエストしたのだ」
「アンタ、あの人のこと、ボロクソ言ってなかった?」
「なにも矛盾はないぞ。召使いが主人のご飯を作るのは普通のことなのだ。でも姉ちゃんはブロッコリー嫌いだから、きっと入らないのだ」
「はぁ……。私、まだアンタの思考回路を、理解しきれてないみたいね」
「われは思慮深いから無理もないのだ」
「言ってろ」
ひそひそ話を終える頃、ブロッコリーについての議論にも決着がついていた。うららの予想した通り、グラタンにブロッコリーは入れないことになったらしい。しかし金沢自宅用に買うことにしたらしく、入り口え走り、カートとかごをもう一つ持ってきて、空のカゴの方へブロッコリーを二つ入れた。
売り場を移動しながら、夏那多は春に、一緒に夕食をとるかを尋ね、 うららがぜひ一緒にと答えた。春はそれを咎めたが、うららが「昨日あんなことがあったのに、三人だけになるなんて無理なのだ! 一緒にいてくれないと困る! いっそ泊まっていってほしいのだ!」と、懇願するので、自宅に電話し外泊の許可を取った。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!