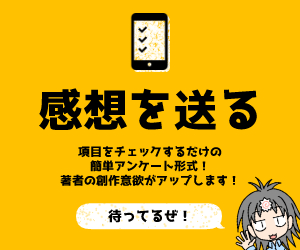ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第二十一話の続きになります。
第二十一話までのあらすじは以下のような感じです。
訓練を終えたフューリは極拳の塔の攻略に挑むが、ヒーゼリオフの怒りを買っていたために、落とし穴に落とされいつもとは違う特別コースを回ることになってしまう。嫌がらせとしか思えないコースをどうにか攻略して頂上に着くと、今度はヒーゼリオフと一対一の戦闘をすることになる。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下二十二話です。
【フューリ 十七】
闘技場を見ると、ヒーゼリオフがガーティレイに背を向け、余裕のある態度でゆっくりと闘技場の真ん中に歩いて行く様子が見える。ガーティレイは構えたまま動かなかった。背中を向けていてもヒーゼリオフにまるでスキがないことがわかっているようだ。
「ガーさんて、やっぱ斧使わないほうが強いんすかね?」
「ふん。素手のほうがマシというだけだろう。あのオーガは武器の扱いがまるでなっていないからな」
「そ、そうなんでしゅか?」
「ええ。頼りすぎるというか、意識しすぎるというか。なんでも武器でやろうとしすぎて、上手く使えていない上に、身体もついていっていない印象ですわ」
「そうね。ほとんど素人の動きと言っても差し支えないかも」
「うはは。そう貶してやるな、二人共」
闘技場のガーティレイを見下ろしていると、後ろからオルナダ様の声がした。僕が振り返ろうとすると、すとんと膝の上に落ちてきて「そうなる理由は察しているんだろう?」と語りかける。オルナダ様は昼間の制服ではなく、風呂屋のローブを着ていて、お湯とお酒と色んな人の匂いがした。やっぱり四時間は待たせすぎだったんだなと僕は改めて反省した。
「お、お言葉ですが陛下……。あのオーガは単に不真面目なだけではないでしょうか?」
オルナダ様のお腹に手を回してローブの前が開けっ放しでないかを確認していると、ヴィオレッタが狼狽えた様子で立ち上がる。
「まぁ不真面目に見えるのは確かだが、その辺は〝武器なんてのはオーガが学ぶものではない〟って考えからくる行動なんだ。宗教みたいなものだな。普段、斧を持って歩くのはただのファッションだろう」
「〝ステゴロ最強こそオーガの本懐〟というヤツですわね。今となってはもうオーガ圏の田舎でもカビの生えた考えとされておりますが」
オルナダ様とキャサリーヌは愉快そうに含み笑いをした。
僕はなんだかモヤっとして、
「オルナダ様って、意外とガーさんのコト、気に入ってます、か……?」
と尋ねてみた。するとオルナダ様はキョトンとした顔をして、
「ん? おお、まぁそうだな。今時あんな肩肘張りまくったオーガは珍しい」
「まったく。二、三世代は昔の年寄りのようですわ。まだ尻の青い童だというのに。いえ、童だからかもしれませんわね」
とキャサリーヌと笑い合う。
そんな様子を見たヴィオレッタは「奴の評価がそれほど高いとは」と目を見開き、あんぐりと口を開ける。僕も似たような顔をしていただろう。オルナダ様とキャサリーヌが揃って「評価しているというのとは違う」と手を振るまで、僕もその肩肘というのを張ったほうが良いのだろうかと真剣に考えてしまった。
「とうに廃れた思想を、あんな若いのが信仰してるのが面白いというだけですわ」
「旧懐の情が湧くというのもあるな。昔はあんなオーガがたくさんいて」
「「それはそれは迷惑を被ったものだ」ですわ」
二人は声を揃えて言って、ケタケタと笑う。ティクトレアはそんな二人に「わたくしはあの時代のオーガはちょっと苦手ね」と苦笑いする。僕も迷惑が面白いなんて変だなと、眉を寄せつつ首をひねった。
「なんだ、フューリ。妬いてるのか?」
「はい。……い、いえ! ぼ、僕も面白くなったほうが良いのかと思っただけです!」
「よせよせ。お前はオリコウなところがカワイイんだからな」
「そ、そうですか? え、えへへへへへ……」
「こら、そこ!! これから対戦ってときにイチャつくんじゃないわよ!!」
僕を見上げるオルナダ様に、首の後ろをもしょもしょしてもらっていたら、ヒーゼリオフがいきなりこちらを指差して怒鳴り声を上げた。ぴょっと小さく飛び上がった僕は、失礼だったかなと軽く頭を下げ、姿勢を正して座り直した。同時に闘技場でヒーゼリオフに向き合っていたガーティレイがこちらを向いて「そうだぞ、オルナダ!」と拳を振り上げる。
「イチャつくなら私とだろう! そんなへにゃ耳じゃなく!」
「はぁ!? アンタとフューなら、断然フュー……、じゃなくって! と、とにかく気が散るから離れなさいよ!!」
「そうだ! これから極拳をぶちのめす私に失礼だろうが!」
「なっ……、できると思ってるの!? どんだけバカなのよ、アンタ!!」
「は! なんだ、負けるのが怖いのか?」
「どこをどう聞いたらそういう解釈になるのよ、この赤ヘチマ!!」
「なんだと、この団子頭チビ!!」
ガーティレイとヒーゼリオフは殴り合いの前に口喧嘩をすることにしたのか、お互いの容姿を揶揄した言葉を並べ立てだした。
隣にいたティクトレアは呆れたように息を吐いたけど「確かに二人の言う通りね」と嗜めるようにオルナダ様を見る。おかげでオルナダ様は「わかったから早く始めろ」と僕の膝を下りて、隣の席に移動してしまった。
もっとくっついていたかったのに。僕の耳としっぽはしゅんと萎れた。
「いいわ。一撃で気絶させてあげるつもりだったけど、たっぷり十分間、遊んであげようじゃない」
「ふん。一分とかからず眠らせてくれるわ!」
二人は僕の視線に気付くこともなく、闘技場の中央で向き合う。ガーティレイの構えは先程と同じ。ヒーゼリオフはガーティレイに対して身体をほとんど真横に構え、深く腰を落としていた。左足を前に伸ばし、開いた右手を頭の後ろ、左手を顎の高さで前方に掲げている。とても独特な構えだ。
「いつでもかかってきなさい! 特別に初撃は受けてあげるわよ!」
「笑わせるな、こっちのセリフだ! とっととかかってくるが良い!」
「そういうのは良いから、さっさとお行きなさい小童! ワシには口喧嘩を見ている暇はなくってよ!」
「そうだぞ! とりあえず、パンチだ、パンチ!」
二人は再び言い合いを始めたけど、キャサリーヌとオルナダ様にやじを飛ばされ、チッと舌打ちをしてにらみ合った。そして一瞬の沈黙ののち、ガーティレイがまっすぐヒーゼリオフに向かって突進した。ボッと音を立てて、ヒーゼリオフ目掛けて右手を振り下ろす。
ヒーゼリオフはすっと静かに後ろへ下がり、それを躱すと、ヒュンと後ろへ宙返るついでに、足を振り上げ顎を蹴り飛ばそうとする。ガーティレイは顔を反らしてそれを躱した。
ガーティレイは大きいし頑丈だから、攻撃が当たっても大したことはないだろうけど、ヒーゼリオフはそうはいかないだろう。オルナダ様より多少大きいとはいえ、それでもガーティレイの腰の辺りまでしか身長がないし、手足の太さも倍くらい違う。その体格差、リーチの差に、僕はハラハラしてしまう。
「ガーさんの動き、意外とコンパクトっすね」
「いつもと違って動きがスムーズでしゅ」
「ふん。確かにいつもよりはマシだが、まるでデタラメだ。構えはラフージャ流のものだったが、あの振り下ろしはギガラン流、今繰り出している蹴りはマザッツとエントナの間のような半端モノ。まぁお似合いだが」
「ほほほ。勉強家ですわね、ヴィオレッタ。つまりはあれが、グリスガラリスなのですわ」
ぐびりと酒を煽ったキャサリーヌが、ガーティレイを顎で指す。聞き覚えのない名称に、僕だけでなく、シシィやほかのみんなも首を傾げた。
「みんなは若いから知らないかもしれないけど、何世代か前までのオーガは、各地の道場を破って回って、その中で見た技を故郷に持ち帰って披露するっていう風習があったの」
「披露と言っても、丁寧に解説しながらやってみせたわけではなく、実戦の中で勝つために使っていたのですわよ」
「そうやって世界中の武術が集まって、使えるものは流行り、使えないものが廃れを繰り返し、やがてオーガ圏全土に普及する格闘術、いや、喧嘩術へと進化していったわけなんだが、その風習が最も盛んだった地の名を取ってグリスガラリスと呼ばれるようになったのさ」
オルナダ様たちの解説に、シシィとルゥは感心したように息を漏らし、ヴィオレッタは口をへの字にした。闘技場ではガーティレイが猛烈な連撃ののちに、蹴り上げを繰り出し、ヒーゼリオフの身体が軽々と宙に浮いたところだった。
「しゅ、しゅごいでしゅ! ガーしゃんが押してましゅよ!」
「うおお、ひょっとすると、ひょっとするかもな!」
ルゥとシシィはガーティレイの戦いぶりに興奮した様子で「行け、そこだ」と拳を振り回す。
「教官、教官! 今のヒー様って、もう一割出してますかね!?」
「ふーむ、四分といったところでしょうね。冒険者ランクで言うなら、今は二人共Cプラス程度ですわ」
「ひゃー、Cプラスで四分か~。私は何分だったらまともに勝負できんだろ?」
「ルゥは二分くらいで相手をしてもらいたいでしゅ」
「ちゃんと目を開けて試合をご覧なさい。パーティ戦のときのヒーゼリオフは八分程度の出力なんですのよ? お主らも四分程度は凌げなくては困りますわ」
キャサリーヌが弱気な発言をする二人をジロリと睨み、二人は照れたように頭を掻いた。確かに今のヒーゼリオフはそんなに速くもないし、二人が善戦する様子は想像に難くない。
「おい、フューリ。他人事みたいな顔してないで、しっかり見ておくんだぞ? お前にはヒーゼのヤツに勝ってもらわないとだからな」
「え?」
「え? じゃない。俺はお前が勝つほうに、お気にの剣を賭けてるんだ。勝ってもらわないと困る」
「な、なぜそんなことを!?」
オルナダ様の突然の要求に僕は思わず、ギュッと首を縮めた。
「うーん、なぜだったか……。気付いたらそういうことになってたんだよなぁ……」
「あら、忘れちゃったの? オルがフューくんなら一割のヒーゼなんか瞬殺だって煽って、そこから売り言葉に買い言葉で賭けをすることになったんでしょ?」
「おお、そうだったな。あいつが笑う壺を出すというから、俺も剣を出すことにしたんだったな」
「あんな変なモノほしがるなんて、オルは変わってるわよね。価値的にも釣り合ってないでしょうに」
「そんなことはない。俺たち魔族から見ても変なモノってことは、それだけ珍しいということだぞ? 回収して研究させれば、なにか出てくる可能性もある。十分、釣り合うとも」
ティクトレアが口を挟んでくれたおかげで事の経緯はわかったが、僕が勝たないとオルナダ様はお気に入りの剣を取られてしまうという点は変わらない。ダメ元で「なかったことにできませんか?」と聞いてみたけど、ティクトレアは「ヒーゼがカンカンだったから無理でしょうね」と肩を竦め、オルナダ様は「心配するな、勝てる勝てる。俺に壺をプレゼントしてくれ」とカラカラ笑うだけで、撤回のての字も考えてくれそうにない。
僕は突如発生した強烈なプレッシャーに喉を締め付けられつつ、なにか突破口はないかと姿勢を正して正面を向く。闘技場の二人の攻防は激しさを増して、攻撃を繰り出すスピードも、一撃の威力も倍くらいになっていた。
軽やかなステップで動き回るヒーゼリオフとは対象的に、ガーティレイは中央にどっしりと構えたまま動かない。スタミナを温存しつつ、カウンターを取ろうという狙いなんだろう。いつもの闇雲に斧を振り回して突進していくガーティレイとは別人のような冷静さだ。
タンッと床を蹴ってヒーゼリオフが超低空姿勢で飛び出す。ガーティレイがその顔面を蹴り上げようとわずかに重心を移動すると、ヒーゼリオフは床に手をつき、飛び出した勢いを乗せ前転して踵を振り下ろす。ガーティレイはそれを片手で受け止めガッチリと掴む。そのまま床に叩きつけようと腕を振るけど、ヒーゼリオフはするりと抜け出し、ガーティレイの後頭部を蹴って背後へ周ると、すかさず床を転がるように回し蹴りを繰り出す。
これらすべての動きが淀みなく流れるように行われるので、ヒーゼリオフは戦っているというよりはむしろ踊っているように見える。パーティ戦のときとは違う、トリッキーな動きだった。
そもそもヒーゼリオフとの対決は、一撃でも入れられたらこちらの勝ちというルールで行われている。つまりガードを搔い潜るか、不意をつくか、あるいはガードの上からでも有効な打撃を打ち込むかして、頭かボディにダメージを与えれば勝ちということだ。だからパーティで戦ったときは、全員でとにかく手数を出して誰かが一撃入れれば良しという戦法を取っていたのだけど、そのときのヒーゼリオフはほとんど動かず攻撃を躱し続けていた。だから僕らはこんなに動き回るヒーゼリオフを見るのは初めてだった。
「ヒ、ヒーしゃま、速しゅぎでしゅ……」
「あんな速度であんな変な動きされたら、どうやって攻撃当てりゃ良いんだよ……」
「正攻法で行くなら読み合いを制するほかないだろうが、これではとても……。もはや全方位攻撃に頼るしか……」
「それは悪手ですわね。捌かれるか、間合いの外に抜けられて、無駄に消耗して終いですわよ」
「ぐ……。確かに陛下は我々全員での攻撃も難なく躱されていた……。生半な全方位など通用するはずもないということですね……」
「さようですわ」
「き、厳しいっすね……」
「でしゅ……」
みんな頭を抱えていた。この戦闘を見てなお、どう勝つかを考えているんだろう。感心すると共に、どうしてみんな戦うのが好きなんだろうかと残念な気持ちになる。倒したって食べられるわけでもないのに。
ふぅと息を吐いて再び闘技場を見ると、ヒーゼリオフがピタリと足を止め構えを変えていた。手の位置はこれまでと一緒だけど、真っ直ぐ片足立ちで立っている。パーティ戦のときによく見る構えだった。ヴィオレッタによると、この立ち方をされると次の足の運びが読み難くなり、動きの予測が立てづらいらしい。ガーティレイも同じ考えなのか、煩わしいと言わんばかりに顔を顰めた。
「さぁ、サービスはここまでよ」
「ほざけ!」
ガーティレイが身体を大きく前傾させヒーゼリオフに突進する。振り上げた右手を真っ直ぐに突き出す。と思わせて、躱しに入ったヒーゼリオフの退路を塞ぐように左手を広げ、加速して距離を詰める。さらに右手でも退路を塞ぎ、顔面に膝が当たる軌道で前方へ跳んだ。
後方へ躱す、上へ跳ぶ、下を潜る。対応策はいくつか考えられるけど、ヒーゼリオフはすっと散歩にでも行くように歩きだす。ガーティレイがヒーゼリオフをすり抜け、ズダンッと背中から床に叩きつけられた。退路を断つために伸ばしていた腕と、顔面を狙っていた膝に軽く手を置いて、勢いを殺さずに力の流れだけを変えたのだ。
ガーティレイは目を白黒とさせ、ヒーゼリオフは上に向けた手のひらをクイクイと手前に引いて余裕の笑みを浮かべる。それだけでガーティレイは元々赤い顔をさらに赤くして飛び起き、再びヒーゼリオフに突っ込んで、同じ様に投げられた。怒りと興奮に飲まれたガーティレイの身体からは湯気が立ち、もはや最初の頃の冷静さは見られなくなっていた。
「ガーさん! ヒー様が強くなってるってことは、割合上げてるってことっすよ! 舐められてるわけじゃないんで、一旦、落ち着いて!」
「そ、そうでしゅ! 初めて見る技を使ってましゅし、追い込んでましゅよ!」
「まさか、あれがまだ見ぬ一割開放……? あのオーガにそんな価値があるというのか……!?」
「まったく、お主らは……。目を開けてご覧なさいと言いましたわよね? さっきのヒーゼリオフはむしろ二分以下に落としてましたわよ」
「「「え――――――――――――――――――――っ!?」」」
ガーティレイに声援を送っていたシシィたちがキャサリーヌの解説に驚愕の声を上げる。
たぶんさっきの投げ技は、ガーティレイの力の流れを利用しただけなので、強化魔法の類は最小限で良かったということなんだろう。だけど筋力の強化を低下させれば、移動速度も下がってしまうので、とっさのときに回避が間に合わないかもしれないし、身体強化も下げているなら万一攻撃が当たれば大怪我をしてしまう。なんて危ないことをするんだと僕は思わず眉を寄せた。
「と、とにかく冷静に頑張ってくだしゃーい!」
「そうっすよ! 割合とか気にしないで行きましょ! ところで教官、あれってイラヴァールでも習えますかね?」
「八流拳自体は学べますが、あの域に達するには相当な修行が必要ですわよ? まぁ、ヒューマー向きと言っても過言ではない体術ですし、槍術、棒術との相性も良い技ですから、お主が学ぶ価値は十分にありますわね、シシィマール。よろしい、食後にでも軽く基礎を叩き込んで差し上げましょう」
「やった! あざっす! あ、今のもすげぇ! ガーさん、パンチはもっと刻んでいきましょ!」
「わわ、またぐるんって飛ばされちゃいましたでしゅ! 受け身取ってくだしゃーい! そ、それから、ルゥも八流拳やってみたいでしゅ、教官!」
「わ、我もご一緒させていただけますか!?」
「ほほほ。構いませんわ」
ガーティレイがひょいひょいと投げられる間、観客席は応援しつつも別の方向で盛り上がりをみせる。なんだかちょっぴりガーティレイが気の毒だった。
「じゃ、そろそろ飽きてきたし、次でお終いにしてあげるわ」
「ぐぬぬ……、ふざけたことを……!」
片膝をついているガーティレイを見据え、ヒーゼリオフは肩にかかる髪を払った。くるりと背を向け、数歩歩いて距離を取り、スタンダードなファイティングポーズを取る。全身が淡い黃色の光に包まれる。
「一応、武人の礼儀として、個人戦のときはどんな相手でも一割は見せることにしてるの。アンタはパワータイプだから、きっちりパワーで負かしてあげるわ」
「んがあああああ!! 舐めるなああああああああああ!!」
本日最大の煽り発言を受け、ガーティレイは闘技場が揺れるほどの叫びを上げた。憤怒の表情を浮かべ飛びかかっていく姿はもはや魔物と同じだった。これならその場に蹲って転ばせるだけで、シシィでも倒せるだろう。だけどヒーゼリオフはわざわざ自分から、ガーティレイの前に飛び出し、振り下ろされる拳に魔力板で強度を増した頭突きを食らわせつつ、黃色の閃光で下からガーティレイの顎を貫いた。
ガーティレイはガクンと尻もちをつき、ドサリと仰向けに倒れた。ヒーゼリオフが顎を撃ち抜くために突き上げた拳がそのまま勝利宣言になった。
「さぁ! 次はアンタよ、フュー! 下りてきなさい!」
ヒーゼリオフが上げていた拳を僕に向け指を指す。たった今ガーティレイのパンチに飛び込む様子を見た、僕は冷や汗まみれで目を逸らした。こんな危なっかしい人と戦ったりしたら、どんな大怪我をさせてしまうかわからない。下手をすれば殺してしまうこともありうる。できれば辞退したいけど、オルナダ様に賭けをしてるから勝てと言われているし、みんなも救護班に運ばれていくガーティレイを指差して仇を討てと盛り上がる。とてもやりたくないとは言えないし、イラヴァールでの実戦訓練みたいに絶対に怪我をさせないだろう力加減で戦うわけにもいかない雰囲気だった。
「っしゃあ、フューリ! オル様の前だし、イイトコ見せろよ! 気合いだ、気合い!」
シシィが鼻息荒く、僕の背中を思い切り叩く。それに釣られたのか、ほかのみんなも「殿下の勝利を祈っております!」、「頑張ってくだしゃい!」、「フューくんなら勝てるわ!」、「魔物を狩るのと同じ様におやりなさい!」とバシバシと背中を叩いて、僕を闘技場へと送り出す。
この行為にどういう意味があるのか、僕にはわからない。雰囲気から察するに、たぶん仲間を鼓舞するための儀式のようなものなんだろう。そう思うと、なんだかみんなと仲良くなれたようで嬉しくなった。それに、背中に触れたルゥの手が、ふかっとしていたのが可愛くて、悶絶しそうだった。
でもだからといって、気乗りがしないことには変わりない。「頑張ってけど負けちゃいました」くらいの感じで許してもらえないかとオルナダ様を見つめて見るけど、
「俺の壺、よろしくな!」
と手を振る様子を見ると、もう勝った気でいるみたいだ。
僕は仕方なくとことこと闘技場へ下りて、ヒーゼリオフの前に立つ。一体どうすれば良いのか、頭がぐるぐるとしていた。幸いヒーゼリオフが「いつでもかかってきなさい」と言ってくれたので、対策をじっくり考えさせてもらうことにした。
この試合の勝利条件は、頭かボディにダメージを与えるというものだ。だけどどの程度のダメージかは指定されていない。ということは、ただ手を触れるだけでも勝ちになるはずだ。それなら子供の追いかけっ子遊びと同じということになる。となると武器も盾も邪魔になるから置いておこう。そういえば、寝技の類は技を決められた段階で勝ちになると最初にみんなで戦ったときに説明されたっけ。結局ヒーゼリオフが速すぎて、とてもそんな技をかけかれないということで誰も試さなかったけど、それを試すのも有りかもしれない。技の種類なんか全然知らないけど、転ばせて押さえつけるとか、首を絞めたりとかなら僕でもできそうだ。いや、でも力加減を間違えてボキッってなったら怖いし、あまり接近するとさっきのガーティレイもみたいに倒されてしまう。それにあんなスピードで動くヒーゼリオフに組み付くなんて、打撃を加えるよりさらに困難だろう。ここは初めに考えた通り、手を触れるのを目標にしたほうが良いかもしれない。それならリーチの差も生かせるだろう。その線でいくなら、躱されたり防がれたりしないだけのスピードが必要だ。でもスピードをつけるということは、攻撃力が増すということでもあるから、それはそれで怪我をさせる心配があるから、これもやっぱり、あまりやりたくはない。かといってノロノロ動いたんじゃ、あっという間にやられてしまうだろうし、寸止めにしようとしたりすれば、触れることすらできない可能性もある。というかそもそも、オルナダ様の憑依を受けた影響で、全身に軋むような痛みがある今の状態じゃ、捕まえられる速さで動けるのかも、ちょうどいい寸止めができるかも怪しい。
「…………フ、フューしゃん、どうしたんでしょ? 立ったまま全然動かないでしゅ……」
「まさかあれは、クルーダ流格闘術を修めた者が好むという『無我の構え』……!? ヒューマー圏ご出身の殿下がなぜ……!?」
「それは違うな、ヴィオレッタ。あいつはその手の訓練を取ってないし、武術についてはてんで素人だぞ。あれはヒーゼのヤツを焦らして冷静さを奪う作戦だろう。ちょっと前に宿敵との一騎打ちに大幅に遅刻して楽々勝利を収めた剣豪がいたが、まさかそれと同じ手を使うとは。なかなかやるじゃないかフューリ」
「オルナダ、何度も言いますが、あれは天候のせいであってわざとではありませんのよ?」
「いや、あの、あいつ対人戦クソ苦手なんで、普通にどうしたもんかって悩んでるだけだと思いますよ?」
僕がなかなか動かないせいか、観客席では「頑張れ!」とか「負けるな!」とかの声援が止み、代わりに僕の戦いに対する予想が始まった。
「なにを言う、シシィ。殿下ならば、それこそヒーゼリオフ陛下クラスの相手でない限り、負けなしに決まっているだろう」
「だったら実践訓練とかで毎回優勝してるはずじゃないっすか。でも実際はいつも中の下くらいの成績で、まるで注目されてないっすよね?」
「なに!? あいつ、そんなに成績悪かったのか!?」
急にオルナダ様が声を上げたので、ギクリと身体が固まった。やっぱり成績が良くないのは飼い犬としてマズイだろうか? 背中に冷や汗をかきつつ、僕は頭の上の耳をぐりんと後ろの観客席へ向けた。
「じ、じゃあ、フューしゃんは訓練を受けてる相手と戦うのは苦手なんでしゅか?」
「そんなはずはないだろう。フューリは感覚が鋭いし、スピードもあるから、どんな技を仕掛けて来ようが動きが読めるし、見てからの対処も十分できるはずだぞ!」
「そ、そういえば、我とあのオーガの間に入られたときも、まるですべてを読んでいるかのような動きをされていた……。で、ではなぜ、中の下などに……」
「本人曰く「怪我をさせないようにって思うと手も足も出せなくなっちゃうんだよね」だそうです」
「おいおい、訓練でもか? ヤッてるときやたら怪我を心配するから、まさかと思ったが……」
「あ、オル様! 私、ダチのそういう話NGなんでシーッで頼んます!」
「ん? おお、そうか、ヒューマーもその辺ナイーブだったな……。まぁ、だとしても、あいつの実力なら、もうちょっとなんとかなるだろ!」
「私もいっつもそう言ってるんすけどね~。やっぱオル様がビシッと言わないとダメなんじゃないっすか?」
「うぅむ。しかしそういうのは飼い主としてダサいというか……、だがしかし中の下はなぁ……」
もう僕の耳は完全に後ろを向いたまま動かない。なんなら今すぐ観客席に戻ってオルナダ様に「頑張るのでクビにしないでください」と泣きつきたい。あとベッドでどうかみたいな話は表でしないでほしい。というか「そういう話を他人にするとBPがつくから気をつけろよ」って前にオルナダ様に言われた気がするんですけど、なにさらっと言ってくれちゃってるんですか? 冷や汗をかくのと同時に、カッカと全身が熱くなってしまった。
「よし。そしたらあれだな。実践訓練の内容を、あいつが無双できるものに変更しよう」
「いいわね。フューくんの無双ならわたくしも見たいわ」
「素晴らしいお考えです、陛下!」
「え? それマジで言ってんすか? 頭ダイジョブ皆の衆?」
「ど、どんな風に変わるんでしゅかね……?」
「オルナダ、ワシはこれ以上、軟弱者が増えるような訓練には賛成しかねますわよ?」
「あ、この辺、教官はまともなんすね。良かったぁ……」
「………………うるっっっっっっっっっっさいわよ、アンタたちっっっっっっっっっっ――――――――――!!」
やいのやいのと騒ぐ観客席へ向かって、ヒーゼリオフが怒号を飛ばした。怒りに任せて踏みつけた床がバゴンとひび割れて、塔全体がグラグラと揺れる。僕はオロオロとしつつ、まるでガーティレイのように真っ赤になって方を震わせるヒーゼリオフに、落ち着いてもらおうと声をかけたけど、
「アンタはせめて構えるぐらいしなさいよ!!」
と怒鳴りつけられてしまった。
あまりの気迫に僕は思わず、ヒーゼリオフの構えを真似てしまう。するとヒーゼリオフはますます怒り心頭といった様子で眉を吊り上げた。さらに悪いことに観客席から、
「お。ここで煽りをかますとは、やるじゃないか。さすが俺の犬」
「なるほど。冷静さを失わせることで、対人戦に弱いという弱点を、わずかにでもカバーしようというのですわね」
「あら。フューくんったら、そういうのもいけるのね」
「まさか、殿下は見ただけで八流拳を習得したと……!?」
「ヴィさん、それだけは絶対に違いますよ」
「で、でも完全にコピーしてるように見えましゅ……」
なんて声が上がる。
違うんです、違うんです!! ただ武術とか齧ったくらいにしか知らなくて、構えって言われてもどんなポーズが良いのかわからなくて、咄嗟に真似しちゃっただけなんです!!
そう叫びたいけど、あまりの気まずさに喉が締め付けられて声が出ない。さっき上がった体温が一気に下がっていく。その間も目の前に立つヒーゼリオフの背中では、山火事かなにかかなと思うほどの怒りの炎が燃え上がっていて、すぐにも頭を下げて謝りたくなってしまう。でなければこっそりこの場を立ち去りたい。
だけどこの状況ではどちらもできるはずもなく、僕はとにかく落ち着いて戦法を考えようと、懸命に深呼吸をした。観客席は「呼吸法がどうのこうの」と盛り上がったけど、聞いてしまうとまた嫌な汗をかくハメになるので、言葉として理解しないよう努めた。
これまでやってきたパーティ戦や、さっきのガーティレイの個人戦の様子を思い返し、自分ができることを考える。万に一つも怪我を負わせることのない方法を。
考えに考えて僕は、勝機があるとしたら、初撃にしかないだろうという結論に至った。
構えの体勢のまま、魔力を巡らせ、青い光で全身を覆う。
『技能「魔装」LV32』
「ほう。いきなり魔装を出すとは……。一撃で決める気のようですわね」
「うええ!? 教官、それマジっすか? いくらなんでもヒー様相手にそれは強気過ぎだろ、フューリ……!」
キャサリーヌの推測に、シシィが声を裏返らせた。観客席から見ても、僕が初撃に賭けたことがわかるらしい。なら当然、目の前の相手も同じ解釈をしただろう。
まっすぐに正面を見つめると、ヒーゼリオフはニヤリと口の端を持ち上げる。
「ふん。割りと良い判断じゃない。だったらこっちも、初めから一割でいかせてもらうわ!」
宣言と同時にヒーゼリオフの身体が黃色の光を放つ。
「わわっ! ヒーしゃまがガーしゃんを倒したときと同じくらい光ってましゅ!」
「てことは自分で言ってる通り一割出すってことか!? 一割って冒険者ランクでどんくらいだっけ!?」
「我の記憶では、Aプラス相当であったはずだが、陛下の気迫のせいか、それ以上に感じられる!」
「ふふ。ヒーゼったら、フューくんが魔装を使ってきたから、嬉しくなっちゃったのね。確かにちょっと一割超えてるかも」
「そのようですわね。ほんの少しですけれど」
「おい、ヒーゼ! 一割超えは反則だろ! セーブしろ、セーブ!」
「ああ、もう!! だから五月蝿いのよ、アンタたち!!」
ヒーゼリオフの視線が一瞬、僕から観客席へと移った。
今! と僕は一直線にヒーゼリオフに向かって駆ける。身体中の魔力を魔装に回す。維持できる以上の魔力を注いだ魔装から、ジャアアアという音と共に青く眩く光る魔力が蒸気のように飛散した。それでも構わずに僕はオルナダ様に教わったように魔装を操作して、肉体の限界以上、強化の限界以上までスピードを上げ、低い姿勢で獣のように突進する。
『技能「魔装」LV54』
「こ、こら、フューリ! 魔装にそんなに注ぎ込むな!」
「あれでは数秒で魔力切れですわ!」
オルナダ様とキャサリーヌが慌てたような声を上げ、ヒーゼリオフは、
「魔装頼みの突進なんて、甘いわね!」
と、両腕を覆うように小さな黄色い魔力板をいくつも並べて重ね、ゴーレムの拳のような形状にした。魔装ごと僕を殴りつけて吹き飛ばすつもりなんだろう。僕が獲物に飛び掛かる獣のように両腕を振り上げると、巨大な拳をグローブのように身に着けたヒーゼリオフが、顔面を打ち抜く動作に入った。
『技能「魔装」LV67』
僕は魔装に流す魔力をさらに増やす。輝きを増す魔装の前面に、ヒーゼリオフのグローブが触れる。
『技能「空歩」LV41』
瞬間、指先と足先に魔力板を作り出し、ぐるんと回転しながら魔装から抜け出した。
着地と同時に後ろでバリンッと衝突音がした。ギシギシと軋む身体を必死に捻って、ヒーゼリオフの背中に腕を伸ばす。
捕まえた!
そう思った瞬間に、目が眩むような黄色い光がこめかみに突き刺さった。
僕の身体は信じられないほど軽々と吹き飛ばされ、ゴロンゴロンと転がって観客席前の壁に叩きつけられた。目を闘技場へ向けると、ヒーゼリオフが片足を上げた姿勢で立っている。どうやら蹴飛ばされたらしい。
立ち上がると、頭がぐわんぐわんと揺れた。相手の動きが見えないのも、素手でこんなダメージを入れられるのも子供の頃以来だ。ヒーゼリオフに伸ばした腕の側から蹴りが飛んできて、咄嗟に反対の手で防いだ気がするけど、それでもこんなに吹っ飛ばされるだなんて、もしガードが間に合わなかったら、今頃完全に伸びていただろう。
「や、やるじゃない……」
ヒーゼリオフは笑って再び構えるけれど、初撃にすべてを賭けた僕には次の手がなかった。作戦を立てようにも、もう魔力がスッカラカンでできることが限られているし、さっきのダメージと魔香で頭がぼーっとして、ろくに考えることができない。もはや勝利は絶望的だ。それなのになぜかとても良い気分で、そんな状況がなんだか面白い。
もうこうなったら死んだふりだ。僕はころんとその場に倒れた。こうやってヒーゼリオフが「なんなのよ」って近付いて来たら、そのときにタッチしよう、そうしよう。なんて名案なんだ。僕は楽しくなって、ついつい鼻歌を歌ってしまう。
「ちょ、ちょっと、なんなのいきなり? やる気ないわけ?」
「魔力使い切ったから俺らの匂いで酔っ払ったんだろ」
「あ、おるにゃだしゃま! ぽく、かんばっへまふよぉ~!」
ヒーゼリオフより先にオルナダ様が転がる僕を覗き込んだので、僕は寝転んだままビシッと敬礼をしてみせた。
「な、なに乱入してんのよ! まだ試合中でしょ!」
「いいや。さっきので決まりだろ。お前の反則負けだ」
「そうよ! 一体何割出したの? 蘇生魔法を使うことになるかと思ったわよ?」
「べ、別にわざとじゃないわよ? う、後ろを取られたから、ついうっかり出力上げちゃっただけで……。す、すぐ一割に戻したし……っ!」
オルナダ様と続いてやってきたティクトレアとヒーゼリオフが僕の頭の前に集まる。どうやらヒーゼリオフは僕にタッチされそうになった瞬間、一瞬だけ一割までルールを破ったらしく、二人に反則を指摘されているようだ。そのためにわざわざ下りて来てくれるなんて、オルナダ様はなんて素敵な飼い主さんなんだろう。それにとってもいい匂いがする。
「ま、まぁ、やっちゃったものは、しょうがないわ」
「しょうがないわ。じゃないでしょ、ヒーゼ。フューくんがこんなに頑丈じゃなかったら、頭がなくなってたかもしれないのよ。あぁ~、かわいそうなフューくん。すぐ治癒魔法をかけてあげるからね~」
「わ~、ありあちょうごじゃいましゅ~」
「ぬ―――――!! ティク、アンタ抜け駆けも大概にしなさいよ―――――!!」
ティクトレアがダメージの確認のためか、僕のおでこをスリスリさすると、ヒーゼリオフがドシドシと床を踏みつけた。試合中に良いのかな? と思ったけど、痛みがなくなるのは嬉しい。
「あら、フューくんったら、本当に頑丈なのね。魔力ゼロの状態で攻撃を受けたのに、オルの憑依で受けたダメージのほうが大きいくらいよ」
「うはは。そうだろう、そうだろう! 魔装をブラフに使うなんてとんでもない戦い方をするし、ヒーゼに三割を出させるし、さすがは俺の犬だな、フューリ!」
「えへへへへへ。はい。がんぱりまひた」
「そ、そんなに出してないわよ! せいぜい二割ちょっとよ、二割ちょっと! それに一瞬だったし!」
「ま、なんにしても反則負けは反則負けだろ。ほれ、壺出せ、壺」
「~~~~~ッ!! ふ、ふん。あんな壺なんかいくらでもくれてやるわ!」
「あえ? しあいはちゅうひれすか?」
「フューリ。頭回ってないんだろうが、ヒーゼの反則負けってことは、お前の勝ちってことだぞぉ? 良くやったな、おかげで壺ゲットだ」
オルナダ様が笑って僕のほっぺたをムニムニする。よくわからないけど、褒められているらしい。お尻の下でしっぽがバタついた。こうして僕は勝利の実感がないままに、オルナダ様の魔法で宙に浮かされて観客席に戻った。興奮したシシィたちが、
「お前ならイイ線いくとは思ったけど、まさか勝っちまうなんてな! マジですげぇよ!」
「魔装すごかったでしゅ!」
「我は、我は感激いたしました……!!」
「普通に戦っていれば、蹴飛ばされることなく勝てていたでしょうね」
と口々に称賛の言葉をかけてくれた。
無事オルナダ様に変な壺をプレゼントできたし、オルナダ様のお気に入りの剣を取られずに済んだし、ホクホク顔のオルナダ様が膝の上に座ってくれるし、良い匂いがするし、ふわふわぽやぽやして気持ちが良いしで、僕は大満足状態で残るみんなの試合を観戦することになった。
「ふんふん、ふすふす。はぁ~、おるにゃだしゃま、いいにおいれふれ~。あむあむ……」
「フューリ……。お前、酔ってるとウザいな……。面白いから良いかと思ったが、やっぱ唾でも飲ましとくか」
「わ~い、やったぁ~! いたらきまひゅ~」
頭に鼻を押し付け、耳を甘咬みしていると、ちゅーの許可が出たので、その場にオルナダ様を押し倒したら、
「「「よそでや」ってくんねーかな!」んなさいよ!」ってくれる?」
と、何人かに大きな声を出されてしまった。
第二十三話公開しました。
ガーティレイ遊ばれてますが、本作は魔族が桁違いに強いので、弱いわけではないのです。
フューリは一割開放のヒーゼリオフが動物か魔物だったら、魔装を使うまでもなく普通に倒して食べていたことでしょう。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!