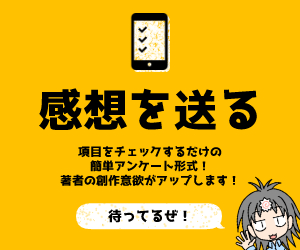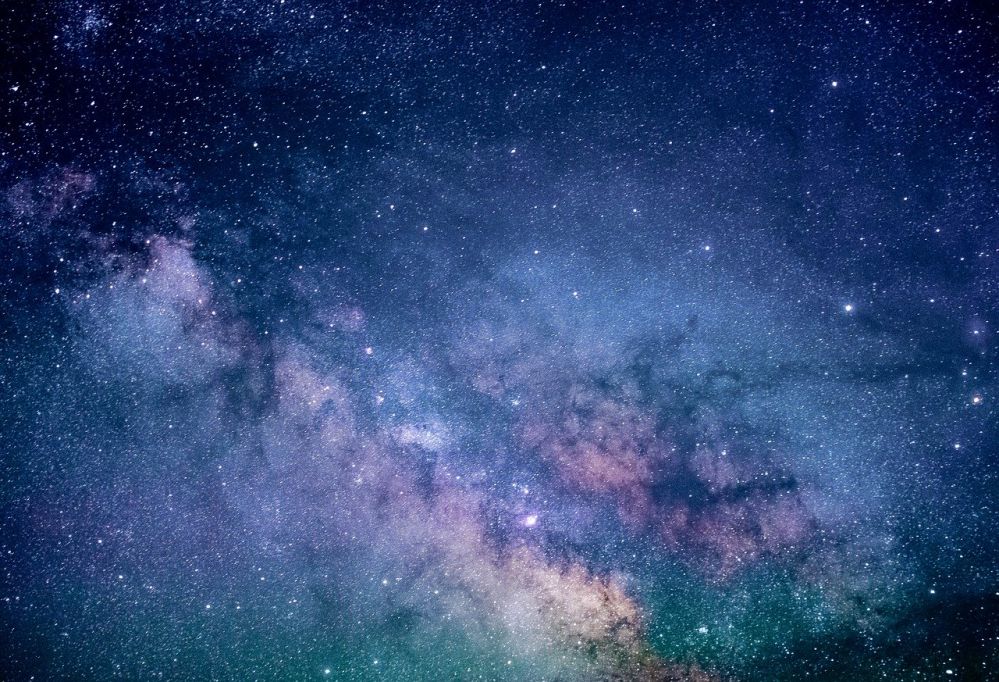
タイトルにパーティーってつく作品を書きたくて書いた、宇宙を走る列車の話。
あらすじは以下のような感じです。
母星を飛び出し、無人の星で途方に暮れていた星人の前に、突如、巨大な宇宙列車が現れた。
必死の思いで飛び乗った列車で目にしたのは、星人には到底理解できない光景で……。
以下、本文。
一
果てのない星の海。
そこへ浮かぶ小さな惑星の上、人型の星人がひとり、たばこを吹かしていた。
周辺の宙には、この星人以外、生命体はない。
星人がギリギリ座れるサイズの惑星に、錆びれたバスの時刻表が一本、佇んでいる。辺境の銀河の、さらに辺境にあるこのバス停には、他に待つものもなく、また、周辺に車はおろか、人影一つ見えはしない。
星人はたばこを踏み消し、乗ってきたスクーターのバッテリー残量を確認する。
何度見ても、ほぼゼロである事実は変わらない。母星に帰ることも、近隣の星に向かうことも、不可能なのは明白だった。シート下や、フロント部分の収納を探ってみても、状況を解決してくれそうな物は、先程吸ったたばこ以外は、見つかりそうもない。そのたばこも、もう吸い尽くしてしまっていた。
星人は途方に暮れた。
空路用のスクーターなら、栄えた星に到着できる程度のパワーはあるはず。そう考えてここまで来たが、惑星内用の輸送機で、惑星間を移動するのは、土台無理な話であった。
そもそも本当に考えたかすら怪しい。
兵隊たちに取り囲まれ、唯一の相棒を取り上げられそうになったところをからがら逃げて、たまたま鍵が外されたこのスクーターを奪い、ひた走ったのだから、とてもまともな頭ではなかったはずだ。なにより、酔っ払っていた。
時刻表を見る。次の便が来るのは三日後だった。
星人は背負ったラッパを構え、思い切り息を吹き込む。
蜷局を巻いた管を通り、反対側の銀の花から、パァーッと軽快な音色となって吐き出される。明るい音を選んで連ね、無意味な不安や後悔ごと、宙の彼方へ吹き飛ばす。
このままここで干上がってしまうのではないか、なぜ酒なんか口にしてしまったのか、家へ帰れたとしてその先どうしろというのか。そんな思考を音に変え、次々飛ばしていくと、だんだん頭がクリアになっていく。
隣のオンムズズ星は遠い。行けばそれだけで、スッカラカンになってしまう。母星のカードは使えないだろう。とすれば、スクーターを売ることができたとしても、数日食いつなぐのがやっとのはずだ。相棒を手放すことは、もちろん出来ない。オンムズズでは、今していることを往来でやれば、金を貰えることもあるらしい。母星では恐ろしくて、とてもできやしないが、他の星ならば……。いやいや、そんな保証はない。けれどもう、やるより他に道もない。一日鳴らして、粘土のような栄養食ひとつ買うのがやっとかもしれない。
ぐるぐる悩む。
帰るなどという選択肢は、ありえなかった。しかし、だがしかし、それもまた、たまらなく恐ろしい。
恐怖が湧くたび、星人は一層激しく、息を吹き込む。その様子は、踊り狂うようであり、また、もがき苦しむようでもあった。
ふいに、星人はラッパを放した。ラッパとラッパに結んだ肩掛け紐が、ふわり、顔の前に留まるのを、掻き分けるように背中へ追いやる。
宙の彼方、だんだんと大きくなる光がある。
正円の光から、車や船ではないことがわかる。バイクやスクーターの類にしては、急速に大きくなりすぎる。だが、確実に、なにかしらの輸送機ではある。それが、猛スピードでこちらへ接近していた。
星人はスクーターに飛び乗り、光へと走る。
接近すると、それが巨大な列車であるとわかった。
頭に、これまた巨大な筒を付けた、黒塗りの機関車が、何十という客車と貨車を連ねて、宙を走っている。
これだけ大きな列車なら、こっそり潜り込んでもバレないのではないか。列車に乗る宇宙海賊というのも聞いたことがないし、見つかっても殺されることはないはずだ。それに客車があるのなら、道中の仕事もあるだろう。新入りのフリでもすれば、今後の路銀を稼げるかもしれない。
飛び乗ろう。
轢かれて死ぬ可能性もあるが、逃せば、どの道、飢えて死ぬ。
星人は列車の進路付近で、スクーターを止めた。
とんとんと胸が高鳴る。
列車がギリギリまで近付くと、同じ方向へ、フルスピードでスクーターを走らせた。
並走すると、列車はますます大きい。星人が、中型種の中でも比較的、小さい人間であることを除いても、超巨大と言って差し支えない。機関車の下で回る車輪の直径さえ、星人を五人並べたより大きいだろう。
列車はその巨体の誇るパワーで、フルスピードのスクーターを見る間に抜き去っていく。隣を走っていたはずの機関車は遥か前方へ消え、続く客車と貨車も、次々と進んで行ってしまう。星人は焦り、ハンドルを切る。近付いただけでも弾き飛ばされそうだが、ギリギリまで寄せなくては、飛び移るのは無理だ。
星人は、なけなしの勇気を振り絞り、必死に腕を伸ばす。が、スクーターの方はその気がない。なにを絞ることもなく、充電切れによって速度を落としていく。ねじ切れるほどアクセルを捻っても、減速は止まらない。奥歯を噛みしめ、固く目を閉じて、星人はハンドルを叩きつける。
彼方へ走り去った列車を想い、遠くを見た。
しかしどうしたことだろう。列車は自分の隣で止まっている。
誰かが気付いて止まってくれたのだろうか? 一瞬、首を捻ったが、この幸運を逃せるわけもない。星人はスクーターを担ぎ、貨車の脇についたハシゴを登って、列車へ乗り込んだ。
気が抜けて貨車の屋根へ転がると、星人の目に、猛スピードで過ぎる星々が映る。どうやら、列車は止まったわけではなかったらしい。
宇宙を行き来する大型輸送機の多くは、走行中の安全のために、空間巻取装置を搭載している。その射程に入れば、輸送機の展開する空間に取り込まれ、一緒に移動することとなるのだ。元は宙魚を取る漁船で使われていた、古くからある技術だったが、宇宙へ出るのも初めての星人には、大変に珍しく感じられた。
ともかく、星人は招かれたわけでないということだ。なれば当然、身をひそめる場所が必要になる。
星人は手始めに、真下にある貨車の様子を探る。全長は走って三分、幅は一分ほどの大きさで、左右どちらも窓はない。隣の貨車との連結部分に、扉らしき物はあるが、走行中に出入りをすることはなさそうだ。
念のため、スクーターを隠しておこうと、星人は梯子を下り、連結部分にあるデッキの隅へと降り立った。
反対側の手すりが、随分と小さい。
デッキの下には、その上に十台は車を停められそうなほどの連結器が見える。星人はデッキ端の手すりへ、ロープ状の鍵を通し、スクーターを括り付けた。バッテリーパックを引き抜いて、上着の内ポケットへとしまう。
車内で満タンのバッテリーパックと交換して、いざとなったらスクーターで逃げ出そう。
星人は客車へと向かった。
スクーターを隠した貨車は、列車全体のほぼ真ん中に位置していた。前後どちらも、吸いこまれるような黒さの貨車と、明かりの灯る客車が、数両置き、交互に並んでいる。星人は一番近い、後方側の車両へ行ってみることにした。後方は機関車がない分、乗組員が少ないと考えたのだ。
屋根の上を歩き、端まで来ると、泳いで隣の貨車へ移る。背負ったラッパが、どこかへ行ってしまわぬよう、気を付けながら、それを五六度繰り返し、客車の手前の貨車の端へとやってくる。
見つからないよう、屋根に腹をつけ、そっと顔を覗かせた。
そうして客車デッキの様子を窺うやいなや、ひっ、となって頭を引っ込めた。
さまざまな星の人間を茹でた、さまざまな形状の鍋が、濛々と湯気を立てていたのだ。
星人の脳裏に、宇宙怪談で有名な、殺人キッチンカーのエピソードが過ぎる。
先々で居住民を誘拐しては、粉砕し、捏ねて、焼き、土地の主食に挟んで食すばかりか、駅前に陣取り、良い値段で売り捌いたという話だ。
ちなみにこの手の話の結末は、『特に○○星人の肉がよく売れたらしい』と、締め括るのが常だ。○○に入るのはもちろん、聞き手の出身星の名称である。
これなら海賊船の方が、マシだったのではないか。星人の身体を、恐怖が巡る。
音を出すわけにはいかないので、静かに、けれど懸命に深呼吸をし、きっと見間違いだと言い聞かせて、星人は屋根から顔を覗かせる。すると、照明に照らされた、煮えたぎる鍋の中から、一人の、おそらくスッパラド星人だろう、蛸のような人間が這い出して、腕とも脚ともつかない、緑色の触手を、目一杯に伸ばすではないか。
スッパラド星人は、熱には弱いはずである。ということは、あの鍋は、煮えているわけではないのかもしれない。
ひょっとすると、煮えた鍋のような動きをする、液状生命体にでも浸かっていただけではないだろうか。
恐怖心が和らいだ星人は、改めてデッキの様子を見回してみる。
スッパラド星人以外にも、イチラック星人や、グラウ星人、人型のツーィア星人、他にも見たこともない形状の人間も、鍋を出たり入ったりしている。よく見れば皆、水着を着用している。星人はようやく、眼下の鍋が風呂であり、具材は乗客であることに気付く。
よくよく眺めてみれば、デッキの上には大小様々のリクライニングチェアやテーブルが並び、背の高い直方体のロボットが、チューブのような腕で、ドリンクを給餌している。
湯気だと思った蒸気は、湯船ではなく、その脇の小さな箱から噴射されていた。のぼせたらしい乗客がその前で顔を仰いでいるのを見るに、冷水の噴霧器らしい。
星人はこの光景に、心当たりがあった。
母星の地底深くに隠された、旧型の星間電波受信期で拾い見た、古代の映画だ。今は無きドウドウ星で作られた作品の、星一番の楽園として登場する島のシーンによく似ていた。
なるほど、これは、リゾートというヤツに違いない。
星人は胸を撫で下ろした。
と同時に湧くのは、上等な食事を失敬できるかもしれないという期待と、法外な賃料を請求されるかもしれないという不安。
だが星人は、潜り込む、身を潜めることに関しては、若干の自信があった。
なにせ母星では、お尋ね者だ。
仲間たちが皆捕えられ、姿を消しても、星人だけは捕まらず、これまで逃げ延びたのだ。孤独に耐え兼ね、生まれて初めて酒を盗み、酔っぱらって住処を出たりしなければ、今も母星の地底でひっそり暮らしていたことだろう。
星人はデッキの上を素早く泳いで渡り、客車の屋根へ降りる。
反対側のデッキへ行こうと歩き出すと、屋根の一部が透過素材になっているのが目に入る。
覗くと中は、形状も色もさまざまの風呂やプールが並んでいた。
中央が吹き抜けの二階建て構造。二階の壁面にはフードコートが、一階のプールサイドでは、緑色の屋根を被った横長直方体の調理ロボットが点在し、乗客にドリンクや軽食を振る舞っている。
星人は、たった今、調理ロボから白いトレイを受け取った乗客に、目を奪われた。正確には、白いトレイの中身に。
トレイには、カラフルなサイコロ状の食品を挟んだ、半分に割った果実のような物が乗っている。
乗客はそれを、上にかかった白や黄色や赤のソースを零さないよう、スプーンで口へ運んでいく。
星人の腹は、獣のように唸った。
どんなものかはわからないが、あれを食べてみたい。強く、そう思った。
ガバと服を脱ぎ、下着姿になる。水着も下着も大して変わらないから、この格好であれば、潜り込めると考えた。
脱いだ服を、ラッパの肩紐で、一纏めにし、さっきのデッキへそろそろと降りて、照明の後ろへ隠す。目立たぬよう、いかにも乗客ですという顔で、堂々と車内へ通じる扉を開けた。
乗客たちはもちろん、ロボットたちも、星人に注意を払う様子はない。
さりげなく見回してみても、乗組員らしき人影もなかった。
星人は少しだけ気を緩めて、調理ロボットの前までやってくる。ロボットはセンサーで星人をスキャンすると、星人の目に、星人が好ましく感じる映像を映し出す。
奥にキッチンのついた、車風の屋台を背景に、人型星人の中でも容姿が美麗とされる、トゥヤクミューイ星人のアバターが現われ、猫のような三角耳をピンと立て、注文を聞いてくる。
星人は初めて目にする機能に面食らったが、ただの映像のはずだと言い聞かせて、怖々、先ほど目にした物と同じメニューの小型星人用を指差す。
「少々お待ちください」と告げたアバターが、材料を切ったり持ったり、目の前で調理してくれているかのような映像が再生され、「熱いうちにどうぞ」と手渡してくる。
両手に余るサイズの大きなトレイだった。
代金の請求はない。
先に一定の金額を支払って、中での支払を不要にする仕組みなのだろう。上手く潜り込みさえすれば、飲み放題、食べ放題だった、母星の上級国民パーティと同じ仕組みだ。
なかなか良い列車に乗ったかもしれない。
星人は受け取ったトレイの中身を口へ運ぶ。果実だと思った物は芋だったらしく、ほくほくとした食感だった。大きさは、星人の頭より二回り小さいくらい。サイコロ状の物体は、加工肉や、様々な野菜をカットしたもので、食感や味がそれぞれ違う。それが脂と、ブニブニした食感でびろびろと伸びる物質と混ぜ合わされていた。
三色のソースは、それぞれ甘い、辛い、しょっぱい味で、全部まとめて食べると、口の中でケンカをするかと思ったが、咀嚼するうちに馴染んで、絶妙な味になる。
昔潜り込んだパーティで食べた物に比べると、高級感はなかったが、ガツンと殴られるような、強烈な美味さだった。星人は近くのベンチに腰を下し、夢中で芋を貪り食った。
「ねぇ、それ、一口もらえない?」
ギクリとして顔を上げると、目の前には星人よりも一回り小柄な、トゥヤクミューイ星人が立っていた。頭の上の猫耳と、先端の毛の白い尻尾を、ピンと立てている。毛色は沈む夕日のようで、瞳は金色だった。
先ほど見た映像より、本物の方がよほど美しいな、と思った星人だったが、下手に絡まれては危険なため、黙ってトレイを渡すことにした。トゥヤクミューイ星人は、「ありがと」と、微笑むと、隣に腰を下して、芋を食べだした。
「これ食べてみたかったんだけど、一番小さいのでもこのサイズでしょ、中々手が出なくて」
「むむ……。まこと、おっしゃる通りにござる」
星人はそのまま立ち去りたかったが、トゥヤクミューイ星人が気安く話し始めたので、タイミングを逃してしまった。こんな場所では、「急ぎますゆえ」と席を立つのも不自然だ。星人は適当に世間話でもして、この場をやり過ごすことにした。
「あぁ、えぇ……、ここの食事で一番の美味を伺っても?」
「うーん、私のイチオシはヒュールア星料理ね。動物の肉を焼いただけの物が多いけど、肉食の口には馴染みが良いっていうか、ワイルドな食事を楽しみたいときはピッタリって感じ。星を出せば、ロロスト銀河産の青角牛の肉も食べられるしね。そっちは?」
「その芋にござる。今のところは」
「あはは。ジャンクフード好きなの? ならクーニョー星料理とか良いかもね。ピッチャってヤツとか、チーズたっぷりで美味しいよ。第四フードエリアの七ブロックにあるから行ってみて」
よし、ここを出たらフードエリアというヤツに行こう。
星人が目的地を決めると、トゥヤクミューイ星人は礼を言ってトレイを返した。
一緒にサウナでもどうかと誘われたが、なんのことかわからないし、これ以上関わる気はない。星人は「まだ泳ぎたいゆえ」と断った。トゥヤクミューイ星人はさほど残念でもなさそうに「残念」と呟くと、ベンチの正面の方向へ歩き出す。
「そうだ、あなた、第三項講習は受けた?」
何歩か歩いたところで、トゥヤクミューイ星人が振り返る。星人には意味不明だ。
だが問われるということは、必ずしも全員が受けるものではないのだろう。星人は黙って首を振った。
トゥヤクミューイ星人はまた、「残念」と呟き、今度は振り返らずに歩いて行った。
星人はほっとして、残った芋を平らげ、フードエリアを探す。
道中にあったクリンマシンで身体と下着を洗い、八割の乗客が着用している、カクテルグラスのロゴが入った客用着を拝借した。大きなタオルの入った、同じロゴの手提げカバンも借りて、デッキに脱いできた服とラッパを回収し、乗組員用と思われる黒のスーツと一緒に中へ入れた。
星人は常に用心して行動していたが、そんな必要ないのではないかと思うほど、車内の警備は緩かった。そもそも警備など、されていないのではないかと思うほどだ。
いたるところに監視装置らしき物体は設置されているものの、誰一人、自分を捕まえに来る気配がない。乗組員らしき黒スーツの人間もチラホラ見かけるが、皆、客に混ざって遊んでは、酒を呷ったりしている。働いているのはロボットばかりで、そのロボットも、注文に対し、代金を要求することもなければ、認証の一つえ求めて来ない。
夜中まで、計六両ほどの車両をうろつき、ピッチャ、もとい、ピッツァを平らげ、湯に浸かり、個室の清潔でふかふかなベッドへ横たわった頃、星人はひょっとして自分は隕石にでもぶつかって、すでに死んでいるのではないかと思い始めた。
あるいは、あの盗んだ酒を飲み干した後、住処の床でぶっ倒れて、夢を見ているのかもしれない。
星人はベッドを降り、腰を落として両手を脇腹に構えると、真っ直ぐ前方へ突き出してみる。これが夢であれば、手から光線が出るはずだ。
が、なにも出ない。
となると、夢ではないらしい。
星人は少し考えて、手提げカバンから黒スーツを取り出し、身に付けた。
ラッパを背負い、念の為、手提げカバンも持って、個室をあとにする。向かったのは、フードエリアを探している途中で見つけた、小さなステージのあるバーだった。
巨大な客車の中に、いくつもの小さな空間が詰め込まれているのだろう、細長い廊下が縦横に走るエリアの一角に、そのバーはあった。
小さな丸窓の付いた、黒いドアを開け、青い照明の灯る、薄暗い室内へ足を踏み入れる。
バーカウンターを投影するロボットと、テーブル席が二つあるだけの狭い室内。その奥に、一段高くなっているだけのステージがあった。地下深くの穴蔵で、仲間たちが作ってくれたステージに似ていた。
星人は吸い寄せられるようにしてステージへ立ち、ラッパへ口をつける。
ゆったり息を吹き込み、静かに鳴らす。
いつかのあの穴蔵で、外に漏れ聞こえぬよう、そっと、協奏したときのように。
星人の母星では、あらゆる娯楽が禁じられていた。音楽もその一つだった。
下級国民は政府に徹底して管理され、労働を基準に、起きてから眠るまで、全てのスケジュールが決められ、余暇はない。
実用書以外は書物さえ禁じられ、唯一、好きに楽しめる物といえば、法外な値段で売られる、酒とたばこだけという有様だった。
耐えられるものは喜んで耐えたが、そうでないものは地下に逃れるしかなかった。星人もその一人だ。
まともな暮らしはできなかったが、代わりに手に入れるだけの知や芸術に触れられる。
星人は自分の暮らしを、地上の者たちより余程豊かと思っていた。とりわけ、相棒と共に、仲間たちを楽しませるメロディを奏でる幸福感は、唯一無二だった。
一人、二人と消えた仲間たちの行方は知れない。捕らえられたのか、自ら地上に戻ったのか、それとも別の星へ逃げたのか。生きているのか、死んでいるのかさえ、わからない。だがもしも死んでいて、自分もまた死んでいるのなら、この音を聞きつけて、飛んできてはくれないだろうか。
恋しさを、遠吠えのように、音に乗せる。
呼び声に応える者はなく、音色に耳を傾ける者もない。
ただ薄暗い室内で、映像のバーテンダーが、穏やかにテーブルを拭いている。星人はそれでも、祈るような思いで、ラッパを鳴らす。
鳴らして鳴らして、息が枯れ、倒れて眠るまで。
二
きっと、二度と、目は覚めないのだろう。
星人のそんな予想は見事に外れた。
揺すり起こされ、しまったと思ったときには、五、六人の黒スーツが、自分を覗き込んでいた。明るくなった室内は狭く、そんな人数に囲まれては、逃げ出す隙きもない。上はどうだ? と思ったが、天井は低く、跳んでも頭を打つだけだろう。
「ややや、お見苦しいところをお見せして申し訳ない。どうやら昨夜は些か飲みすぎたようでござる……」
酔い潰れた客を装い、ラッパを背負って頭を掻き掻き、その場を離れようとするが、当然、止められてしまう。
乗組員のスーツを着ているのだから、乗客のフリは無理があった。
星人は唇を噛み、身構えたが、どういうわけか、黒スーツたちは穏やかな表情で、ケラケラと笑い出した。
「デュフフフ、アンタ、いくら酔っ払ったからって、チップ剥がすのはイカンよ」スッパラド星人が、くぐもった声で笑って、
「よりにもよってこのエリアだしな。おかげで探すのに苦労したぞ。さぁ、脳はどこだ? 人型だから頭で良いんだよな?」大きな熊のようなイルイグ星人が、星人の頭を指した。
拒否する間もなく、黒く硬そうな指先が、星人の額に透明のフィルムを乗せる。すると後ろの方にいた、透明で肉厚な二本の触覚と、ブラシの毛のような無数の腕を持つ軟体系星人が、「おや、まだ数値が良くないね。というか、かなり悪い」と、細長い身体をくねらせる。
「そ、そんなに悪いのでござるか?」
星人は、さも、”数値”について知っているかのように尋ねた。
黒スーツたちの会話の内容から、今、頭に付けられたフィルムで、対象者の位置と、数値を把握するだろうことが予想できた。
数値が悪化すると、対象の位置を特定し、改善するのが仕事なのだろう。問題なのは、その数値が、なにを示すものなのかということだ。
星人はなんとかそれを探り出したかった。
「まぁねぇ、昨日のことも考えると、最後尾に隔離も考えないと、って数値かもねぇ」
「昨日、というと……?」
星人は内心、身震いしつつ、尋ねる。
「アンタ、どれだけ飲んだんだい? 客車一両丸々ダウンさせるくらい、ネガってたのに?」
「まぁまぁ、またハッピーになれば問題ないさ。君、煙でもどうだい?」
「二日酔いに煙はダメだろ。メシ食わせて、水飲ませて、寝かしといた方が良いんじゃないか?」
「それじゃ隔離と変わんないじゃないか」
黒スーツたちは、星人になにを勧めるかについて、言い合いを始めた。
飛び交うのは、酒、煙、メシ、風呂、マッサージ、スポーツといった単語ばかり。初めのうちは、監禁、拷問、放流、解体などの隠語なのかと思って聞いていたが、どうも本当に言葉通りの意味らしい。
星人はますます混乱した。
「それじゃあ、これは? あのトランペットを演奏してもらう。楽器のヤツは大抵それでご機嫌だ。どうよ?」
首長の甲殻系星人が、星人の背中のラッパを指す。他の黒スーツたちは感心したように息を漏らし、「それが良い」と頷き合い、一斉に星人の方へ向き直った。
吹け、ということだろう。
星人は仕方なく、ラッパを構えた。足で床を鳴らし、軽快な音で演奏に入る。
仲間たちにせがまれ、よく吹いた曲だ。
大昔に全宇宙で大ヒットした映画のテーマで、星人も気に入って、相当練習した曲だった。黒スーツたちも、イントロでそれとわかったらしい。「ナイス」「やるね」「渋い」と、リズムにノリ、手拍子を始めた。
久方ぶりの聴衆に、少しだけ調子に乗った星人は、ラッパを左右に振ったり、仰け反ったり、ターンしてみたりと、パフォーマンスを披露する。黒スーツたちも思い思いに踊り出したりするものだから、一曲吹き終える頃には、その場の全員がすっかり楽しくなってしまっていた。
「アンタ、やるじゃないか。星をやるよ」
「だね。こっちの数値もアゲアゲになったし」
黒スーツたちは口々に称賛を述べては、頭の前で星人に向かい、手を振った。
一体なんのことかと思った星人だったが、先ほど頭につけられたフィルムのせいなのだろう。頭の中にカウンターのイメージが浮かび、手が振られる度、数値が増えた。所謂投げ銭なのだろうが、ずいぶんと先進的だ。
星人が礼を言う。黒スーツたちは「次はもっとデカいフロアでやると良い」と言って、にこやかに立ち去る。どうやら数値とやらは改善されたらしい。
ほっとすると、視界が歪んだ。星人は袖で一度、目を拭い、昨夜の部屋へ帰って、休むことにした。
道中は夜に比べると、人通りがまばらで閑散としていた。
すれ違うのはロボットだけで、皆「サンドイッチはいかがですか」と尋ねてくる。
言葉の意味がわからない星人は、三回目にやっと、黒い液体の入ったカップと、野菜や加工肉の挟まった、薄茶色で楕円の食べ物を受け取った。それらは数秒でお腹へ消えた。
個室のあるエリアへ戻った星人は、蜂の巣のように並ぶ、黒い六角形の中から、昨日の部屋を探す。
ドアは、空室なら中央に緑の円が、使用中なら赤字で利用者のサインが表示されている。外出中は黄色のサインだ。
星人はラッパマークのサイン目掛けて、水中から浮き上がるように、床を蹴った。
重量がほぼゼロに設定されているらしい通路では、身体が容易く浮かび上がる。
すいとドアの前までたどり着き、白の縁に設置された取手を捕まえ、ドアに手を触れる。ピピ、と音がして、砂が落ちるようにドアが崩れ、中に入ると、ドアはまた、元の黒色の六角形に戻った。
昨日はてこずったが、慣れればなんということはない。
星人はふふんと鼻を鳴らし、改めて室内を見回す。
右側にベッドが一つ。その左と手前にはそれぞれベッドの半分ほどの空間が設けられている。高さは星人の身長よりやや高いくらい。床も壁も天井も、黒く、つるりとしている。床には手提げカバンが、昨日の状態のまま転がっていた。
昨日は、完全に寝るだけのスペースに思われた部屋だが、ドアの仕組みを考えると、壁のどこかにでも、触れると崩れる部分があるかもしれない。
星人はそっと壁を撫でて回る。予想通り、室内には数カ所、崩れる壁があり、中には、収納スペース、用途不明の機械が置かれたスペース、簡単な飲食物を作るロボットのいるスペースがあったが、星人の求めていた、列車案内の類の物は見つからなかった。
今朝は運良く無事に切り抜けられたが、この先も全て上手くいくとは限らない。この謎の列車がどんな場所なのか、せめてもう少し、情報を得たかった。
星人はしばらく、見つけた機械をこねくり回してもみたが、結局使い方がわからず、諦めてベッドへ転がった。目を閉じて、今朝言われた「デカいフロア」という言葉を思い出す。
演奏をするための、大きな会場があるということだろうか?
そこへ行けば、咎められることなく、好きにラッパを吹けるのだろうか?
ともすれば、映像でしか見たことのない、ライブというものが見れるのではないだろうか?
思うほど、そわそわとして、一体、それはどこにあるのだろう? と考えた。すると、目の前に、ふわりと地図が浮かび上がる。星人は一瞬、驚いたが、今朝貼られたチップの存在を思い出し、落ち着いて地図を眺めた。
この列車の客車は計ニ十一両。五から八両の貨車に挟まれ、七つに分かれている。車両間の移動はテレポート装置で行われ、外へ出る必要はない。今いる個室エリアは最後尾に位置し、デカいフロアとやらは、昨日のプールエリアの隣にあるようだ。
星人は行き方を確認すると、このイメージの全体像が見れないだろうかと考える。
地図のイメージが、目次へと変わった。
表題は『銀河貨物列車ヴァルカノス号 総合案内』。下には、概要から索引まで、百以上の項目が並ぶ。概要の項を開くと、穏やかな音声で、列車についての解説が流れた。
要約するとこの列車は、全宇宙を股にかける、新進気鋭の貨物運送社が所有する輸送機の一台で、高揚感や、幸福感といったポジティブな感情をエネルギー転換して運行するらしい。
そのため乗員、乗客の区別なく、常にハッピーでいることが義務付けられているという。料金についての項目はなく、替わりに各銀河通貨と星の両替レートが載っている。
星人は昨日目にした光景や、先ほどの黒スーツたちの対応に、ようやく合点がいった。
パッと飛び起きて、ラッパを背負い、デカいフロアへと向かう。
今朝、黒スーツたちにもらった星は、全部で三十ポイント。
母星の通貨なら、下級国民向けの一番上等な酒が、四ダースは買える額だ。
ここの乗車券がいくらなのかは知らないが、もしも無賃乗車がバレても、星を貯めて支払いをすれば良い。バレなければ、降りた後の路銀がたっぷり作れるだろう。
ラッパを吹いて星が稼げるなら、滞在中、稼げるだけ稼ごう。
星人はそう、心に決めた。
デカいフロアは、パーティエリアにあった。
辺りは静まり返り、人の気配もない。
どのドアも、開いてはいるものの、『夕方オープン』と案内が出ているだけで、中は無人。照明は落ちていて、ロボットさえスリープしていた。
決意を胸にやってきた星人は、拍子抜けしてしまった。
だが同時に、安堵しもした。
このエリアの部屋は、どれも広すぎて、落ち着かなかったのだ。
試しに、覗いた中の中位の部屋で鳴らしてみたが、あまりにも音が響いて、怖くなり、飛び出してしまったほどだ。
そもそも、長い間、暗い地下の穴蔵で暮らしていた星人とって、広く明るい場所というのは、それだけで恐怖を抱かせる。
しばらくは、今朝のバーで吹くことにしよう。
肩を落とし、来た道を戻ろうとして、パッと振り返った。
かすかに、ラッパの音が聞こえた気がした。
星人は音の出所を探る。
赤い絨毯が引かれた廊下の奥の奥。それまで覗いたどの部屋よりも巨大なホール。そのステージの端の方から、その音は聞こえてくる。薄暗いホール内の壁側を、そろそろと歩き近づくと、ステージ横の小さなドアから、細く、オレンジの灯りが漏れ出している。
その中で一人の人間が、一音ずつ確かめるように、太く、曲がりくねった、金色の楽器を鳴らしていた。
吹き込み口があり、末端が円形に広がっていることから、ラッパの仲間であろうと予想される未知の楽器に、星人は目を奪われた。
やがて試奏を終えた奏者が、メロディを奏でだすと、音を立てないよう、そっと仰向けに寝転がる。
自分のラッパとは違う、暖かな音色が心地良い。
しばらく穏やかな曲が続き、次第に明るくなって、その後は激しくなった。
星人の身体は旋律に従い、ウキウキとなる。指先がひとりでに、腹に乗せたラッパを叩く。
そうして調子良く酔いしれていると、ふいに、ラッパの音が止んだ。閉じた視界が、すっと明るくなる。
なにごとかと目を開けると、光の帯の中央に、頭に二つの三角がついた黒い人影が、逆さまに立っていた。
「あ、昨日の!」
声と、慣れた目に写る、耳と尻尾の形で、星人はその人影が、プールで芋を分けた、トゥヤクミューイ星人であると気付いた。
「こ、これはどうもっ、いや、その、綺麗な音色が聞こえたもので」
「なら一緒にどう?」
星人のラッパを見たトゥヤクミューイ星人は、親しげに、起き上がった星人の手を取って、光の中へ招き入れる。強引さに面食らい、手を引きかけた星人だったが、部屋の奥に、ある楽器を見つける。
お気に入りの映画のワンシーンで演奏されていた、名前も知らない楽器。
黒く大きい脚のついたそれへ、吸い寄せられた。
真っ直ぐに歩いていって、そっと手を触れる。その表面は、星人の想像より暖かく、滑らかだった。
「……ピアノも弾くの?」
「い、いえ、実物を目にするのは初めて故、つい……。これは、ぴあの、というのでござるか?」
「トランペットより、メジャーな楽器のはずだけど……。聞きたいなら、夜には誰か弾くと思うよ」
「ほう。それは……、ぜひ、聞いてみたいものでござ……、あいや、失敬」
想像のピアノの演奏にうっとりしかけた星人は、慌ててピッと姿勢を正す。
「ふふ、触りたいなら、気が済むまで触ってからでもいいけど?」
「いやいや、某は、こいつの鳴らし方を知りませぬ故……」
「叩けば鳴るよ。ほら」
トゥヤクミューイ星人は、黒い塊の細くなった部分を持ち上げ、現われた、馬の歯のような、白いブロックを押す。
ポーン、ポーンと弾むような音が鳴る。
映画で聞いたよりも、ずっと澄んで、どこまでも伸びていくようだった。
促されて星人は、恐る恐るブロックを押してみる。ピアノは、ピン、と控えめに鳴る。
その様を見たトゥヤクミューイ星人は、逆に、思い切りブロックを叩いて、大きな音を立てみせる。
星人は先ほどよりも強く、同じブロックを押す。
強さの分、音が大きくなった。
強さを変え、位置を変えて押すうちに、瞳が煌めき、口元がむずむずと緩んでいく。
トゥヤクミューイ星人は、ピアノに頬杖をついて、星人の様子を愉快そうに眺めた。
「ほぅ……。美しい音が鳴るものですなぁ……」
「……あなた、名前は?」
「おお、これは、申し遅れた、某、×××××と申しまする」
「なんて?」
「×××××にござります」
「……発音、難しいのね。ニルでも良い? 私はタビ」
「かまいませぬぞ。タビどの、以後、お見知り置きを」
星人は深々と頭を下げ、タビは物珍しげに耳を動かした。星人に出身や、目的地、職業などを尋ねては、その答えに目を輝かせる。
星人の出身星は、星図にも載らない辺境。
タビから見れば、文明的に未発達な星で、文化風俗はスタンダードから外れている。
地下に潜み、盗みで生計を立てた話を始めた頃には、タビは、映画スターでも見るような顔になっていた。ラッパの演奏以外で、褒められたことのない星人は、少し、むず痒い気持ちになっていた。
めっちゃ中途半端なところで執筆途絶えてますけど、結構気に入ってる作品です。
そのうちちゃんとプロットを練って、完成・出版までたどり着きたいですね。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!