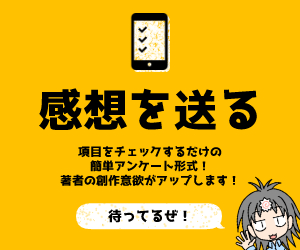ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第二十四話の続きになります。
第二十四話までのあらすじは以下のような感じです。
単身遠征をなんとか阻止したいフューリはシシィに相談し、ヒーゼリオフとティクトレアに相談する機会を作ってもらった。しかしそれは相談に乗るという名目でフューリとデートをするための時間であった。そんなこととは知らないフューリはヒーゼリオフと共にイラヴァールの市内を散策し、デートの終わりに有用な対策を約束してもらい、ティクトレアの元へ向かった。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下二十五話です。
【シシィ 八】
名前を呼ばれて顔を上げると、べそべそ泣いているフューリと目があった。
「シシィ! うあぁ、よ、よかった、生ぎでだあああ……!」
「お、おう……。なんか、悪い……。てか、ここどこだ?」
身体を起こすと、ざり、と頭の天辺がこすれた。腰に下げた光石のランタンひとつしか光源がないにも関わらず、周囲がゴツゴツとした岩で囲まれているのがハッキリわかる。
出口はない。完全に生き埋め状態だ。
私の記憶は、地面が崩れるのに巻き込まれ、なんとか戻ろうと魔力板を作ったけど、降ってきた瓦礫を避けきれずに頭を打ったところで途切れている。てことは、そのあと助けに来たフューリも一緒に埋まって今に至るって感じだろう。
「シ、シシィ……、ぐすっ、け、ケガは、大丈夫? ルゥちゃんはどう? ぜ、全然動かなくて……」
下にいるフューリに言われて隣を見ると、ルゥが仰向けに倒れていた。まさかと慌てて脈と呼吸を確認したけど、どうやら気絶してるだけっぽかった。なるべく動かさないように外傷を確認してみると、後頭部にでっかいたんこぶがあった。たぶん、私と同じ様に瓦礫で打ったんだろう。
まったく酷い目にあったなと、自分の額に手をやると、パリパリと生乾きの血が剥がれて、ちり、と傷口が傷んだ。
「……ルゥはこぶが出来た以外は大丈夫。私ももう血は止まってるし、なんともない。お前のおかげだな」
「う、うぅ! ぐすっ、うべべべべべ!」
「あー、わ、悪かったって。ほら、チーンてしろ。顔ぐちゃぐちゃだし、鼻水で溺れそうになってるぞ」
頭を掻きつつ、ハンカチサイズのスライムシートを取り出して、フューリの顔を拭ってやる。
生き埋めになった上に、友達二人がピクリとも動かず腹の上で倒れていたんだから、不安やら心配やらで気が気じゃなかったんだろう。どのくらい気絶してたかはわからないけど、随分泣かせちまったみたいだ。
「で? 今ってどんな状況だ? 気ぃ失ってたから、さっぱりでさ」
フューリを落ち着かせるため、このくらいなんでもない、ってな調子で尋ねた。
もちろん尋ねるまでもなく、状況が最悪だってのはわかってる。こんな状態にあるってことはつまり、フューリの力でもここを脱出できないってことだ。
フューリは今、両手両足を別々の岩に当ててる。おそらく、この空間が崩れないように支えてるんだろう。つまり私たちは、ただ生き埋めになってるんじゃなく、いつ死んでもおかしくない大ピンチ状態ってわけだ。
「え、えっと……、深さは、階層で言うとたぶん、五十層とかそのくらい。お、大きい瓦礫が来て、登れなくて、横に飛んだら崩れて……。うぅ……、ご、ごめんね……」
「おいおい、謝るなよ……。お前のおかげでまだ生きてるんだから」
また泣き出したフューリをスライムシートで拭いてやる。
きっとフューリ一人なら、パンチなり体当たりなりで瓦礫を粉砕して、強引に元いた場所まで戻ることもできた。だけど気絶した私たちを抱えてたんじゃ、そういうわけにもいかなかったんだろう。てか、跳んだ先が崩れて埋まったってのに、まだ生きてるどころか、全員ほぼ無傷ってのは、フューリの機転やら力量やらがあってのことだ。感謝こそすれ、責める気なんてない。
「とはいえ、あのバカデカイ魔力の柱のことを考えると、救助される見込みは薄いだろうから、脱出手段を考えないとな」
「き、救助は来るよ。ヒーゼリオフ陛下が迎えに来るって言ってたし……」
「あぁ……。なら来るだろうけど、それまでココの空気が持つかどうか……」
人間てのは種を問わず、呼吸で酸素ってのを取り入れないと生きられない。昔読んだ小説で、主人公の仲間の一人が生き埋めになるって展開があったけど、そのとき作中では二十時間がタイムリミットだとされていた。あの話がどこまで現実に則して書かれていたかはわからないけど、この空間に三人じゃ、私たちに残された時間はもっと少ないに違いない。
私はとりあえずルゥを起こそうと、ぽんぽんと肩を叩いて、目を開けたルゥに手短に状況を説明した。
「ぴ、ぴえぇぇぇ……。た、大変でしゅ……」
「まぁ、ビビるよな。でも三人とも無事だしさ、落ち着いて協力して乗り切ろうぜ」
「う、うん。わかった……」
「でしゅ……」
ぎゅっと拳を握ってみせると、二人は顔をこわばらせつつも頷いた。
「よし。んじゃまずは状況の把握だな。フューリは壁支えてくれてるけど、片腕か片足だけでも動かせないか? そしたらパンチかキックで……」
「た、たぶん無理だと思う……。二人が寝てる間に試したけど、ちょっとでも離そうとすると、パラパラってなっちゃうから……。それに外まで穴を開けられても、衝撃でこの空間ごとすぐ埋まっちゃうんじゃないかな……」
「そっか……。ルゥ、土魔法か操作魔法で支えたりとかできるか?」
「そ、そうでしゅねぇ……。うぅ……、この感じだと、今の魔力量じゃ難しそうでしゅ……」
「昼前に結構強いのと戦ったもんなぁ……。ルゥが無理なら私も無理だろうし……、手で穴でも掘るしかないかな……」
私は空洞の内部を見回し、掘れそうな場所を探す。通り抜けられるサイズの穴は無理でも、如意槍を伸ばして外に通じる場所に空気穴を空けられれば、少なくとも酸欠で死ぬことはなくなる。だけどこの空間の向こうはすべて土砂で埋まっていて、ステボの探知によると外までは百メートル以上の距離があった。
試しに岩の隙間に如意槍を差し込んで、グリグリと穴を掘ってみるけど、私の力じゃ貫通させる前にここの酸素が尽きるだろうことは明白だった。
「掘るのも無理そうでしゅね……」
「お、大人しく待ってたほうが良いんじゃないかな? ここは僕が支えてるし……」
「いや、脱出できるなら脱出しといたほうがいいぞ。いつ助けが来るかわかんないし、あの魔力の柱がもう一度上がったら、ここも巻き込まれるかもしれないし……」
想定される事態はほかにもあるけど、あえてそこで言葉を切った。こんな状況で不安を煽るのはマズイ。きっと二人もわかっているだろうし、わざわざ口にすることもないだろう。今はできることを考えるほうが重要だ。
「……そうだ、転移ロープ! あれで脱出できるんじゃないか?」
「えと……、無理だと思う……。あれで転移できるのは、僕だけだってオルナダ様が……」
「ぐ……、そういやそうだった……」
これで助かる! と思ってしまったあとだったから、つい、ガクンと肩を落としてしまった。魔術式を書き換えたらイケるんじゃ? と悪あがきでフューリのポーチから引っ張り出したロープを見てみるけど、恐ろしく細かい式がみっしりと書かれている上に、高度すぎてまるで理解できない。とてもじゃないけど、いじるなんて無理だった。
「シシィ。心配しなくても大丈夫だよ。きっともうイラヴァールに連絡が行ってるし、すぐにオルナダ様が出してくれるから、大人しくしてよう?」
フューリが穏やかな口調で呑気なことを言う。こいつはさっきまで混乱気味に泣きじゃくっていたくせに、私たちが無事とわかったら、すっかり落ち着きを取り戻したらしい。涙の跡は残ってるけど、表情もいつも通りの感じに戻っていた。必ずオルナダが助けてくれると確信してるんだろう。
「……ま、それもそうだな。オル様はヒー様と違って転移系得意そうだし、パッと出してくれるだろ」
「でしゅね」
なんだか本当に大丈夫な気がして、私もルゥも肩の力を抜いた。
たぶん、外は未曾有の事態に大混乱で救助どころじゃないだろうけど、魔族って連中はなにかと規格外だ。きっと他の種ぞくじゃ真似できないような大魔法でもなんでも使って問題を解決し、さくっと愛犬を救助するだろう。しかも飼い主のほかにも、こいつに惚れ込んでる魔族が二人もいる。なにも心配することはない。
はずだ。きっと。
【ヒーゼリオフ 三】
皆兵制を採るイラヴァールの市民たちは、例外なく全員が有事に備えた訓練を受けている。誰であろうと、普段なにをしていようと、要請があればすぐさま兵士として現場へ駆けつけ、対応する義務と能力を持っているってわけ。
だから最初の援軍は驚くほど早く到着して、今ではもう百人もの人間がこの最前線で戦っていた。殺した魔物の数も、とっくに千を超えただろう。にもかかわらず、スタンピードの勢いは未だに衰えない。
ていうかむしろ、増している。
「ちぃッ、なんなんだ、こいつら、キリがないではないか!」
肩で息をしたガーティレイが忌々しげに吐き捨てる。口には出さないけど、周囲のほかの人間たちも同じことを思っているだろうことは、その表情から容易に推測することができた。
「やっぱり元から断つしかないわね……」
私は小型の魔物が大型の魔物に押しつぶされてできた赤い肉の絨毯の向こう、今なお次々と魔物が這い出す大穴を睨んだ。
『ガーティレイ、ヴィオレッタ! 貴様らは交代じゃぁ! 下がって休めぃ!! 陛下と閣下は次の部隊が到着するまで、ご健闘いただけますでしょうか!? あと十分ほどでございます!』
ブゥプが念話で私たちに交代の指示を出した。私とキャサリーヌが同時に下がっても良いってことは、次に来るのはかなりの大部隊か、強者揃いということだ。
『ブゥプ、キャサリーヌ! ここ、任せられるわね?』
『お、お任せいただけるとあらば!』
『無論ですが、ヘバるにはまだ早いのではなくて?』
『そうよ。だから余力のあるうちに前に出るんでしょ』
私は二人の返答と同時に、渾身の正拳突きを放ち、正面の魔物を一層する。
『全員、聞きなさい! 今からこの極拳の魔王が、あの大穴に突入するわ! 私がスタンピードの発生源をぶちのめす間、踏ん張りなさい! そのくらいの根性、見せられるわね!?』
「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!」
周囲から一斉に鬨の声が上がった。この程度の激でも、多少のバフ効果はあるだろう。
『行くわ。あとは頼んだわよ』
『ど、どうかご無事でっっっ!!』
『武運を、ヒーゼリオフ』
私は頷き、大穴へと駆け出した。立ちはだかる魔物を体当たりで吹き飛ばし、一直線に進む。
あの穴の底になにが潜んでいるかはわからない。だけど、穴から這い出す魔物に、少なくとも二十三層まででは見かけなかった個体が混じり始めている。最下層である三十層の魔物まで、この規模で出現するなら、被害は今の倍以上になるだろう。一刻も早く発生源を始末しないと、取り返しのつかない事態になる。
ダッと地面を蹴り、穴の中央に躍り出た。飛行魔法で落下速度を増し、十、十五、二十と降りていく。そして三十層を過ぎた。
本来ならもう底についているはず。だけど目の前には、黒く巨大な虚が広がるばかりだった。
【ティクトレア 一】
書類仕事を終えて、「今日のランチはどうしようかしら?」なんてぼんやりしていると、慌てた様子のオルに念話で呼び出された。どうやらスタンピード訓練で、想定外の事態が発生したみたい。現場にはヒーゼもキャサリーヌも居るのに、五割開放と階位五階魔法の使用申請をしておけなんて一体何事なの?
当惑しつつ、わたくしは中央鐘塔の大会議室へと転移した。
天井に近い位置に跳んで足元を見ると、緑服たちが忙しなく地図やら資料を持って、走り回り、黒、赤、紺服たちが立ったまま大きな円卓を囲んでいる。円卓の中央には、ロスノー洞周辺の地形が再現された立体映像が映し出され、その上には、物資量のグラフ、スタンピードを起こしている魔物の数などが表示された魔光板が複数浮かんでいた。
それらを見る限り、今の状況はだいぶ不味い。
わたくしは今後の対応について計画を聞こうと、オルとユミエールの姿を探す。するとなぜか二人の背後にある壁にケイシイが「ボクなにも関係ないです」という顔で突っ立っていた。ということはつまり、なにかやらかしたということなので、もうこの時点から頭痛がしてくる。
わたくしはなにも見なかったことにして、ケイシイに背を向け、オルたちの後ろへ降りた。
「一体なにが起こったの?」
真面目な顔と声音を作って、さもなにも知らないかのように尋ねた。
「詳細は不明だが、おそらく通常予測される最悪より、さらに最悪の状況だろうと予想されている」
「えぇ。誰かさんはロスノー洞を百層まで掘り下げた上に、転移門を作って放置してたし、別の誰かさんはそんな危険な門の先に、魔力もりもりの引纏石を大量に捨ててくれたしね……」
あまりの話にぐるりと後ろを振り向くと、ケイシイは頭の後ろで手を組み、ぴーぴーと口笛を鳴らして「ボクなにも知りません」アピールをしていた。思わず内側から破裂させそうになるのをなんとか堪え、オルのほうが責任が重いことをアピールするため「どうして百層まで掘ったりしたの?」と非難の目を向けた。
「俺が俺のダンジョンをどうしようと勝手だろう。三十層までだとウチの連中の訓練には物足りない難易度だったしな」
「後者はその通りだけど、前者は違うでしょ。ロスノー洞はイラヴァールの資産なんだから」
オルが鼻を鳴らすとユミエールはすかさず反論した。わたくしも「しかも門を開いてほったらかすなんて」と追撃する。
「ほったらかしになんかしてないぞ。ちゃんと結界やら石材やらで隠して、市民が迷い込んだりしないようにしてたんだ。それを破ってバカをやらかしたのは、お前の飼い犬だろうが!」
「た、他種族に簡単に破られるような、しょぼい結界なんて、張ってないも同然でしょ!」
反論しつつ、わたくしはケイシイを睨む。
ケイシイはどういうわけか結界破りがやけに得意で、普段からわたくしが結界の中に隠したお菓子なんかをつまみ食いしている。しょぼい結界なんて言ったけど、実際はそう簡単に破られるような代物ではなかったはず。それでもそういうことにしておかないと、わたくしの落ち度ということにされてしまうから、この点は徹底して突いておかなくてはいけない。
「二人共、今はそんな話をしてるときじゃないでしょう。早く現地に行ってなんとかしてきて」
ユミエールがパンパンと手を叩いて、言い合いを止めた。
早い段階でオルが悪いことにしてしまいたかったけれど、確かに今は事態の収拾が優先。顔を見合わせたわたくしたちは、一時休戦して現地の上空へと転移した。
現地では豪雨のような鬨の声が大気を震わせていた。眼下の地表は血に染まり、大小さまざまな魔物の死骸がそこかしこに転がっている。兵士たちはその間を縫うように前進し、目の前に現れた魔物を次々と死体に変えていた。
前線の兵は適度に交代し、駆除数を一定に保っているし、後方には防壁が築かれ、魔法兵たちが大規模魔術の式を構築し、補給兵たちが次々に武器や回復アイテムを運び込んでいる。十数キロ先では五百人ほどの援軍が土煙を上げて、全力でこちらへ向かっているし、データで見たよりはだいぶマシな状態に見えた。
「ふふん。これだけの数を相手になかなかやるじゃないか。さすがはウチの市民だな。このまま見解くしてても大丈夫なんじゃないか?」
「この期に及んでまだ訓練を続行する気なの? 十分対処できるってわかったんだから、もう助けてあげなきゃ可哀想でしょ。次になにが起きるかもわからない状況なんだし」
「むぅ。それもそうか……。ならまずは掃除だな。お前は回復を頼む」
オルは不満そうに唇を尖らせたけど、すぐに気持ちを切り替えて自分の周りに赤い魔法陣をいくつか作り出した。呼応するように、地表にも夥しい数の赤い光が灯る。
光は魔法陣の上に半球形状に生成された魔力壁で、その内部に魔物を封じ込めていた。元から興奮状態にあった魔物たちは、突然閉じ込められ身動きが取れなくなったことでますます暴れ狂う。だけどオルが生成した魔力壁が破れるはずもない。魔物たちの必死の抵抗は、単なる自傷行為に等しかった。
オルの周りに展開している魔法陣は、呪文の部分が次々と高速で書き換わり、やがて一文字ずつ動きを止めていく。
そうしてすべての文字が動きを止め、魔法陣が完成すると、わたくしたちの目の前、つまりは兵士たちの上空に、地上で捕らえた魔物の心臓を集めて作られた、巨大な心臓が浮かび、同じく巨大な赤い手に握り潰された。ぐしゃりと勢いよく潰れた心臓は、周囲に血と肉片を撒き散らし、ぼたぼたと地上に落下した。
わたくしは下にいる兵士たちを気の毒に思いつつ、隣でドヤ顔をしているオルに呆れた。
魔物の心臓を潰すなら、地面から石槍を生やすほうが簡単だし、魔力消費も少ない。それなのに、消費魔力の大きい転移魔法で抜き取り、操作魔法で心臓型に並べ浮かせ潰して、映像魔法で光る手の演出まで加えている。なぜそんな手間を掛けるかといえば、使用申請が必要な上位魔法っぽくてカッコイイから程度の理由でしているんだから、バカバカしくてクラクラしてしまう。それもこれだけの魔法を魔法陣の展開からここまでわずか数秒で、正確に処理を終えてしまう魔法技術の高さにも、別の意味で目眩を覚える。わたくしはオルとほぼ同時に展開した魔法陣を、まだ弄くり回しているというのに。
「へ、へへへへへ、陛下あああああっっっ!!」
じっとりとオルを睨んでいると、下から「感激です!」と言わんばかりの声が上がった。降り注いだ魔物の血に困惑する兵士たちの上を、生成した魔力板をぴょんぴょんと渡って、人兎のブゥプが目を潤ませて駆け寄ってくる。
「陛下、閣下! まさかお越しいただけるとは! 本職、万感胸に迫る思いでありまっっっす!!」
ブゥプが叫ぶと下の兵士たちも、わたくしたちが駆けつけたことを認識し、「わああああああああああ!」と歓声を上げた。オルは兵士たちに向かって軽く手を上げ、大穴を覆うように結界を張りながら、ブゥプに現在の状況について尋ねた。
「現在は、ヒーゼリオフ陛下が根源を絶つと単身、穴の底へと向かわれております。で、殿下は魔力放出によりダンジョン崩壊に巻き込まれ、行方が……。ほ、本職が至らないばかりに、救助隊も出せず……っ」
「……そうか。まぁ、あいつはそう簡単にはくたばらないだろう。地上の戦況はどうだ?」
涙に喉をつまらせるブゥプに、オルは顔色を変えずに先を促す。
わたくしはフューくんの行方について、詳細を尋ねたかったのを、ぐっと堪えた。
「前線に立っている兵は三百。先程陛下に始末していただきましたが、地上にいた魔物の数は約五百。ヒーゼリオフ陛下が内部の魔物を始末してくださっているおかげか、大穴からの湧きはほぼ収まっており、殲滅まで十五分ほどの見込みでございました。また、およそ北へ五十キロほどのところに基地を建設しており、非戦闘員や負傷者はそちらへ移動済み、さらに大型兵器の組み立て、輸送を準備中であります……」
「ふむ。やはり手を出すまでもなかったな。よくやってくれた。フューリのことは俺がなんとかするから気にしなくていいぞ」
「ブゥプも指揮と援護で疲れたでしょう? 回復かけるから魔法陣の下に入ると良いわ」
「も、もったいないお言葉でございまっっっす!」
術式の調整を終えたわたくしが、足元に直径二百メートル程度の魔法陣を三枚展開すると、ブゥプは深々と頭を下げ、鼻をすすりつつ地上へ降りていった。
『はーい、じゃあみんな、できるだけ、わたくしの魔力に身を任せてね! 行くわよー!』
ブゥプが射程に入ったことを確認したわたくしは、効果を高めるために念話で全員に呼びかけてから、回復魔法を発動させる。魔法陣と兵士たちの身体が徐々に発光していく。回復魔法の効果によって、体内の疲労物質がゆるやかに消滅し、消費されたエネルギーが充填されるにつれて、そこかしこから感嘆の声が上がった。
「なんか魔物の死体も光ってないか?」
「死体を回復させたところで、生き返りはしないんだから良いじゃない」
「それはそうだが、こんなときに魔力を無駄に使うのは感心できないぞ」
「あなたにだけは言われたくないわ」
肩を竦めるオルに、思わず眉を顰めた瞬間、バァ―――ンという結界が砕ける音と共に、わたくしの回復魔法の比ではない、まばゆい光の柱が大穴から立ち上った。
「ぬお!? ま、また引纏石の爆発か!? お前、どんだけ大量に捨てたんだ!?」
「こ、この規模の魔力放出が二回も起きるほどは……」
言いかけて、ケイシイが捨てたのは昨日の分だけではなかった可能性に思い至る。事が済んだら、向こう百年はお小遣い減らしてやるから覚悟しなさい! と怒りを燃え上がらせていると、魔力柱の上がった方角の上空から、こちらに向かって、なにかが落ちてきた。
ヒーゼだった。
「嘘だろ。お前、やられたのか!?」
あちこち焼け焦げ、身体から煙を上げるヒーゼを、オルが操作魔法で受け止める。ヒーゼは両手足の金輪で強制的に出力を一割程度に抑えられているとはいえ、魔族であることには変わりない。それがこれほどのダメージを負うなんて。
わたくしもオルも少しだけ狼狽えた。
「っさいわね……。ちょっと油断しただけよ」
ヒーゼは苦い表情を浮かべつつ、自分で魔力板を生成し、膝に手を付き立ち上がる。
「……ヒー様はもう一回行ってくるから、アンタたちは地上の連中をなんとかしなさい。兵士たちの態勢も万全にしておいて」
「おい、せめて回復受けてから行け」
「そんな時間ないわ」
「ないってそんな、なにが来るっていうのよ」
明らかに疲弊しているのに、ヒーゼはオルの静止も聞かず飛び出していく。
去り際、
「第二波よ」
の一言を残し、あっという間に大穴の中へと消えた。
『ブゥプ、もう一度全隊の指揮を頼む。至急、陣形を整えろ。盾兵、重装兵を前に置き、迎撃しつつ後退だ』
直後、オルが険しい顔で、ブゥプに念話で指示を飛ばす。どうやら未だ危機的状況を脱してはいないらしい。オルがこんな風に表情を変えるなんて、一体あの大穴になにが潜んでいるのか。わたくしは探知の範囲を大穴の深部にまで広げた。
五、十、十五と順に探っていくけれど、さっきの魔力放出で一掃されたのか魔物の気配はない。二十、二十五、三十も変わらず。フューくんが地上に戻ろうと階層を登って来ていないかと、一層一層、丹念に探るけど、気配が見つからない。
四十層に差し掛かると、ちらほらと魔物の気配が出始め、徐々にその数を増した。五十層付近ではもう大群と呼べる数に達していて、それらが猛スピードで地上に向かっていた。群れを構成するのはここよりさらに深層の魔物。これまでの魔物に比べ格段に強力であることが窺えた。
でもこの程度、わたくしたちが地上にいる今、まるで脅威にはなり得ない。応援も続々と駆けつけているし、手を出さなくても兵士たちだけでも十分対処できるはずだ。なら一体なにが? とさらに探知を広げようとしたとき、穴を這い上がってきていた魔物の群れが地上に到達した。
『魔法隊、放てぇぇぇい!!』
ブゥプの号令で、魔法兵たちが一斉に魔力を高めると、大量の魔方陣が大穴をぐるりと取り囲むように出現した。魔法陣は周囲の砂や岩を飲み込んで、その中心から先端の鋭い楕円形の巨石を放つ。
限界まで強度を増した無数の巨石は、ほとんどの魔物を粉砕しつつ、全方位から穴の中央に向け進んで衝突し、散弾のように飛散して、穴の中の魔物を貫く。攻撃を受け落下した魔物は、下にいる魔物を巻き込んで、穴の奥底へと消える。
やはり危なげなく対処出来ている。オルはなにを警戒しているのだろう。再び探知を広げようと集中を高めると、
ゴウ―――――ッ
突風と共に巨大な岩の塊がわたくしたちの横を通り過ぎ、背後の岩柱を粉々に粉砕した。
「……魔法反射のようだな」
オルが大穴を睨んで呟く。
言われて飛んできた岩をよく見ると、確かに魔法兵たちが生成した巨石だった。
「そんな……。魔法反射なんて、まさかミスリルや、オリハルコン系の魔物が出たって言うの……!?」
「いや、その手のヤツではないようだ。だがそれ以上に厄介かもしれないぞ」
オルが指す砂埃の向こう、体高六メートルほどの一際大きな魔物が姿を現した。
ゴツゴツとした平たい身体に、先端の尖った六本の脚と、全身を覆い隠せるほど巨大で平らな二本のハサミを持つ、蟹型の魔物だった。暗い緑色の外殻は、意思を持つかぬように蠢く泥で覆われ、所々に黒い金属製の鎧を纏っている。魔族のネットワークに情報がないかと照会をかけるけれど該当がない。完全に未発見の魔物のようだ。
鎧蟹とでもいうべき姿の魔物は、ギィギィと不気味な声を上げ、胴体から突き出した目をしきりに動かし様子を窺っている。
「確かに鉱物を餌にしてそうな感じじゃないけど、魔法反射ができそうな魔法器官もなさそうだし、一体どうやって……」
「よく見ろ。あの鎧、ゴーレムだぞ」
バラバラになっていたから気付かなかったけれど、よくよく見ると鎧蟹は中身の泥ごとゴーレムを着ているような格好になっていて、胴体のあちこちにジタバタと動くゴーレムの手足がくっついている。鎧に入っている刻印が、ヒーゼがフューくんたちへの嫌がらせに、どこかから借りてきた新型のゴーレムのに似ている気がするけど、さすがに気のせいよね。同じものだとしたら、土、水、火などの物理魔法はほぼ通じないことになるし、蟹型のような生物は往々にして物理攻撃が効きづらい。兵士たちは苦戦を強いられることになりそう。
「迷うな。魔法で派手にぶっ飛ばしたくもあるし、うちの連中がどう対処するか見たくもある」
「異常事態なんだから、あなたが対応するべきでしょう」
この期に及んでそんなことを真剣に呟くオルに、わたくしは呆れた。
オルは不満そうに唇を尖らせはしたものの、やはり自分が対処したほうが良いと思ったのか、「ハサミだけでも封じてやるか」と片手を上げ、八体いた鎧蟹の下の地面を蔓のように伸ばして、ハサミを胴体に縛り付けてしまう。鎧蟹は拘束を解こうともがくけれど、巻き付いた岩石は灰色の金属に変わり、どれだけ暴れようと、びくともしない。
『よぅし、お前ら、後退を続けろ。蟹は適当なタイミングで仕留めておけ』
オルが指示を出すと、剣や槍で武装した物理兵たちが盾兵の後ろから飛び出し、次々と鎧蟹を仕留めた。魔法兵たちは二発目の巨石でほかの魔物を殲滅し、全隊が順調に後退していく。
「楽勝だな。これなら俺たちは、あっちに集中して問題なさそうだ」
「あっち?」
「見てろ。もう出てくる」
見るとオルが言い終わるかどうかというタイミングで、シューッという異音と共に、大穴から白い柱が生えた。直径は三メートルほど、その表面は鱗に覆われている。わたくしたち頭上、地上百メートルほどの高さでは、無数の赤い光が煌めき、その先からはダンジョンを崩壊させたのと同じ、紫色の魔力柱が天に向かって放たれる。
「……蛇だな。おそらくお前が捨てた引纏石を食って巨大化したんだろう」
「わ、わたくしが捨てたわけじゃ……! というかコレ、もう蛇って言うより龍じゃない!」
探知で確認すると、大蛇の全長は百五十メートルもあり、全身が鉄板並の強度の鱗で覆われ、お腹からは凄まじい魔力を放っていた。中にケイシイが不法投棄した、引纏石が詰まっているのだろうけど、魔力量からして尋常ではない量を飲み込んだことが窺えた。これほどの引纏石をお腹に抱えているなら、ダンジョンを崩壊させた、あの魔力砲とでも言うべき魔力放出を起こしたのも納得だし、少なく見積もっても、あと百回は打てるだろう。
というかこんな大量の魔力を魔物が体内に取り込んだりしたら、次になにが起きるかなんて予想もつかない。巨大化と魔力砲で済んでいる事自体、奇跡のようなものだ。オルが警戒するのも無理はない。
固唾を呑んで凝視していると、大蛇は口を閉じ、柱状に放射していた魔力砲を止め、球状の魔力弾を低く垂れ込めた雲へ向かってデタラメに放ちだす。
ほとんどの魔力弾は、そのまま雲を突き抜け飛散して消えたけれど、いくつかはバァンバァンと音を立てて爆ぜる。魔力板を鎧のように纏ったヒーゼが、魔力弾を粉砕しながら、大蛇目掛けて急降下していく。
「や――――――――――っ!!」
黄色に光る鎧の腕を大蛇も殴り飛ばせるサイズに拡大し、拳を叩きつけようと振りかぶる。
けれど大蛇が倒されることはなかった。
代わりにヒーゼが空高く吹き飛んで、力なく頭から落下してくる。矢の何倍ものスピードで大蛇が高く伸び上がり、魔力を纏った鼻先で突き上げたのだ。
「ち、ちょっと、ヒーゼ! 大丈夫なの!?」
わたくしは落ちていくヒーゼを、操作魔法で手元まで引き寄せる。
仰向けに浮かせたヒーゼは低く呻いて、「かすり傷よ」と力なく呟く。明らかな戦闘不能状態だった。
「ったく、一割しか出せないくせに無茶するからだ、バカめ」
「っさい……。これ付けてても、三割までは出るのよ……」
「瞬間的にだろうが。とにかくもう休め。ティク、下の救護班のトコに下ろしてやってくれ」
「え、回復は?」
「こいつが全快したところで、あの蛇相手じゃ対して役に立たないだろ。回復させる分の魔力を攻撃に当てるほうが有益だ」
状況が状況とはいえ、友人に対してあまりに無慈悲な決断に、眉がわずかに寄るのを感じた。けれどその判断が適切であることも理解できる。わたくしは憤りを覚えつつ、ヒーゼを地上の救護班へと引き渡した。
「ティク、お前は何階魔法まで承認された? 開放率は?」
「まだ、二階と、三割……」
「俺はどっちも一のままだから、少しばかり頼るぞ。まずは操作で持ち上げて、イラヴァールから遠ざける」
いつの間にか降り出していた雨に濡れた前髪を掻き上げ、オルは左手を掲げる。
わたくしもそれに倣い、タイミングを合わせて大蛇のお腹を押すように操作魔法をぶつける。
大蛇の上半分は衝撃によってドシンと倒れ、大地を削り、岩柱をなぎ倒しながら、大穴の南側へと飛んでいく。けれど下半分は大穴の中に隠れたまま、中々しっぽを出さない。
「そのまま押してろよ、ティク」
「え? ちょ……っ」
ぐんっと負荷が重くなり、大蛇を退けるスピードが落ちる。
抵抗される前に少しでもここから遠ざけたいっていうのに、一体なにを考えてるの?
じろりと抗議の視線を向けるより早く、大蛇のしっぽが引きずり出され宙に浮いた。
「そうら、飛んでけ!」
オルが掲げた両手を振り下ろすと、しっぽはギュンギュンと風を切り、大蛇の頭の上へ落ちた。
わああああああああああ! と後方から兵士たちの歓声が上がる。地上からは、オルが大蛇を倒したように見えたのだろう。
でも実際はただ少し遠くへ移動させただけ。対処を行うのはこれからだ。
「行くぞ」
「えぇ」
ヒーゼの状態を見れば、一割程度の出力では防御もままならないことは明らか。二人がかりでとはいえ、今のわたくしたちの手に負えるのか、検討もつかない。それでも魔族としてこの事態に対処しないわけにはいかない。
わたくしたちは互いに「油断しないように」と目配せをしつつ、無数の赤い目を光らせる大蛇へ向かって飛んだ。
洗われる犬ってカワイイですよね。猫も。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!