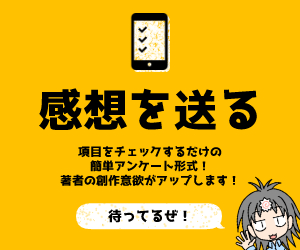「沖田ァ! 味玉を作れぃ!」
その日、沖田が耳にした信長の第一声は、そんな突拍子も無いものだった。
重く雲の垂れ込める季節。気圧による倦怠感と、ぼつぼつ屋根を叩く雨音が、全身に眠気を縫い付けるような朝だった。
こんな日は二度寝に限る。昼まで眠って、お腹が空いたらそうめんでも食べればいい。沖田は隣で眠る信長を、湿っぽい布団ごと抱きしめ、そう決め込んでいた。味玉作りを言い渡されたのはそのときだ。仰向けにスマホをいじる横顔を確認し、再び眠りに落ちようと、目を閉じたところだった。
飛び起きた信長が、ふすまを開けてキッチンへ向かうのを、沖田は恨めしく睨む。信長は爛々と目を輝かせていた。隅に置かれたスーパーの袋を拾い上げ、酒の缶を冷蔵庫へ詰め込んでいく。
「も~、ノッブ~。朝からお酒とかやめましょうよ~」
「安心せい! 飲むのは沖田の味玉ができてからじゃ!」
胸を張る信長を無視して、沖田は布団に包まろうとするが、こういうときの信長は普段より強引だ。布団を剥ぎ取り、起きろ起きろとほっぺたを引っ張る。
「はぁ、なんで朝から味玉なんですか……」
しぶしぶ起きた沖田が鍋を火にかける。信長が腹が減ったと言うので、ついでに塩鮭をグリルに放り込んだ。
「何時間か漬けんと味玉にならんからに決まっとるじゃろ」
信長は沖田に背を向け、玄関に束ねて置かれたダンボールをばらす。
「ちょ、せっかく縛ったのになんで解いちゃうんですか!」
「去年バーベキュー行ったとき、ついでに買ったスモークウッド、結局使っとらんじゃろ? 雨じゃし、暇じゃし、ベランダで燻製というのも乙なもんじゃろと思うてのう」
なるほど、燻製にするために朝から味玉をねだったのか。沖田はようやく合点がいった。一日二人でダラダラ寝るのも、それなりに良い休日の過ごし方だが、燻製作りというのも楽しいだろう。でもなにも、こんな雨の日にやることはないだろうに。沖田は少しばかり眉を寄せるが、信長はすっかりはしゃいでいる。
キッチンの収納から揚げ物のときに使う網を引っ張り出し、カッター、ガムテープ、割り箸を使って、燻製器を作る後姿は、完全に子供のそれだ。惰眠を奪われ、尖っていた沖田の口が、くにゃりと歪む。もう不満を言う気も失せ、「使わない分は縛っておいてくださいね」とだけ言って味玉作りに取りかかった。
卵の底に軽くヒビを入れ、沸騰したお湯に沈め、かき混ぜてタイマーをセットした。待つ間に、信長の手を止めさせ、並んで朝食をとる。
六分後、茹で上がった卵を水に浸け冷やす。全体にヒビを入れると、殻の上からでも、押せばぐにゃりと形を変えた。黄身がいい塩梅に半熟になっている証拠だ。
ビニール袋にキッチンペーパーと一緒に卵を入れて、めんつゆを流し込む。三時間もすればうっすら味がつくだろう。
「お、ちゃんと半熟じゃの。わしの方も準備バッチリじゃぞ」
袋の上から卵を軽く押した信長が、ほれ、と後ろを指差した。
手ごろなサイズのダンボールが無かったのか、二つのダンボールをガムテープで繋げた箱が目に入る。四隅に割り箸が通してあり、中に網を設置できるようになっていた。食材を網に乗せやすいよう、上部が開く作りをしている。不恰好ながら立派な燻製器だった。
「せっかく作ったのに卵だけって、ちょっともったいないですね」
「そうじゃのう。よし、ググって他に燻せるもんがないか探すのじゃ!」
「え、私がですか?」
「お前が言い出したんじゃろ。ほれ、早う、早う」
引きっ放しの布団に転がり、スマホで燻製について調べる。あーだこーだ言い合ううち、次第に脱線し、くだらない動画を見ていると、あっという間に昼になった。二人でそうめんをすすって、腹がこなれた頃、ゆるゆると燻製作りを開始する。
冷蔵庫から色の変わった卵を取り出し、キッチンペーパーで水分を拭き取る。乾かすためにそのまま皿に並べておき、金ザルにポテトチップスを半分ほど空ける。おつまみ用に常備してあるチーズも、アルミホイルに乗せ、一緒に燻すことにした。
空は相変わらず灰色で、無数の雫が、所狭しと並ぶ屋根を叩いている。ベランダのガラス戸を開けると、外の空気は冷たく、薄手の部屋着では少々肌寒い。信長は気にせず、Tシャツ短パン姿のままベランダに出る。沖田は一度引き返して、パーカーを羽織って戻り、ガラス戸のレールの手前に座った。
ベランダのコンクリートに、ポテチ入りの燻製器と、カセットコンロを置く。キャンプ用の折りたたみ椅子に腰掛けた信長が、火バサミで直方体のスモークウッドを摘まみ、コンロで炙る。固められた木粉の表面に火がつき、転々とした赤い光と共に、煙を発しだした。もうもうと立つ煙の量に、沖田は思わず顔を顰め、袖で顔を覆う。信長は平然と、床に置いたアルミホイルに燃えるスモークウッドを置き、上から燻製器をかぶせた。
「思ったよりすごい煙じゃのう」
「でもダンボール被せてると、そんなに気になりませんね」
沖田はチューハイの缶を、信長に手渡す。度数の低い、甘い、梅の酒を信長は呷る。液体が喉を流れる音がした。沖田も自分の手にある缶を開け、同じように呷る。しゅわしゅわという刺激が、すっぱい苦味と一緒に口に広がり、檸檬が香る。
「む。火、消えとるな」
信長が具合を見ようと持ち上げた箱の下、さっきまで元気に煙を吐いていた直方体が、すっかり大人しくなってしまっている。
「去年のだから湿気ちゃってるんですかね」
「ま、ガッツリ炙ればいけるじゃろ」
念入りに火をつけ、箱の中に戻す。箱の上部から、先ほどより多くの煙が漏れるようになった。
「こんな雨の日に、なんて思いましたけど、晴れてたらお隣の洗濯物まで燻すことになりそうですね」
「かえって良いじゃろ、苦情も来んじゃろうしな」
信長がカラカラと笑い、煙を吐く箱からポテチを一枚拾って口へ運んだ。「ずるいですよ」と、沖田も手を伸ばす。
口に入れた瞬間、燻香がぶわっと口内へ広がり、鼻へと抜けた。程よい塩気が、香りと相まって、舌の根を刺激する。無意識に酒の缶に手が伸び、一口、二口。
「お酒、冷やしておいて正解でしたね」
「そうじゃろ、そうじゃろ」
ポテチをザルから半分ほどティッシュに空ける。残りはチーズと一緒に箱に戻して、さらに燻すことにした。煙の香りのするポテチは、際限なく酒を進ませ、沖田も信長も早々に缶を空にしてしまう。
「次、何にします? ビールが良いですかね?」
「うーむ、ココはウイスキーじゃろ。ロックで持ってこい!」
「ダメですよ、ノッブは下戸なんですから。水割りにしといて下さい」
一口くらい良いじゃろうと不平を漏らす信長をおいて、沖田はキッチンに立った。小型のタンブラーに手を伸ばしかけ、ジョッキとショットグラスを手に取る。ジョッキには、氷と、底から四分の一までウイスキーを入れ、蛇口を捻ってなみなみと水を注ぐ。ショットグラスの方には、ウイスキーだけを半分程度注いで、信長の元へ戻った。
「ストレートは半分個ですからね。ちびちび飲んで下さいよ?」
「わかっておるわ~」
注いだ半分を飲み込んでから、ショットグラスを手渡す。まろやかな甘い味と香りが口内、鼻腔に広がり、胸が温まった。燻したポテチを放れば、燻香と酒の匂いが馴染む。
確かに合う。沖田は信長を見る。
信長はグラスに口をつけ、酒の表面を舐めるようにしては、ぷるぷると首を振っていた。口に広がる、ウイスキーの風味とアルコールに、身震いしているのだろう。黙って眺めていると、信長は、ストレート、ポテチ、水割りの順で飲み食いしては、目を細めていた。時折、ほう、と吐き出される息が、随分と熱を帯びている。
いつもより酔いだすのが早い。燻製が酒を進ませるせいなのだろうが、ゆるり雨を眺める横顔を見ていると、この陰鬱で気怠い空気に酔っているようにも思えた。立ち上がった信長が、ベランダの柵にもたれ、雨粒に手を伸ばすので、ますます確信めいてくる。
沖田は燻製器からポテチとチーズを取り出し皿に移す。煙の立たなくなったスモークウッドに火をつけ、乾かしておいた味玉、残りのポテチと一緒に、燻製器へ入れた。水割りを一口、きつね色に変わったチーズをつまむ。いつの間にか傍らにしゃがんでいた信長が、大きく口を開けていた。
「酔っぱらい」
口にチーズを放ると、信長はもちゃもちゃ頬張りながら、ショットグラスを片手に、また柵へもたれかかった。グラスの酒を舐め、満足気に微笑む。この世を手中に収めたかのような笑みだ。
見つめたまま、沖田もチーズを齧る。煙の香りが口に広がる。市販のスモークチーズと似ているが、より芳醇だった。水割りを喉に流す。ストレートのときに比べ香りが弱く、燻香とのバランスが悪い気がした。
「おきた、たまご」
もう少し、ウイスキーを足そうかと悩んだところへ、信長がふやけた声をかけてきた。沖田はポテチとチーズが乗った皿を、自分の膝に乗せる。そこへ、燻製器から出した卵を二つだけ移した。折りたたみ椅子に腰掛けた信長に、割り箸を手渡す。
「チーズみたいには色ついてませんね」
「パッと見わからんだけじゃろ。めんつゆに漬けたんじゃし」
信長が早速、卵に齧り付いたので、沖田も続く。半分ほど齧ると、中はとろとろの半熟。箸では黄身が零れ落ちそうだった。沖田は箸を置き、手掴みに切り替える。零す心配がなくなったところで、口の中の卵を改めて味わった。
燻香の香ばしさが、濃厚な卵の味と混ざり合い、独特の風味を醸している。どことなく、カラメルのかかったプリンを思わせた。漬け込みの時間が短かったため、酒に合わせるには、やや薄味に感じられるが、それでも合う。ウイスキーも良いが、日本酒やビールでも美味しいだろう。
信長を見ると、器用に箸で卵を摘んだまま、目を閉じ、じっくりと味と香りを楽しんでいる様子だった。黄身が流れ落ちないよう、そっと卵を皿に乗せ、ショットグラスに数ミリ残ったウイスキーを飲み干す。
こう美味そうに飲まれてはたまらない。沖田は立ち上がり、キッチンからウイスキーのボトルと、缶ビールを掴んで来た。信長のグラスを奪い、ウイスキーを注ぐ。卵を一齧り、ウイスキーを一口。もう一齧りして、今度はビールをがぶ飲みにする。爽快感のあるのどごしに、思わず、ため息がこぼれた。
「ずるいじゃろ~、わしも、わしも~」
ぱたぱたと手を振る信長に、缶ビールを手渡す。ほんのり赤らんだ細い首が、ビールを飲み込む様が見えた。は、ふ、と炭酸混じりの息を漏らす信長の瞼が、重たげな瞬きをする。事を終えた後のようだ。
首の後を、熱が這うように登る。あふれた唾液を水割りで流し、視線を遠くへ飛ばす。雨に濡れる、灰色の町並みが映る。
この長い雨が上がれば、じきに夏が来るだろう。そうしたら、この人の誕生日のお祝いをして、花火に、お祭りに、バーベキューと、またたくさん思い出を作ろう。今年こそは日差しに負けず、水着で並んでビーチにも立ちたい。いや、そうしなくては。
沖田の胸に、ある種の使命感のようなものが湧き上がる。
何故かはわからない。ただ、そうしないと、誰かに盗られてしまいそうな気がするのだ。
信長と二人、このアパートで暮らし始めてから、相当な時間を共に過ごした。しかし沖田は未だ、そのような想いに悩まされる。時が穏やかであるほど、それは黒く影を落とすから、この瞬間の胸のざらつきは、中々に苦いものがあった。
「なぁ~に、小難しい顔しとるんじゃ~?」
知らぬ間にシワの寄っていた沖田の眉間を、信長がつついた。
「安酒がこんなに美味くなっとるんじゃぞ? もっと景気よく飲まんか」
信長がビール缶の口を、沖田の唇に押し当て、傾ける。慌てて缶に手を添えたが、飲みきれなかったビールがこぼれて首を伝い、パーカーを濡らす。
「美味かろ?」
信長は目を細めて、ビールを一息に飲み干した。
酔っ払いめ。そう思った沖田だったが、言い返さなかったのは、確かに美味かったからだ。膝の皿を床に下ろし、沖田は信長を引き寄せる。脚の間に座らせて、煙の匂いのついた首根っこに歯を立てた。それなりに強く噛んだというのに、信長は喉を鳴らす猫のように笑っている。
「ずいぶん酔ってるんじゃないですか?」
「うはは、こう美味くては、是非もなかろう」
「昔は一滴も飲まなかったじゃないですか」
「お前が毎晩毎晩、ぶっはーゆうて飲むからじゃろ。わしじゃって、飲んでみとうなるわ」
だらりと沖田の胸にもたれかかった信長が、ぷうぷう紅い頬を膨らませて、顔を見上げる。
「そういうわけじゃから、はよう、おかわり」
「まだ水割りが残ってますよ」
脛をペチペチ叩いてくる信長に、ジョッキを手渡す。信長は沖田の胸を枕にしたまま、すっかり氷の溶けた水割りを呷った。
何の気なしに、ポテチを信長の口元に運ぶ。ガブリ指ごと食いつかれた。固い歯の感触と、唇の熱が、指先にじんと留まる。艶めかしさに、口の端が歪んだ。沖田にもたれた信長は、ますます脱力してお腹にジョッキを乗せ、鼻歌を歌い出す。
あめあめふれふれ。そんな童謡ならば情景にも合ったろうが、聞こえてくるのは、吹雪を思わせるアップテンポなヒットソング。なにもかもがミスマッチなのに、フンフンと鳴る振動が、上機嫌を伝播させる。
「ノッブもすっかり酒飲みですね」
「じゃから、おかわりをもてぃいうとるんじゃ~」
半笑いの指摘に、ふにゃふにゃの要求が返ってくる。脚から退こうともしないで無茶を言う。一応、後ろに倒れて目一杯、冷蔵庫に手を伸ばしてはみたが、かすりもしない。倒れた沖田の上で、ますます身体を伸ばした信長は、細い足を柵から突き出して、つま先で雨粒を蹴りだす。
その仕草がなぜか、沖田の胸を覆った雲を、緩やかに晴らしていった。
倒した身体を起こし、ショットグラスに零れそうなほどウイスキーを注いで、信長の胸の上にぶら下げる。
「せいぜい、今のうちに楽しんでおいてくださいよ。じきに飲めなくしてさしあげますから」
不安が消えた反動か、強い言葉が口をついて出た。
「そんときはお前も禁酒じゃぞ」
くっくっ、と笑う信長が、沖田を見上げる。酔っぱらいの癖に、言葉の意図を汲んだらしい。いつも沖田をからかうときの顔をしていた。ふい、と後ろめたさに視線を逸らすと、信長はその心中をさらに弄ぶかのように、沖田の持つグラスに口をつけた。一口すすり、ふ、と余韻を吐き出す。
「わしは構わんが、お前はコレ抜きでは辛いのではないか?」
再び沖田を見上げる信長が、舌舐めずりをしてみせた。その舌、その唇の紅が、腹の奥を疼かせる。沖田は、グラスの中身を一気に喉へ流した。
「私は平気です」
「飲み干しといてよう言う」
熱い息と一緒に宣言すると、下から呆れた声がした。確かに説得力はない。だが「平気なものは平気です」沖田は言い切る。
「私はもう、今日のこと、想い出すだけで酔えますとも」
グラスを置き、まっすぐ前を見た。照れ臭いやら、やましいやらで、信長の顔は見られなかった。
「そう飲んだわけでもないにのう」
囁きと共に、信長がしっとり微笑む。からかわれるだろうと思っていた沖田は、意外に思って視線を落とした。信長は、先ほどまでの沖田のように、眼前の雨空を向いている。紅く染まった頬は酒のせいなのか、はたまた。アルコールに焼けた胸が、さらに、じわり温まる。
それきり会話がなくなったが、居心地はむしろ良い。沖田は信長の身体を引き寄せて、腹に腕を回す。耳に頬を寄せれば、肌からは煙の匂いがした。
きっとこの先、ふとした拍子に今日を思い出すことが、幾度もあるだろう。互いの体温に、なんとなく、そんな予感を感じる。視線の先は、降り止まぬ雨だ。
身に染み入るすべてが、醒めない夢のよう、寄り添う二人をいつまでも酔わせた。
補足。
今作は「性別なし・結婚・妊娠・出産、すべて可能」という世界観で書いているので、沖田さんの「飲めなくしてさしあげます」発言は、「孕ませてあげます」という意図で言っています。(こんな補足なくても伝わるのが良い作品なんでしょうが…
支部に上げる時はちょっと改変せねばな。頑張ったのでオリジにリメイクもしたい。
世界観の詳細はこちらを参照してください。
ハイエナ設定解説
雨の日ってなんとなく燻製欲が高まる気がするなってのを沖ノブにしてみたお話。ファイナル本能寺の発表に浮かれて書いてみました。
燻製する話が書きたいだけで書き始めて、途中からなんか意味深にしたくなって無理くり足したのでチグハグ感出てるかも。冬コミめがけてのネーム作成もストップしちゃったしゲフゲフしとります。まぁ、まだまだ時間あるしイイヨネ!
ちなみに、ノッブのお誕生日は、7月19日説を採用しています。
酒と燻製の感覚を思い出しながら書いたので、次の週末にでも同じことして加筆修正を行いたいと思います。酒が飲みたくなる話を目指してー!(どこに向かっているのか…
我が家では、ダンボール製の燻製器と、スモークウッド・スモークチップを使って食材を燻しているので、沖ノブちゃんたちにもそうしてもらいましたが、お茶の葉っぱとフライパン、網、ボウルがあれば手軽に燻製を楽しめるので、燻製やってみたい!となった方はぜひトライしてみてください。
やり方を簡単に説明すると、以下のような感じです。
① 鉄製のフライパンにアルミホイルを敷く
② 紅茶や緑茶などのお茶っ葉を①に乗せる
③ 揚げ物用の金網など、燃えないモノで、かつ、煙を通すモノを②上に乗せる
④ ③の上に食材を載せる
⑤ ④の上に金属製のボウルを被せ、火をつける
⑥ 煙の出具合を見ながら火加減を調整し、お好みの時間燻製する
テフロン加工(フッ素樹脂加工)のフライパンは空焚きすると加工が溶ける場合があるので、鉄製のモノを使いましょう。もしくは土鍋。必ず換気扇を回して作るようにしてくださいね。
最後に、芸術点高めに出来た燻製味玉を披露したいと思います。沸騰してから6分煮るとこんな感じになります。
他の沖ノブ、ノブ沖作品はこちらへ。
沖ノブ、ノブ沖作品1話リンクまとめ
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!