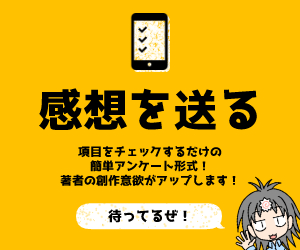ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第九話の続きになります。
第九話までのあらすじは以下のような感じです。
ダンジョンから戻ったフューリは調理班に今日取った獲物の調理法を説明し、ダンジョンに併設された温泉へと向かったが、ガーティレイにしっぽを掴まれるというトラブルに遭遇。オルナダを始めとしたみんなに救出され、ガーティレイはお仕置きされた。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下十話です。
【フューリ 九】
風呂から出た僕たちは、外で待機していたブゥプの案内で、山形に張られたタープテントへ向かった。タープの下には六角形状に大きな長テーブルが置かれ、真ん中で炭が焚かれていた。長テーブルはそれぞれ二人分の席が用意されていて、僕はオルナダ様と並んで座る。他の席は僕らから時計周りに、ティクトレアとケイシイ、シシィとヴィオレッタ、キャサリーヌとガーティレイ、ブゥプとルゥ、ユミエールとヒーゼリオフがそれぞれ並んで座った。
席につくと調理班の人々が術式が掘られた氷の皿とワインをテーブルに並べた。皿の上には何種類かのソースと、スライスされた内臓、何種類かの内臓を細かく切って煮て固めたようなゼリー、ペースト状にした内臓、キノコとソテーして冷やした内臓、薄いトースト数枚が乗っていた。僕がオルナダ様が生の内臓を気に入ったと言ったせいか、だいぶ内臓づくしな一皿になっている。どれも驚くほど美味しくて、高級感のある盛り付けが目にも楽しい。まるで王様の食事だ。本職の料理人の腕に僕はすっかり舌を巻いてしまった。
「このトゥルンとしたヤツ美味いな。どこの部位だ?」
「それは肝臓ですね。こっちのは心臓、舌、横隔膜で、この辺のは胃袋。これは脳で、このゼリーみたいなのはなんだか色々入ってて、ペーストのはたぶん肝臓、キノコのは腸です」
オルナダ様が肝臓を刺したフォークを振って僕を見たので、わかる範囲で答えた。
「イタチのは若干臭みがあったが、この牛はまったくないな。実に美味い」
「ちょっと、オル。確かにご飯は美味しいけど、そろそろわたくしたちにフューくんをちゃんと紹介してくれない?」
「そうよ! イラヴァールを出る前にちょこっと挨拶しただけじゃない! べ、別に話足りないってわけじゃないけど!」
「す、すみません、僕、失礼をしてしまったようで……」
ティクトレアとヒーゼリオフがオルナダ様に文句を言いだしたので、僕はなにか挨拶のときにするべきことをしていなかったのかと、慌てて立ち上がろうとした。オルナダ様は片手を上げ「お前は失礼なことなんてしてないから座ってろ」とそれを制した。
「こいつらはアレだ。俺の飼い犬ってことでお前に興味があるんだ。つまり「今晩空いてる?」の手合いだな。お前はまだそういうのダメだから止めろと言ったんだが……」
「なっ、ヒ、ヒーゼリオフ様はそんな興味なんて持ってないわよ!」
「わたくしもただオルに気に入られた子がどんな子なのか、お話してみたいだけよ?」
「そ、そうよ。あのそこそこな狩りの腕についてとか、そういう話を聞いてあげてもいいかなってだけなんだから!」
「ふーむ。疑わしいが、とりあえず信じよう。どうだ、フューリ、話してやれるか?」
「そ、そんな話で良ろしければいくらでも……」
「良かった。狩りはいつ頃から始めたの?」
「母が狩人でしたので、物心がついた頃には……」
「ふーん。二人共?」
「いえ、ヒューマーのほうの母が……」
僕は食事の手を止め、ティクトレアとヒーゼリオフの質問に答えた。途中でオルナダ様が食べながらで良いと言ったので、ゼリーやソテーを口に放り込んで、赤ワインを飲み干した。ゼリーのほうは香味野菜やハーブで煮込まれたスープのような味で、ソテーのほうは牛脂の旨味とスパイスが効いて、どちらもワインに合う味付けだった。一口食べてワインを煽ると、それぞれの味と香りが口の中で手を取り合い踊っているみたいだ。
「おい、魔族共。そんなクソ犬より、私に興味を持ったらどうだ? 三人まとめて今晩の相手をしてやっても良いぞ。そのヘタレと違って経験豊富だしな」
炭を挟んだ向かい側のテーブルから、ガーティレイが口を挟んできた。
魔族は他の種族と違い、生命機能の維持に魔力を必要とする。魔族にとっての食事は、他の生物や大気、大地から魔力を吸収することであり、食べ物を口に入れるのは単なる娯楽でしかない。そして最も効率の良い魔力吸収の手段は、他者との性的な交わりであるため、魔族は日に二、三度そうした行為に及ぶ。ガーティレイはその相手に立候補しているのだ。
「あ、お相手ならボクも空いてますよ~」
「わ、我も陛下方のお相手とあらば、喜んでこの身を捧げます……!」
ケイシイとヴィオレッタが便乗して手を上げる。僕もそれに倣うべきか迷ったけど、オルナダ様以外の人とそういうことをするのはまだ抵抗がある。
「ありがとう、嬉しいわ。でもあなた達は明日も調査があるし、今日は身体を休めて」
「そーよ。へばってたヤツは特にね」
迷っている間にティクトレアとヒーゼリオフは、申し出をきっぱりと断った。「私はへばってなどいない」と食い下がったガーティレイはキャサリーヌに頭を木剣で殴られた。
「はいはいは~い! ボクは調査とかあっりませんよ~!」
「あなたは遭難でもしたときのために取っておくわ」
「俺もティクトレアに賛成だ」
「ヒーゼリオフ様もね!」
「そこまで飢えてなくても、ボクは美味しいと思いますけどっ!?」
連続で断られたケイシイが悲痛な声で訴える。そのお断り三昧な光景がおかしいらしく、シシィは笑いを堪え、キャサリーヌはゲラゲラと笑ってワインの瓶を煽った。オルナダ様がガーティレイたちの申し出を断ってくれてホッとした僕も、グラスのワインを飲み干して、新しいのを注いだ。
「フューくんはお酒に強いのね。かなり飲んだのに顔色が全然変わらないわ」
「あぁ、その、僕、お酒で酔ったことはなくて、味が好きなだけなんです……。魔力の匂いには酔いますけど……」
「なにそれ? どういうこと?」
「聞いたまんまだ。濃い魔力を嗅がせると酔っ払う。最初の頃は俺の近くに来るだけで酔っ払ってたよな」
「あはは。たくさん吸い込めば、今でも酔いますよ」
「「なっ……! かっ……!」」
オルナダ様に笑いかけられて頭を掻くと、なぜかティクトレアとヒーゼリオフが二人揃って両手で顔を抑えて震えだした。二人はしばらく覆った顔をふるふると振り、やがて顔を上げ、口元を抑えて咳払いをした。なにが起きたのかとオルナダ様を見たけど、二人の行動に感心がないようで、もぐもぐと料理を頬張っていた。
そうこうするうちに次の料理が運ばれてくる。大鍋が炭の上に掛けられ、山盛りの丸パンを入れたザルがテーブルごとに置かれた。ブゥプが魔法でお玉を操作し、金属製の器に鍋の中身を取り分けてくれた。ブラウンソースで煮込まれた内臓だ。いろいろな部位が野菜と一緒に一口大にカットされている。元々用意されていたものに獲ってきた内蔵を足した料理なのか、鶏肉も入っていた。トマトがたっぷり入っているせいかオイリーなのに、どこかさっぱりとしていて食べやすい。
「はぁ~、良かったぁ。やっと普通の食べ物が来たぞ~」
ケイシイが嬉しそうに声を上げた。そういえばこの人だけは、結局心臓のスライスを食べなかったんだっけ。よく見ると皿の料理にも、ほとんど手を付けていない。それに気付いたガーティレイが「なんだ、貴様食わんのか? 私がもらってやっても良いぞ」と料理を横取りしようと立ち上がる。僕は止めようかと思ったけど、ケイシイが「ぜひお願いします」と言うので、上げた腰をまた下ろして「その、なんというか、すみません」と頭を下げた。
「この子が勝手に食わず嫌いしてるだけだから、気にしないで。基本的にビビりで、わがままで、失礼な子なの。わたくしも手を焼いているのよ」
「ボクは飼い犬の義務として、健康を維持するために、お腹を壊しそうなものは食べないようにしてるだけですよう」
「なら緑の野菜や人参もちゃんと食べなさいよ」
「それは我が家の家訓で、食べてはいけないことになっているので、仕方がないんですって」
「あっそ。そこへいくとフューくんは好き嫌いなさそうね?」
ケイシイのほうを向いてため息を吐いたティクトレアが、くるりと僕に笑顔を向けた。
「そ、そんなことはないですよ。僕も毒キノコなんかは苦手です」
「それは食べ物じゃないぞ、フューリ」
「やっぱり好き嫌いはないのね。オルが羨ましいわ。今日の活躍を見る限り、手がかからないだけじゃなく、頼りにもなりそうだもの。ケイシイとは大違いね」
「だからなぜボクを引き合いに?」
「ふはは。まぁ、そうだろうが、フューリとは得意分野が違うだろう? 比べられては、ケイシイが可哀想だぞ」
「そうよ! ケイシイとフューじゃ、全く比べ物にならないじゃない。フ、フューを褒めてるわけじゃないけどね!」
「そんなぁ、オル様もヒー様も、キっツイっすよ~」
ケイシイが情けない声を出すと、その場は笑いに包まれた。みんな親しげな様子なのでいつものことなのかもしれないが、 ケイシイとは飼い犬同士仲良くしたいと思っていた僕は、反感を買ってしまわないか心配だった。
「おい。活躍したのはそいつだけじゃないだろう。誰が盾になってやったと思っている? この私だぞ」
「寝ぼけているのか、オーガ。貴様の貢献度など、殿下の足元にも及ばないだろう」
僕ばかり褒められるのが気に入らないらしいガーティレイが口を挟むと、すかさずヴィオレッタがケンカになるようなことを言う。
「あれ? ヴィさん、いつからフューリを殿下呼びに?」
「初めからだ。我は陛下同様、殿下のこともお慕いしている」
「嘘つけ! 貴様、初めは『陛下の犬』とか呼んでたろうが! 手柄を立てられなかったから、おべっかで点数稼ぎをする気か?」
「またしても我を愚弄するか、オーガ! 言っておくが我の貢献度は、貴様などより遥かに高い!」
「またかお前ら、いい加減にしろ。みんな各々よくやってくれた」
ヴィオレッタはガーティレイに掴みかかりそうな勢いで立ち上がったが、オルナダ様の一言で大人しくまた席についた。
「そうだな。イタチの辺りまではアレだったが、役割がはっきりしてからは良かったぞ。ガーティレイはどんな攻撃も止めていたし、ヴィオレッタは確実に止めを刺した。ルゥの魔法と魔術の支援で多くの魔物を安全に仕留めることができたし、シシィマールは魔物の誘導や妨害の援護もさることながら、パーティをよくまとめてくれた。今日一日でなかなか良いパーティになったと言えるだろう。このまま行けば冒険者パーティランクでCからCプラスぐらいのパーティに成長できるかもしれないな」
「うおおお! マジっすか!」
「ほ、ほんとでしゅかあああ!?」
オルナダ様の言葉にシシィとルゥが目を輝かせた。冒険者ランクはSからFまであって、Cはちょうど真ん中のランクにあたる。冒険者はDランクくらいがなんとか一本で食べていけるレベルで、Cならそれなりの暮らしができるレベルらしいので、夢が膨らむのだろう。ガーティレイは不服らしく「私がいるのだからもっと高いはずだ!」と文句を付けていた。ヴィオレッタはなにも言わなかったけど、ガーティレイと同じようにどこか不満げな顔をしているように見える。僕は冒険者のことはわからないけど、オルナダ様がシシィのすごいところをちゃんと褒めてくれたことが嬉しかった。
「キャサリーヌ。お前からもなにか言うことはないか? 今後のこいつらの育成方針とか」
「とにかく戦闘力の高い魔物と戦わせるのみですわ。明日は全滅の危険があるレベルのが出てくれると良いですわね」
オルナダ様が思い出したように声をかけると、キャサリーヌは煮込み料理の次に運ばれてきた横隔膜のステーキをぱくつきながら、天気の話でもするように物騒なことを言ったので、僕はおかわりしたステーキを喉につまらせた。
「ふーむ。確かに今日はそれほど強いのには出くわさなかったな」
「まったくだな。オルナダのダンジョンというから多少は期待していたが、口ほどにもなかったぞ」
「そうねぇ。Eランク程度のパーティでもなんとかなりそうなのばかりだったものね。浅層階は低ランカーでも挑めるレベルのほうが経営側としてはありがたいけど」
「そういえば最初のイタチも、数さえいなきゃ私でもソロでなんとかなりそうだったもんなぁ」
「ルゥもあのイタチなら一人で倒せそうな気がしましゅ」
みんな口々に今日出くわした魔物の手応えのなさを語り合い、明日はもっと強いのと戦いたいと頷きあった。シシィやルゥまでもがだ。今日だって危ない場面がなかったわけじゃないのに、さらなる危険を求めるなんて、みんななにを考えているんだろう。
「ボクは強い魔物と戦うなんてごめんっすけどね~。やっぱ調査班なんかに志願する人は変わってるんだなぁ~」
「だからあなたはいつまでたってもヘナチョコなのよ」
「またまたぁ、そこがボクのチャームポイントじゃないっすか」
ケイシイはまるで興味がなさそうなコメントをして、ティクトレアに睨まれた。それでも気にせず油で揚げた芋とチーズを頬張っている。どうやらこの場でまともなのは、僕とケイシイだけらしい。僕はケイシイに倣って、強力な魔物を如何にして倒すかという話で盛り上がるみんなを横目に、食事に集中した。芋は揚げ油に牛脂を混ぜているのか、旨味が強く塩が効いていて、いくらでもワインが飲めそうな味だった。
やがてみんながお腹を擦りだし、僕とガーティレイが余った芋を競い合って平らげた後、食事会はお開きとなった。僕らはブゥプに連れられて、就寝用テントエリアへと向かう。就寝エリアは東西南北に別れていて、僕らが案内されたのは、ダンジョンの入口に近い南側だった。オーガが五人くらいは寝れそうなドーム型のテントがいくつも立っている。テントは種族ごとに別れて使うそうで、僕はガーティレイやルゥと一緒にならなくてよかったと胸を撫で下ろした。
「じゃ、俺は帰るが、明日以降もしっかりな」
「なに!? 貴様、帰るのか!?」
「当たり前だろう? これから〝食事〟をしなけりゃいけないしな」
「それなら私が相手をしてやっても良いと言っているだろう」
「お断りだと言ったはずだ。お前はなぜいつもそうしつこいんだ」
「貴様がいつも断るからだろうが!」
ガーティレイは僕が言おうとしたことを全部先に言ってしまった。お陰で僕はお断りされずにすんだけど、耳としっぽは、しゅんと下がってしまう。オルナダ様が調査期間中ずっといてくれるわけもないのだけど、今晩くらいは泊まって、僕と過ごしてくれるんじゃないかと期待していただけに寂しい気持ちが湧く。
「おい、そうしょぼくれるな。調査が終わったら、たっぷり可愛がってやる」
オルナダ様は僕の様子に気付くと、浮かび上がって頭を撫でてくれた。その身体を抱きかかえて、鼻に鼻を寄せて名残を惜しむ。人前なのでそうしたのだけど、オルナダ様はニヤリと笑い、躊躇なく僕の首を抱き寄せて、唇を重ねる。ガーティレイが「あーーーーー!!」と耳障りな声をあげた。
オルナダ様は、ひんやりとした柔らかさを、しっかりと感じ取れるくらいの時間、唇を押し当てて、やがて僕の上唇にぬるりとした熱い感触を残して、僕の腕から飛び降りた。しっぽがひとりでに振れて、首やらほっぺたやら、いろんなところがぽぽっとなった。
「んじゃ、しっかりな」
オルナダ様はティクトレア、ヒーゼリオフと一緒に手を振って、すっとその場から姿を消した。「おい、私にも……」と掴みかかろうとしていたガーティレイの手が虚しく空を切り、「ちょっっっ、ボクを置いてかないでくださいよぉぉぉ!!」とケイシイが地団駄を踏むように飛び跳ねた。
こうして僕らの調査初日は終了した。
僕はキャサリーヌと一緒の混血者用のテントで、空いている毛皮の上に横になり、今日一日を振り返る。随分たくさんの人と知り合えた日だった。捕食者シリーズの影響下にあるルゥ以外、誰も僕を怖がらないし、普通に話もしてくれる。もう故郷にいた頃とは違うんだなと思うと、ムズムズと口元が緩んだ。ガーティレイにしっぽを掴まれるという最悪な経験をするハメにもなったけど、これについては今後、人里でも気を抜かないようにすればなんとかなるだろう。ガーティレイ以外のみんなとは、シシィと仲良くなれたみたいに仲良くなれたら嬉しい。そんなことを思いながら、僕は眠りについた。
第十一話公開しました。
モツは鍋で食べたいところですが、舞台が西洋ファンタジー風異世界なので、オードブル料理はフレンチの内臓料理でググって出てきた、中目黒にあるBistro Tatsumiさんのメニューを参考に描写してます。いつか食べに行ってみたいですね。
モツ煮込みはサイゼにあるヤツのイメージ。牛脂で揚げたポテトはマックのポテトみたいな味になるそうです。
あとジビエの生食はリアルでは超危険なのでやめましょう。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!