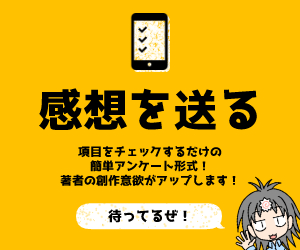ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編になりますが、知らなくても読めるようにしているので、気軽に読んでやってください。
なろう系を目指して書いてみたので、書き上がったらなろうにも上げてみようかと思っています。5千~1万字くらい書き溜まったら随時公開していきます。また、上げた分はちょこちょこ修正します。
ハイエナ??という方はこちらを参照してください。
ハイエナ設定解説
あらすじは以下のような感じです。
人狼とヒューマー(人間)の混血であるフューリは、なぜか魔王の名を持つ魔族オルナダに『飼い犬』という職を与えられる。フューリはあり得ないほどの厚遇にビビりながらも、オルナダの飼い犬に相応しいスキルを身に着けようと日々努力することに。しかしオルナダはフューリのパラメーターがとんでもない数値であることに気がついて……。
以下本編です。
【フューリ 一】
魔族に飼われる者はすべてを手にする。
この格言でいうところの〝すべて〟が、なにを指すのかはわからない。だけどこうして幸せな朝を迎えるたび、そう言われるのも納得だとしみじみ思う。
僕はワインレッドのシーツに、艶やかな長い黒髪を散らして二度寝を貪る飼い主をそっと抱きしめて、その甘い匂いを胸いっぱいに吸い込んだ。香りに酔いしれるように、お尻の後ろでしっぽが振れる。できればずーっと一日中、この小さな身体を抱きしめていたい。
だけど魔術式が施された、シーツと同じ色のカーテンは、とっくの昔にひとりでに左右に開いて、寝室に陽の光を取り入れていた。壁や天井を装飾している金が輝きを増して、もう起床時間なのだということがわかる。
こういった魔術で動く物品、通称『魔術器』は、とても便利な道具なのだけど、時間になったら自動で開くカーテンは作らないでほしかったなと、僕は少しだけ眉を寄せた。
「オルナダ様、そろそろ起きる時間ですよ」
名残惜しさを堪えて、飼い主のオルナダ様こと、オルナダルファウルス・ギルオウーフ・レ・ギルオウーフ・ヴェンダリオン・ラウ・ガルダーフに、小さく声をかけてみた。
オルナダ様は、うにゃうにゃと何事かを呟いて、僕の胸に額を押し当て、再び布団に潜ってしまう。この仕草、豊潤な魔力の甘い香り、小さな頭、頭の横でぴくぴくと動く尖った耳、ふすーっと長く吐き出される息、なにもかもが愛しい。布団をかけ直して、また一緒に眠りたくなる。
眠りたくなるが、そういう訳にもいかない。
僕はオルナダ様の枕に、ぐっと魔力を流した。覚醒の術式が施された枕は、まばゆい白色の光を放ち、たちまちにオルナダ様から眠気を取り去った。オルナダ様はむくりと起き上がり、裸のまま天蓋付きのベッドから飛び降りる。両手を広げると、一瞬で白い肌の上に、いつも着ている、片側に紅いマントがついた黒い制服が現れた。
この現象は転移魔法という高度な魔法によるものらしい。便利なのだろうけど、着替えを手伝いたい僕としては、使用を控えてもらえると嬉しい魔法の一つだ。
魔法で着替えられてしまうと、この後やることは腰まである長い髪を襟から引き出すことくらい。それもうなじに手をやって払えば済むことなので、手を出すスキもなくオルナダ様が自分でやってしまう。その間、僕ができることといえば、さらさらと指先を滑っていく髪に見惚れることくらいだ。
為す術もなく、しっぽを左右に揺らしていると、オルナダ様が振り返り、ぱっちりした猫目の奥の宝石みたいな紅い瞳に僕を写す。
「この俺からまどろみ奪うとは、いい度胸をしているな、フューリ」
「す、すみません……。今日は絶対寝坊はダメって、昨日ユミエールさんに言われていたので……」
オルナダ様がエルフをも凌ぐ美しい顔に不服の表情を浮かべた。いつもと変わらない落ち着いたトーンの声色から察するに、怒っているわけじゃないようだけど、僕は一応、弁解を述べた。オルナダ様は「む。そうか、今日はアレの日か」と予定を思い出したように呟く。理解が得られて安心した僕は、いまだに裸でいる自分が急に恥ずかしくなり、昨夜脱ぎ捨てた青い制服を拾って、こそこそと部屋の隅へ移動した。
「おい、モタモタしてると、ユミエールにどやされるぞ」
それはオルナダ様だけですよね? と思いつつ振り返ると、そこに寝室はなく、代わりに、赤い石柱の立ち並ぶ開けた空間があった。
また転移魔法が使われたらしい。
わっとなって自分の身体を見た。幸い、服は着せられていた。唯一の自慢の青い毛並みのしっぽも、ブラシをかけたようにサラサラだった。
僕はきゅっとなった喉をさすりつつ、辺りを見回す。どうやら東西に伸びた廊下にいるようだ。
二、三十メイタルはあるだろう石柱の上にアーチに支えられた天井があり、高い位置にある明りとりの窓から陽の光が差し込んでいる。柱や壁には装飾とも術式ともつかない模様の彫刻が施されて、どことなく教会を思わせる神秘的な雰囲気の場所だ。
西側の扉が開いていて、奥ではエルフやドワーフが数名集まり何事か話し合っていた。みんな緑の制服だ。一人がオルナダ様に気付くと、緑服たちは「陛下」と声を上げ、一斉にこちらに駆け寄ってくる。その声に釣られた人たちも続々と集まって、僕らの周りには、あっという間に人垣ができた。
「散れ散れ、集まるな、仕事に戻れ」
オルナダ様は煩そうに手を振るが、命令が聞こえていないのか、廊下の両脇に並び、胸に手を当て恭しく頭を下げた。
僕はとんでもない人に飼われている。改めてそう実感した。
オルナダ様はこの魔術研究学院都市『イラヴァール・ディアッグ』の国王のような存在なのだ。
本人は「何百年か前にこの地を開拓しただけで、統治もしてないし王なんかじゃない」と否定しているが、市内でも市外でもこのような扱いなので、実質国王であると言っても過言じゃない。
「ったく、敬意なんか衝突しない程度に払えば十分だろうに」
ぶつぶつと文句を言ったオルナダ様は、ポケットに手を突っ込んで歩きだした。
オルナダ様は僕のみぞおち辺りまでしか身長がないとは思えない、大きなオーラを纏って堂々と廊下を歩いていく。僕はそのあとを、背中を丸めて着いていった。
故郷ではいつも隠れて生活していたから、人目に晒されるのはどうにも落ち着かない。緊張でしゃっくりが出そうになる。でもこの人に飼われた以上は、こんなことにも慣れないといけないだろう。わかってはいるのだけど、首筋からたらたらと冷や汗が流れ出た。
「ところでフューリ。お前は正式に俺の犬になったわけだが、なにか変化はあったか? 困り事があるようなら聞くぞ」
前を歩くオルナダ様がふわりと浮き上がり、僕の顔を覗き込んだ。
ドキリとしつつ「こんなに良くしていただいているのに、困ったことなんて」と両腕を差し出すと、腕の中に収まったオルナダ様が「本当に? なにも?」と目を丸くするので、僕はもう一度しっかりと思い返してみることにした。
『飼い犬』は、飼い主の庇護下で教育を受けていれば良いという、意味のわからない待遇の職だ。衣食住は保障されるし、教育だって学都であるイラヴァールでならどんなことだって学べるだろう。そんな職に採用されて困ることなんてあるはずがない。
強いて挙げるとするなら、
「そうですね……。飼い主がオルナダ様なので、そのぅ、変な興味を持たれることが多い、かも……。ってことくらいです……」
ぽそぽそ小声で答えると、オルナダ様は先を促すように首をかしげる。
「えぇと、なんというか、会う人会う人みんなに「今晩空いてる?」みたいなことを……」
はっきりとは言いづらく、言葉を濁した。
厚遇されている飼い犬だけど、一般的には〝飼い主のお気に入り〟という身分を与えられた奴隷と認識されている。そしてオルナダ様は、魔族の中でも特に好色と評される人物。そんな人に気に入られるということはつまり……。
「ぶはは。俺を虜にした技があるとでも思うんだろうな。モテて当然だ」
僕にそんな技なんかあるはずもないのだけど、まぁ、そういうことだ。
気恥ずかしくて、頭の上の耳がへにゃりとなる。オルナダ様はそれが愉快らしい。上機嫌に笑って「わかったわかった、なんとかしてやるから」と頭をなでてくれた。
無意識にしっぽがバタついた。僕はそれをなるべく人目に晒さないよう、緑服がずらりと並ぶ廊下を足早に駆け抜けた。
複雑な模様の重たそうなドアの前まで来ると、オルナダ様は僕の腕から飛び降りた。無事に送り届けたので一礼してその場を離れようとすると「お前も来い」と言われたので、後について中に入る。
室内は廊下と同様に天井が高いけど、シンプルな白い壁に囲まれて、落ち着いた雰囲気だった。縦に長い大きな窓が並び、室内はとても明るい。中央には大きく長いテーブルがあり、左右には別室へのドアが付いていた。
中に誰かいるのだろう、右側のドアは開け放たれていて、中から人の匂いがした。変わった足音がこちらに近づいてくる。
「よっっっうこそ、お越しくださいました、陛下ぁ!! お待ち申し上げておりましたっっっ!!」
右手の奥の部屋から、相当な大声を上げる緑服の黒うさぎが、ぴょこぴょこと駆け寄ってきた。
人兎という人口の多い種族だけど、間近で見るのは初めてだ。魔力の匂い『魔香』に混じって、青野菜の匂いがする。大きさは僕の膝より下くらいで、山で獲るうさぎとは違い、顔も手足も短く、とてもかわいい。思わず顔が綻んでしまい、僕は慌てて目を背けた。
ブゥプという名前らしい人兎は、僕らを中央のテーブルへ案内してくれた。制服に付いた徽章の数を見ると、結構偉い人なんじゃないかという気がする。
「くるぁ!! チンタラすんなボケェっっっ!! 早う陛下と殿下にお食事お出しせんかいっっっ!! 閣下ぁ、陛下がお越しくださりましたーーーっっっ!!」
僕らが席に着くと、ブゥプは大きな足で床を踏み鳴らし、ドスの効いた声で奥にいた他の緑服たちを急き立てたかと思ったら、出てきたときと同じように慌ただしく別室へ消えた。
小さくてふわふわの愛くるしい見た目からは想像もつかない罵声が飛び出したことに、僕はそこそこ大きなショックを受けた。許されるなら、もう帰りたい。それがダメならどこかに身を隠したい。そんな気分だった。
少しでも落ち着きたくて、斜め前に座ったオルナダ様が運ばれてきた軽食を口に運ぶのを眺めていると、ブゥプがオルナダ様と同じ黒い制服のエルフを連れて戻ってきた。ユミエールだ。
肩甲骨辺りまで伸ばした金髪に、緑色の目、尖り耳。顔も美形で、肌は白い。やや丸目な点以外は、まさにエルフといった風貌をしている。魔香の濃さから、かなりの量の魔力を持っていることが伺えた。たぶんオルナダ様の右腕のような存在なんだろう。閣下と呼ばれていたのは初耳だけど、何度かオルナダ様が仕事を丸投げしているところを見たことがある。
優秀かつ偉い人と予想してるけど、オルナダ様に対して遠慮がないところがあるので、僕は少しだけこの人を警戒していた。
ユミエールは優しく微笑み、穏やかな声で僕らに挨拶をすると、ブゥプと並んで僕の正面に座った。
「早速だけど今日の式典の段取りを説明をするから、食べながら聞いてね。よろしくブゥプ」
「おっっっほん、では、僭越ながら本職がご説明させていただきまっっっす!! ファンファーレが終わりましたら、本職からご出座の声をかけさせていただきますので、陛下、殿下の順で広場前のテラスに……」
「ホントにコレ必要か? 別にやらなくても……」
「あら。オルったら、また必要性の説明聞きたいの?」
「いや、もういい」
「あなたたち魔族は、その気になれば指先ひとつで大陸を吹き飛ばせるほどの大魔法を行使できるでしょ? その中でもあなたは特に……」
「……スピーチ原稿は?」
「はいコレ。よろしくね」
ユミエールが手をかざすと空中に緑色の文字が浮かび、オルナダ様の前に移動した。浮いた文字を眺めながら、二人は修正案を話し合い始めた。
こんな感じでユミエールはいつも、言葉巧みにオルナダ様に仕事をさせる。僕の想像する王様と家臣のやり取りとは余りにかけ離れているので、こういう光景を見るたび、複雑な思いが湧いた。
「殿下の分はこちらになります。素案になりますので、これから手を加えて殿下の人となりが伝わる内容に修正を……」
もやもやした気持ちでサンドウィッチをかじっていると、ブゥプが僕の目の前に、文字の書かれた紙を差し出した。思わずサンドウィッチを咥えたまま、両手で受け取る。そこで初めて違和感に気がついた。
殿下って誰のこと?
殿下というのは王様の親族に使う敬称だったはずだ。僕はてっきりオルナダ様の親族が別室に控えているのかと思っていた。でもこのスピーチ原稿と思われる紙が、僕に渡されるということは……。
どっと全身から汗が吹き出た。僕は恐る恐る「すみません」と左手を上げた。
「えっと、あの……。デ、デンカ……?」
この混乱をどう伝えればいいか、わからなかった。
結果、なにを言いたいのかわからない言葉が出たけど、ユミエールは僕の言いたいことを察したらしい。オルナダ様に「なにも説明してないの?」と呆れ顔を向けた。
「ええとね、フューリちゃん。飼い犬は一般的には奴隷と変わらないと思われているし、実際そういう扱いをする飼い主も多いけど、本来、飼い犬というのは慈善活動のためにある制度なの。簡単に言うなら、恵まれない子を引き取って育てましょうって仕組みね。だから正式に飼い犬になった今、あなたはオルの養子みたいな立場にあるわけ。殿下と呼ばれて当然なの」
「そのっっっ通りでございます!! 故に大々的に就任式典を執り行い、存在を全市民に知らしめるのでっっっす!!」
ユミエールは丁寧に説明し、ブゥプは大げさに両手を広げた。
「ま、お互い悪さをしないように、顔を覚えさせるってことだ。市民がお前に危害を加えても、お前が市民に加えても、面倒なことになるからな。管理責任があるから俺も罰を受けるし」
「ちなみに魔族が治めてる魔導圏では、自分より弱い相手に危害を加えた場合、罪が重くなるから気をつけて。フューリちゃんは元々戦闘力が高い上に、権力も獲得しちゃったから、かなり重くなるはずだしね。まぁ、刑罰は基本、何割かの資産没収だから、やってくれてもいいけど。オルのお財布からいくらか没収できたら予算が潤うし」
「絶対するなよ。これ以上、遊ぶ金が減るのは困る」
オルナダ様とユミエールは、カラカラと笑う。
養子うんぬん以降は、まるで初耳だった。
とんでもない人に飼われている自覚はあったけど、これはあまりにとんでもなさすぎる。
僕は劣等とされる種族のヒューマーの町で育ち、雑種だということで冷遇されてきた人間なのに、それがいきなり殿下だなんて、からかわれているとしか思えない。
オルナダ様が今にもニヤニヤと笑いだすのを期待して、じっと顔を見つめてみるけど「そのうち慣れる。俺も陛下呼びに慣れたしな」と肩を竦めるだけだったので、僕の身体は緊張でこわばり、しゃっくりを出し始めた。
「もっと言うと、この式典はフューリちゃんが市民の脅威にならないと示すことを目的にしてるの。可能なら、魔王の犬に選ばれたという僥倖の恩恵を、ふんだんにこの都市に還元してくれそうな人物だって印象を与えたいから、少し自分のことを話してもらえる? 生い立ちとか、夢とか、特技とか。それを元に原稿に手を加えるから」
「キョウ、イ……?」
理解が追いつかなくて、耳についた単語をオウム返しにした。
「大昔の話だけど、不幸な生い立ちの飼い犬を持った魔族が、その子の生まれた国を地図から消したことがあってね。「よくも私の犬をいじめたなー」って。魔族って犬を持つと溺愛する傾向にあるから」
「おい。俺がそんな飼い主バカになると思ってるのか?」
「思ってるから、ならないって宣言してもらうの。気を悪くしないでほしいけど、フューリちゃんはひと目で混血だってわかる見た目でしょ? 不安な者がいてもおかしくないと思わない?」
ユミエールは両の手のひらを天井に向けた。
混血は雑種とも呼ばれ、それだけで侮蔑の対象だった。それに魔導圏以外の地域では、雑種は奴隷の身分である場合が多いらしい。
二重の不遇に遭って、強い恨みを持っている。
それが僕に対する市民の印象だと、ユミエールは言っているのだ。
オルナダ様は口をへの字に歪める。
「えぇと、僕、ヒューマー圏出身で、人狼との混血なので、いじめに来る人は少なくて、どちらかというと怖がられていたというか……。あと奴隷でなく、狩人でしたので……」
「なんとぉっっっ!? 殿下をいじめた不届き者が少数いたとっっっ!?」
少しは場の空気が和らぐかと思って言った言葉に、ブゥプが鼻息を荒くする。
「ブゥプ、オルみたいにならないで」
「俺みたいってなんだ。なにも言ってないだろ」
「原稿では静かに暮らしてたって感じにしましょ。狩人のところは伏せたほうがいいかもね」
「無視か、おい」
オルナダ様がむくれるのも気にせず、ユミエールは淡々と話を続けた。
「じゃあ次ね、これからしたいことはあるの?」
正直、特にない。なにか良い答えを返せないかと考えるけど、オルナダ様に飼われたという、とてつもない幸運と幸福を、田舎の狩人に過ぎない僕が還元するなんてできるだろうか? いや、できるはずがない。最大種の竜を百万体狩って納めても足りないだろう。相手を見て言ってほしい。
なんだか「末代までかかっても返し切れない借金がある」と言われたような気持ちになり、耳としっぽを垂らした。苦し紛れに、逆にどう答えるべきなのかと尋ねてみる。ユミエールは通常、飼い犬になった者は、長年の夢を叶えようとするケースが多いと教えてくれたけど、それでどうして〝借金〟を返せるのか検討もつかないけど、どの道そんなもの、僕にはなかった。
僕はずっと、成人して親元を追い出されたら、どこかの森の奥深くで、孤独に苛まれて死ぬんだと思っていた。夢と言えるような願望は、町のヒューマーたちと同じような、普通の暮らしをすることくらい。だからオルナダ様に飼われた時点で、最上位互換と言える形で叶ってしまったのだ。
「僕、やっぱり、これ以上望むことなんて、思いつきそうもないです……」
「殿下は無欲であられますな、素ん晴らしいっっっ!!」
「うーん、それじゃあ、オルの犬としてどうありたい?」
「いっぱいお役に立てるようになりたいです! 身の回りのお世話をするとか、乗り物代わりになるとか、もしものときの盾になるとか……」
「そういうのはいらんと言ってるだろう。自分の世話は自分でするものだ」
これは答えられると、即座に早口に言葉を連ねたけど、本人にきっぱり拒否されてしまった。
一瞬ピンと立った耳が、再び萎れた。
「まぁ、その方向でいきましょうか。狩人だったなら、猟兵として防衛に尽力、辺りが妥当でしょうね。戦闘力の高さを示すことにもなっちゃうけど」
「は、はい……。じゃあそれで……」
「では直ちに修正をっっっ!! 陛下の飼い犬に相応しい、勇猛なイメージを抱かせるスピーチにしてみせますよっっっ!!」
僕が同意するやいなや、ブゥプはものすごい勢いで、さっきの紙に書き込みを加えていった。
兵士なんてできればしたくないけど、どの道イラヴァールの市民は全員、有事の際に兵士として動けるよう訓練される。兵士として尽力なんて、単に市民としての義務を果たすというだけだ。拒む理由はない。
ただ〝オルナダ様に相応しい〟という言葉が引っかかった。
一般の市民と同じ義務を果たすだけで、オルナダ様に相応しいなんて言えるだろうか? とてもそんな風には思えない。
「あの、オルナダ様……。僕、オルナダ様の犬としてやっておくべきこととか、ありますか?」
ユミエールとブゥプが式典の準備のために席を立ったスキに、小声で尋ねてみた。
「ないぞ。健康で、しっぽブンブンしてれば、それでいい」
即答されてしまった。
喜べばいいのか、困ればいいのかわからず、僕は酸っぱい顔になる。
「ヤツらの言ったことなら気にしなくていいぞ。そりゃあ、俺の犬なんだから、周りは立派な人間であってほしいとか思うだろうが、別のなにかになろうとすることなんかない。どうしても気になるなら、お前自身がやりたいことで還元することだ」
オルナダ様は頬杖をついて、ふっと目を細めた。
やっぱりステキな人だな、と胸が暖かくなる。穏やかな気持ちになると同時に、いつかはこの人の役に立てる人間になって、この莫大な借金、もとい、恩をいくらかでも返せるようにならなくてはと思った。
程なくして僕らは、飾紐やらサッシュやら、制服にごてごてと、いろんな装飾品を付けられ、中央広場に面したテラスに案内された。
高い位置にあるテラスからは、イラヴァールの街がよく見えた。赤茶色の石造りの建物が、遥か遠くの城壁まで所狭しと並んでいる。まだ朝食の時間のためか、乾いた風からパンの香りがした。眼下の広場では、式典を見にやってきた市民たちがざわめいていていた。朝市の三倍は混み合っている印象だ。
今からここでスピーチするかと思うと目眩がする。しっぽもいつの間にか、脚の間に潜り込んできていた。
式典が始まり、オルナダ様は集まった市民たちの声援を浴びて、簡単な挨拶をした。僕も続いてスピーチをしたはずだけど、しゃっくりが出始めた辺りから記憶がなく、気付くとふらふらとオルナダ様の後ろに下がっていた。もう一度前に出たオルナダ様は、締め括りの演説をしている。
僕は無事にスピーチできたのだろうかと、それとなく控えている緑服たちの顔色を窺う。みんなどことなく残念そうな顔をしているように見えたけど、ブゥプは目が合うと、親指を立ててくれた。
「……というわけで、見ての通り社交的なタイプじゃないがよろしく頼む。慣れるまでは、なるべくそっとしておいてやってほしい。特に、一発やろうなんて誘いをかけたりしないように。コイツはついこの間、俺で初体験を済ませたばかりで、まだまだ初々しいからな」
どっと笑いが起き、僕の顔面はボッと火の付いたようになる。
こんな大勢の前で、なにを言ってくれちゃってるんですか! と叫ぶのを堪え、膝を抱えて身体をぎゅうぎゅうに縮めた。
僕は本当にとんでもない人に飼われている。それはもう、いろいろな意味で。
第二話公開しました。
10万字は超えると思うので、気長にお付き合いいただければ幸いです。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!