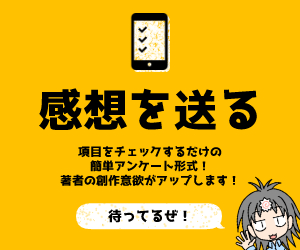ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第十七話の続きになります。
第十七話までのあらすじは以下のような感じです。
ランピャンでの活動が本格始動して一週間。フューリはオルナダに会えないことで、ほかのメンバーたちはサバイバル訓練で疲弊していた。飢えに苦しむメンバーたちを挑発するケイシイと言い合った流れで、パーティ対抗のお料理対決が催されることになった。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下十八話です。
【フューリ 十三】
「ぐぬぬ、あのひょろエルフめ……。おい、クソ犬! 勝算はあるのだろうな?」
ケイシイの態度が気に食わないらしいガーティレイがずいっと僕の顔を覗き込む。もちろんそんなもの、あるはずがない。こちらはまともな食材がないし、シェフもいない。そもそも圧倒的に不利なのだ。でもそれを言ったら夕飯を完成させることすら難しくなってしまうだろう。
「えーと……、じゃあとりあえず、食材の確認からですね……。みんな手持ちの食材は?」
「私は魚と猪」
「ルゥは捕まえた鳥と、野菜がありましゅ」
「我は米と野菜と少々」
「どれもこれもチンケだな。私を見習え、虎だぞ虎」
「僕はまだ狩りに出てなくて、干し野菜と調味料と、あとは小麦粉くらいしかないから、これでそれなりに料理っぽいものだと……」
僕は言葉を切って考えられるだけのレシピを頭の中に思い描く。ティクトレアとヒーゼリオフ、それにキャサリーヌも一緒に食べることになるだろうから、なるべく全部の材料を使って量を増やしたい。かといって一番大きいガーティレイの虎は、きっと臭みが強くて普通に調理したのでは、みんなが食べられるような味にはならないだろう。
「とりあえず、シシィは止めと解体をお願い。なに作るかは味見してから考える。鳥は処理し終わったら僕の盾で煮ちゃって」
「了解」
シシィに肉の処理を任せ、僕は自分のキャンプ地から捨ててあった植物を拾ってきて、ルゥとヴィオレッタに渡した。
「ルゥちゃんとヴィさんは、この植物の根っこをできるだけたくさんと、鳥の卵を採ってきてもらえますか? あとは食べられる野草とかキノコとかを見つけたらそれも」
「わかりましたでしゅ!」
「承知いたしました! 全霊を持って採取いたします!」
ヴィオレッタの持っている米を使えばお粥が作れる。ルゥの鳥のスープで炊いて、卵でかさ増しすれば、ひとり一、二杯は食べられるだろう。あとは猪と虎。猪はどうにでもできるけど、虎はどうしたものか。そもそも虎はまだ食べたことがないし、どうすれば美味しく食べられるのか検討もつかない。
僕はうんうんと頭を捻る。捻りつつ、どうしてこんなことに頭を使わなくてはいけないのかと、不満が湧く。訓練の合間のわずかな自由時間くらい、オルナダ様との思い出に浸っていたいのに。
「ほい、フューリ。猪と虎の切れ端」
「あ、ありがと……」
シシィから解毒皿に乗せた生肉を受け取って口に放り込む。
「んー……。虎、臭いな……。あと固い……」
「だね。脂も少ない……」
「重要なのはデカさだろう。それにこれまで私が獲った肉の中では格段に上手いぞ」
横から生肉を奪い取ったガーティレイが誇らしげに鼻を鳴らすが、これをティクトレアやヒーゼリオフが食べて美味しく感じられるレベルの料理にするのは至難の業だろう。
「わたくしも味見して良いかしら?」
「ヒー様ももらうわ」
僕が頭を抱えていると、ティクトレアとヒーゼリオフが生肉をつまみにやってきた。二人は猪を食べてふむふむと頷き、虎を食べて顔を歪ませる。やっぱり臭みが気になるのだろう。
「「まさかコレは料理に使わないわよね?」」
「食材が少ないので、できれば使いたいんですけど……、この感じだとグリルで食べるのは難があるでしょうし、煮込んで臭いを飛ばすのは時間がかかるので、どうしたものかと……」
「「時間でなんとかなるものなの?」」
正直に考えを打ち明けると、二人は揃って驚愕の表情を浮かべる。
「お酒と一緒に煮ると臭いが飛ぶのでたぶん……。ただどのくらい煮たら食べられるレベルになるかはわかりませんし、少なくとも一、二時間はかかるかと」
「うーん、ネットワークにもそういう調理法の記録はあるから、きっと可能なんでしょうけど……」
「確かに……。じゃあ好きなだけ煮てみたら? 特に時間制限は設けてないんだし。コレが食べられるようになるのか興味があるわ」
二人はこめかみに指を当てると、表情を和らげて煮込みをOKしてくれた。
それならと、僕らは早速虎を煮込みにかかる。味見をして臭みの強かった脂部分を取り除き、骨ごとぶつ切りにする。そしてガーティレイを説得して、持っていた酒を残らず出させ、肉と猪の膝から下の部分を一緒に盾に入れて、ガンガンに焚いた火にかけた。温度が上がるにつれ、盾からは猛烈な獣臭が立ち上り始め、みんな顔を顰める。
「ぐおおお……、わ、私の酒が……」
「……なぁ、すでに口に入れるのが憚られる臭いがしてるけど、これ大丈夫か?」
「それだけ臭いが飛んでるってことだから大丈夫だよ。これが許容できる程度に落ち着いたらほかの食材と調味料を足してスープにしよう」
「クソ犬、貴様! これで不味かったら地獄を見せてやるぞ!」
ガーティレイが涙目で僕の胸ぐらを掴む。訓練中の唯一の楽しみだったものが、悪臭の発生源に成り果ててしまったのだから無理もない。でも元はといえばこの人が虎なんか獲るからいけないのだ。僕は「丸焼きよりは確実にマシですよ」と適当にあしらって、次のメニューを考える。
「猪は内臓も肉も野菜と一緒にソテーにしちゃおうか。ガーさん、向こうの川に岩があるので、まな板みたいに平らに切って持ってきてもらえますか? ガーさんが両手で作った輪くらいの大きさで良いので」
「なぜ私がそんなことをせねばならんのだ」
「あ、岩をキレイに切るとか無理な感じっすか? じゃあ私が行ってきますけど」
「んなっ……、バカを言うな! 出来ぬわけがなかろうが! 少し待っていろ、すぐにデカイ板を持ってきてやる!」
「はーい、よろしくでーす」
作業を振った途端に反発したガーティレイだったが、シシィが口を挟むとすぐに斧を担いで川の方角へ歩いていった。本当に人の扱いが上手い。ガーティレイへの作業分担については悩ましいところがあったけど、シシィがいてくれたらなんとかなりそうな気がする。
ほどなくしてガーティレイは岩板を抱えて戻り、数分後に野菜や卵、キノコを抱えたルゥとヴィオレッタも戻ってきた。岩板は意外にも理想的な大きさと形状で、十分調理に使えそうだったし、ルゥが五感と魔法をフル活用してくれたのか、頼んだ食材は予想の倍の量があった。
「三人ともありがとうございます。これなら思っていたより美味しく作れそうです!」
「光栄でございます、殿下。次のご指示は?」
「じゃあヴィさんは最近作ってた器を使って、水と小麦粉を練り合わせてもらえますか?」
「ルゥはなにをしたらいいでしゅか?」
「しばらく食材を冷やしておきたいんですけど、氷のドームとかって作れますか? それと、この草の根っこの皮を剥いてみじん切りにしてほしいです」
「私は?」
「シシィは内臓の下処理をして、終わったら魚から骨と皮を外して塩を振ってスライムシートに包んで、ルゥちゃんの氷に入れといて」
「キリキリ働けよ、貴様ら」
「ガーさんには僕のナイフとスライムボードをお貸しするので、虎をミンチにしましょう」
調理の目処がついた僕は、テンポ良くみんなに作業を割り振った。ガーティレイは岩板を頼んだとき同様の反応をしたけど、またシシィが上手いこと言い包めてくれた。虎の臭いも意外と早く飛ばすことができたし、とりあえず食べられるレベルのものにはなりそうだ。
木々の向こう、ケイシイたちのキャンプ地からはすでに出来上がった料理の良い香りと、歓談の声が上がって、ティクトレアとヒーゼリオフの匂いもする。きっと審査中なんだろう。匂いからすると、トマトのパスタに、ハム、チーズ、温野菜、牛のグリルといった感じの料理が出ていそうだ。
こちらの食材ではとても作れないメニューだなと思いつつ、僕はみんなに細かく指示を出していく。ヴィオレッタにはパン生地のように纏まるまで練るということを。ルゥには草の葉の部分とほかの野菜をどう切るかを。ガーティレイには虎の味見をしてからどの部位をミンチにするかを伝える。シシィには特に言うことはなかったので、猪をソテー用と、ガーティレイにミンチにしてもらう用に分けるように頼んだ。
「あとはガーさんがミンチにした猪と虎を、僕の干し野菜と調味料、ルゥちゃんが細かくしてくれた、にんにく、生姜、野菜と混ぜて、ヴィさんが作ってくれた生地を薄く伸ばして包んで焼きます。歓迎会のときにみんなで食べたのは茹でてあったけど、たぶん焼くのでも作れると思うから」
「あぁ、あれかぁ。確かに焼いても美味そうだよな。餃子って言ったっけ?」
「殿下がお求めになった植物は生姜でありましたか。にんにくは形状でわかりましたが、生姜がこんな姿をしていたとは」
「イラヴァールだと生姜は粉末でしゅもんね」
「うむ、あれは美味かったな。よし、さっさと焼け」
餃子と聞いた途端、ガーティレイが火にかけていた岩板をべしべしと叩く。まだ材料を混ぜてもいないのに気が早い。「まずはミンチを作りましょう」と伝えて、シシィが切り分けてくれた猪の脂の多い部分と、煮えた虎の肉を渡して切り方を教えた。なにを作るかわかってやる気が出たのか、特に反発はされなかった。
餃子の具作りを三人に任せ、シシィにはソテーを担当してもらう。岩版に猪の網脂や腹脂を乗せて脂を出し、続いて心臓や舌など臭みの少ない臓器と肉、刻んだにんにくとその葉を加え、焦げ付かないよう時々木の枝で突き回しながら焼くように頼んだ。焼けた肉と脂の香りが食欲をそそる。
やがてルゥが野菜を切り終えたのでお粥と虎のスープを任せた。鳥を煮ている盾にキノコを入れて、鳥から骨を外し、肉を細かく裂いてもらう。それが終わったら米を入れて、十分に煮えたら塩で味付けをすれば完成だ。虎のほうは、たっぷりの生姜と、野菜、外皮を剥いた生姜の葉、キノコを入れて煮る。ランピャンの市場で買ったごまの油と、穀物を発酵させた液体調味料、独特の香りのする複数のスパイスを渡して、野菜が煮えたら指定した分量で入れるようにと頼む。これでスープも僕の手を離れた。
あとはヴィオレッタとガーティレイが餃子を包み終わるのを待とう。意外にも包むのはガーティレイのほうが上手いのか「もっと薄く伸ばせ! ヒダはこうだ!」とヴィオレッタに怒鳴っている。土器の出来栄えを見るにヴィオレッタも手先は器用そうだから、このまま二人に任せて大丈夫だろう。
なんだか肩の荷が下りて気が抜けたせいか、胸に重たさが戻ってきた。少しでも肺を軽くしたくて、僕は長く息を吐き出す。
「順調そうじゃない」
座り込んで肩を落としていると、ケイシイたちのキャンプから戻ってきたヒーゼリオフが、僕に声をかけた。
「あぁ、はい。陛下が時間をかけていいと言ってくれたおかげです」
「べ、別に大したことじゃないわ。も、元々制限時間なんてなかったんだしね」
「それでも言われなければ気づかなかったので、ありがたいです。そうだ。僕らのメニューは技術交流会で教わったランピャン料理を参考にしているので、たぶん馴染みのある味になっていると思いますよ」
「そう。ヒー様はランピャン料理にはうるさいわよ? 審査に響くかもね」
「あはは、お手柔らかにお願いします」
ヒーゼリオフがニヤリと笑って軽口を叩くので、僕も笑顔を作って軽い返事をした。するとヒーゼリオフはきゅっと眉毛を寄せ、疑うような目をして僕の顔をまじまじと見た。
「アンタ、やっぱりしょげてるでしょ?」
「い、いえ、そんなことは……」
すぐさま否定したけど、ヒーゼリオフは表情を変えない。じっと僕を睨むように見つめ続ける。なんだか責められているような気がして、僕は首を縮めた。
「……ま、別に良いけど。アンタはどうせオルの犬だしね」
しばらくするとヒーゼリオフは興味を失ったのか、ふいっと顔を背けてその場から消えてしまった。たぶんどこかへ転移したんだろう。僕は深く追求されずにすんで、ほっとしたのと同時に、ずんと頭が重たくなった。
僕はオルナダ様の飼い犬なのだ。
具体的にどうすれば良いのかはわからないけど、それに相応しい人間でいなければオルナダ様の顔に泥を塗ってしまうことになる。調子を崩している場合ではないのだ。未だ恩恵を還元できるようなやりたいことも見つけられない不甲斐ない身なのだから、せめて言われたことくらいは完璧にこなさなくては面目が立たない。
なのに今の僕は、それらを全部投げ出してしまいたくなっている。海を泳いででもイラヴァールへ帰って、オルナダ様の小さな身体を抱き締めて昏々と眠りたい。そんなことばかり考えている。
僕はなんて情けないヤツなんだろう。視界が徐々にぐにゃぐにゃと歪んでくる。
「おい、クソ犬! 包み終わったぞ、早く焼かぬか!」
離れた場所に座り込んでいた僕に向かって、ガーティレイが怒鳴り声を上げた。あとは岩版に乗せて焼くだけなんだから、そのくらい自分でやってほしい。割増された疲労感に潰されないよう、膝に手をついて立ち上がり、岩版の横へと足を運んだ。
シシィに頼んでいた猪のソテーは、しっかり火が通って表面がカリッとしていた。スペースを空けるため、ソテーを左側に寄せて餃子を並べていく。寄せたソテーには、ポケットから取り出したランピャン地方特有の豆と唐辛子を発酵させた調味料で味付けをする。脂っこいし、内臓の臭みが多少あるので、濃い目にしておこう。シシィに多目の分量を伝える。あとは冷やしていた魚を一口大に削ぎきって、各料理の味見をして、味を調節したら完成だ。
ガーティレイが適当な大きさに切った丸太を椅子とテーブルの代わりにして、ルゥが審査員の三人を呼びに行く。その間にヴィオレッタが自作の土器に料理を盛り付け、僕とシシィで並べた。
メニューは、虎と猪の焼き餃子、猪のソテー内臓入りランピャン風、生姜の効いた虎スープ、川魚の鱠、鳥と卵とキノコのお粥。品数は多いけど、ガーティレイや僕が食べる量を考えると、やっぱり少なめになってしまった。それでもここ最近のみんなの食事を思えば、豪勢な夕食と言える。
「はあぁぁぁ、久しぶりのまともな飯だぁぁぁ」
「全部美味しそうでしゅ~~~」
「殿下、我は、感激であります!」
戻ってきたルゥとシシイが仲良く並んでぴょんぴょんと跳ね、ヴィオレッタは信じられない量の涙を流す。最初はちょっぴり、厄介なことになったなぁと思っていたけど、こんなに喜んでもらえるなら頭を悩ませた甲斐があったというものだろう。ちなみにガーティレイはみんながテーブルに着く前から餃子に手を伸ばしたので、やってきたキャサリーヌに二、三発ひっぱたかれ、今は地面に転がっている。
「え~……、うっそぉ~ん……」
「ほ〜ら見なさい。ちゃんと食事になってるでしょ」
続いてやってきたティクトレアとケイシイが、並んだ料理を見て声を上げた。ケイシイは僕らの料理が想像以上にまともだったからか、あんぐりと口を開けて「いや、これ、なんかズルしてないっすか?」疑いの目を向けてくる。
「フューくんがそんなことするわけないでしょう。あなたとは違うの。ということで、賭けはわたくしの勝ちよ。今月はお小遣いなし!」
「ぐふぅ……! こ、こんな勝ち確の賭けに負けるとは……」
お小遣いなし宣言を受けたケイシイは、パタリとその場に倒れてしまった。飼い主が毎日様子を見に来てくれているだけでありがたいのに、賭けで小遣いを巻き上げようとするなんて強欲な人だ。僕なんてもう二週間はまともにオルナダ様に会えてなくて「もう幻覚でも良いから目の前に現れてください」なんて祈る日々を送っているというのに。
呆れたやら羨ましいやらで、僕は星の瞬く夜空を仰いで、今日何度目かの祈りを捧げた。すると、今日に限って願いが届いたのか、僕のすぐ後ろから幻臭が香ってきた。オルナダ様の魔力と肌と保湿に使う樹脂製のオイルが混ざった、ほのかな樹木っぽさを感じさせる甘い香りが、はっきりと感じられる。
「ほう。サバイバル飯と聞いていたが、ずいぶんまともな食事を作ったな」
まさか、幻聴まで……? ひょっとして振り向いたら姿が見えるんじゃないか? 恐る恐る首を回すと、オルナダ様が見慣れた制服姿で立っている。
今日のお星さまは随分と上機嫌だ。もとい、僕の頭は本格的におかしくなったらしい。
これで触ることもできたら完璧だなと、そっと幻覚の脇の下に手を入れて、抱き上げてみる。軽く、温かく、柔らかい、まさしくオルナダ様の感触だった。お腹に顔を埋めて、香りを肺いっぱいに吸い込むと「どうした? くすぐったいぞ?」と頭をくしゃくしゃ撫でてくれる。なんてよくできた幻覚だ。今すぐ寝床へ連れ帰って抱いて眠りたい。食事を抜いても構わない。だけどティクトレアとヒーゼリオフを招いた食事会で、審査の結果も聞かずに姿を消すのは流石に不味い。
食事が終わるまでこの幻覚は消えずにいてくれるだろうか。不安な気持ちで腕の中のオルナダ様を見た。うん? と首をかしげるしぐさに胸がきゅっとなる。
「なんだオルナダ。飯をたかりに来たのか? 餃子はやらんぞ」
「ケチくさいヤツだな、ガーティレイ。味見くらい良いだろう?」
のしのしとこちらにやってきたガーティレイが幻覚に話しかけた。
「…………? あの、この幻覚……、ガーさんにも、見えるんですか……?」
「あぁん? なにが幻覚だ。ここにいるだろうが」
「いるぞ」
オルナダ様が僕の顔の前でひらひらと手を振る。幻覚じゃなかったのか。僕は驚きのあまり飛び上がりそうになる。
「すすす、すみません。勝手に抱き上げてしまって……。その、本物だとは思わなくて……」
「構わんさ。慣れたものだ」
「あはは。えぇと、今日はどうしてこちらに?」
「ヒーゼが「フューが枯れかけの植物みたいに萎びてるからなんとかしなさい!」って言うから見に来たんだが、全然元気そうだな」
「そ、そんなことないです! オルナダ様を抱っこするまではすごく萎びてました! それはもう、砂漠で死んだトカゲみたいにカラッカラでしたよ!」
「それじゃ〝萎びてる〟じゃなくて、〝干からびてる〟だろう。ところでどこへ向かってるんだ?」
「はい?」
言われて僕は両足を揃え、ズザザ―――ッと地面を抉る。知らないうちに全力疾走していたみたいだ。みんなのいたキャンプ地からは随分と離れてしまった。匂いを確認すると、どうやら僕は街の方向へ向かっていたようだ。
「えぇと……、街の迎賓館にヒーゼリオフ陛下が用意してくれた部屋があるので、たぶんそこに向かってたと思います……」
無意識とはいえ自分の行動が恥ずかしくて、思わず唇を噛みしめる。これじゃまるで人攫いだ。きっとBPがついたに違いない。
「なんだフューリ。お前、俺をベッドに連れ込もうとしてたのか?」
ひょっとして怖がらせてしまったんじゃないかと気を揉んだけど、オルナダ様はニタニタと笑って僕の鎖骨の辺りをつついた。怖がっても怒ってもいないようだけど、浅ましい想いを見透かされて顔から湯気が出そうになる。
「あの、違うんですよ? そういうことではなくて、久しぶりにお会いできたので、二人きりでお話したかったというだけで……」
「そうなのか? 俺はまだ〝食事〟をしてないんだが、そういうことなら先に風呂屋にでも……」
「い、いえ! そういうことなら僕を食べちゃってください!」
「わはは。そうか、ならそうするか」
オルナダ様はケタケタと楽しそうに笑った。僕はほわほわとした気持ちになって、再び街を目指して走る。ここのところずっと調子が悪くて、全身が沼に浸かっているみたいに重かったのに、今は羽根が生えたみたいに軽い。身体の脇を通り抜けていく夜風がびゅんびゅんと小気味の良い音を立て、落ち葉や木の実の匂いを運んで、目の前に広がる空には満天の星が瞬いている。
ここはこんなに綺麗な場所だったかな? はてと首を傾げつつ、オルナダ様をしっかりと抱き直して、僕は星の降るような夜を駆け抜けた。
「猪のソテー内臓入りランピャン風」は豆板醤で味付けしたもつ焼き、「川魚の鱠」はお刺身です。
この回のために中華料理とか肉食獣の味とか無駄に色々調べました。大したことはわかりませんでしたが、ライオンよりは虎のほうが美味しいらしいですよ。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!