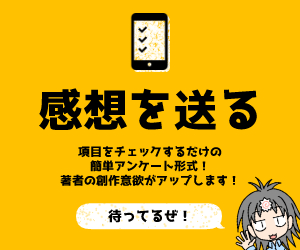ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第一話の続きになります。
第一話までのあらすじは以下のような感じです。
魔族のオルナダに『飼い犬』という職を与えられた主人公フューリは、オルナダに連れられて大々的な就任式典でスピーチをさせられる。そしてフューリはそれに伴う打ち合わせの中で、オルナダの飼い犬であるということの重大さを思い知らされたのだった。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下二話です。
【フューリ 二】
夕方。僕は狩った熊で作った着ぐるみで全身を覆い隠し、七五番訓練場にやってきていた。
岩石砂漠と高山に隣接したイラヴァールは、日中かなり気温が上がる。もう日が傾いているとはいえ、まだかなり暑い。でも、あんな大暴露の後では、顔を晒して歩くことは憚られた。僕は汗だくになって、匂いを頼りに同郷の友人、シシィマール・ヴォンルーフこと、シシィの姿を探した。
主に剣術の訓練を行う七五訓練場は、石を削って平らにした広いスペースがあるだけの場所なので、簡単に見つけることができた。風に巻き上げられた土埃の向こう、僕と同じ青い制服を着た短い金髪のヒューマーが、他のヒューマーやエルフたちと一緒に備品庫に木剣を返しに歩いていた。
ヒューマーの割りに色白なシシィだが、汗と埃に塗れたせいか、今は顔が赤茶色っぽい。
「シシィ! このあと時間ある?」
「うぇっ、誰!? フューリ!? なんだよ、犬の次は熊になったのか?」
人熊に変装した僕にシシィマールことシシィは、青い目を丸くして驚いたけど、すぐに整った顔に呆れた表情を作ってみせた。
普段なら楽しいシシィの軽口だけど、今は笑っている余裕はない。周囲の人々に、アレが今朝大恥をかいたオルナダ様の飼い犬だと気付かれないか、気が気でなかった。
「と、とにかく来て!」
「お、おい、よせって! 下手すりゃ捕まる!」
僕は強引にシシィを担ぎ上げ、寮のある北側地区を目指して走り出した。他人から見たら犯罪に見えるかもしれない。シシィはそれを心配したようで、僕に担がれている間ずっと「誘拐じゃないのでご心配なくー、このほうが早いってだけですー」と周囲にアピールしてくれた。
イラヴァールの北側は標高の高い山々が脈々と連なっていた。溶けた雪が川になり麓へ流れるので、南側の砂漠地帯とは異なり、豊かな森が広がっている。動物や魔物の数も段違いに多い。
そのため北側地区は、度々、魔物の侵入に見舞われて、危険地域に指定されている。応戦可能な戦闘力のある人間でないと、立ち入りが許されないくらいらしい。僕は飼い犬としてオルナダ様と同じ寮に住む必要があったので、自動的にこの地区に身を置くことになったけど、狩りは得意だし、森にも慣れているから、それほど危険には感じなかった。多少魔物には遭遇するけど、むしろ食材が豊富でありがたいという印象だ。
「お前、今日は泊めるか、送るかしろよ。さすがにここの夜道はヤバいし。ちなみに私は泊まり希望。食事付きで」
「わかってるよ。シチューでいい?」
僕はシシィを抱えたまま、寮の門を素通りして、ぐるりと塀を回り、丸太を組んだ真新しい小屋のドアを開けた。
「初めてくるけど、なんだここ? 調理場?」
「調理場兼、解体場兼、貯蔵庫かな。寮で猪を解体していいかオルナダ様に聞いたら、魔法でバーッって建ててくれたんだ」
僕は着ぐるみを脱ぎながら、石窯を覗くシシィを振り返る。
シシィは火床の上にぶら下げた真新しい鍋や香辛料、調理台にかかる使い込まれたナイフ、木製のダイニングテーブルなんかをしげしげと眺めて「こんなのポンと作ってもらえるなんて、マジでチート職だな、飼い犬」とうんうん頷いた。物珍しそうに部屋全体を眺めて、ドアというドアを開けて中を覗く。
「へー。二階もあるのか。てか屋根裏?」
「そっちは燻製室だよ。火床とか石窯から出た煙が屋根裏に回るようになってるんだ」
「ほーう。こっちの青い部屋は?」
「解体室。全面スライム製だから、獲物から出た血を全部吸ってくれて掃除が楽なんだ」
「うへぇ。こういう形状固定スライム製品って買ったらいくらするんだろうな」
「こっちはバスルームか。でかいスライムもらったな。四角いのが洗身用だよな? 服ごと浸かっていいか?」
「いいよ。オーガ用サイズだから気をつけてね。僕も次、浸かるよ」
シシィは「わーってるって」と、木の床の上に置かれた、一メイタル四方よりやや小さいくらいの直方体状スライムに頭を突っ込んだ。
スライムは物体の全体を体内に取り込むと、その物体を消化する性質がある。そのため、掃除、洗濯、風呂、トイレなどなど、様々な用途で使われるけど、誤って全身をスライムの中に入れたりすると、大怪我をしてしまう。風呂として使う場合は、小さければ不便だし、大きければ危険なのだ。
ちなみに通常の楕円球型のスライムは、ヒューマーでも無理なく買える値段だけど、形を加工したスライムはなかなか高価だったりする。
「危ないつっても、やっぱでかいと早く汚れ落とせて便利だよな。広いし良い家もらったじゃん」
「えへへ。地下はもっとすごいよ。来て」
シシィと交代でスライムに浸かり、亜麻のローブに着替えた僕は、もらった小屋を褒められてすっかり気を良くしていた。床板を持ち上げて地下への階段を降り、手招きでシシィを呼ぶ。
地下は地上の小屋よりも広く、階段の先は、右側が開けた空間になっていて、食料を満載した棚を並べている。石積みの壁の石すべてに、幾何学模様をした温度を下げる術式が掘られていて、この空間はとても涼しい。
左側には普通サイズのドアが二つと、僕の頭ほどのサイズのドアが一つある。普通のドアの先の部屋は、一つはここよりも温度が低くて寒い冷蔵室。内蔵を抜いた獲物を熟成させるのに良い。もう一つは身体が凍りつくくらい寒い冷凍室。こちらは食べ切れない肉を長期保存できるらしい。まだ使っていないのでほとんど空だ。小さいドアの向こうは、僕の頭がすっぽり入るくらいの空間になっていて、その空間いっぱいに手のひらサイズの氷が作られている。獲った獲物を冷やすときに便利だ。
僕が説明するとシシィは「チートじゃねぇか!」と頭を抱えた。気持ちはわかる。僕も故郷とのあまりの差に呆然とした。
魔術器はヒューマーの町にはほぼ存在しない。魔術器を起動するには一定量の魔力を流し込む必要があるので、魔力を持つ者がほとんどいないヒューマーは、たとえ手に入れたとしても使うことができない。それに、あらゆることが魔法で回っているこの世界では、魔力のない者は良い職につけないため、スライム製品より更に高価な魔術器には手が届かないのだ。
「でもシシィの家は魔術器あるって言ってたよね?」
「まぁあるにはあったけど、注入式の着火ロッドとか、製氷箱くらいのもんで、こんな全自吸式のは見るのも初めてだぞ。つーか、こんなの魔導圏でも持ってるヤツほとんどいないんじゃないか?」
全自吸式は魔力を注入したときだけに起動する注入式とは違って、空間に存在する魔力を自分で吸収して術式に流すので、一度起動すると半永久的に動作する。魔力を吸収する術式の構築には、かなり高度な技術が必要なため、シシィの言う通り、あまり普及してはいないらしい。ここをくれたとき、オルナダ様が得意げに語っていた。
「こういう魔力注入しなくても動く魔術器こそ、ヒューマーに使わせてほしいもんだよなぁ。あー、魔術ももっと勉強しないと……」
シシィはバリバリと頭を掻いた。
僕はそれを横目に冷蔵室に入り、昨日作ったシチューが入った寸胴鍋を両手で持ち、市場から取ってきたパンと、乾燥させていた肉を魔法で胸の前辺りに浮かせて戻った。その間にシシィは気を取り直したようで、食料棚を物色していた。
「お。これ氷室に隠してたミードか? こっちはハムだろ?」
「うん。ここをもらったときに全部取ってきたんだ。どっちも一年モノかな。食べる?」
「当然!」
シシィにミードの瓶とパンを持ってもらい、僕は鍋と肉とハムを持って調理場に移動した。
火床に薪を積んでおくよう頼んで、屋根裏に肉を吊るし、戻って魔法で火を付け、スタンドをセットし鍋を置いた。木製のカップにミードを注ぎ、乾杯する。
「ふはー。相変わらず、上等な白ワインって言われても信じられるレベル!」
ぐっとカップを呷ったシシィは、心底美味そうに息を吐いて、どっかり椅子に腰を下ろした。
まぁまぁ強い酒なので、僕は「ゆっくり飲んでよ?」と忠告し、ハムを切り出しにかかる。かつては山を駆ける猪のスネだった部分を握り、茶色く光る肉の塊をテーブルに乗せた。人差し指の先に魔力を集中させ、半月型の長い爪を作って、表面をすぱっと切り落とし、現れた赤く艶めく肉を薄く削ぎ落とす。自分のは生のまま、シシィのは軽く火で炙ってから皿に盛り付け、オレーアの油をかける。いつの間に持ち出したのか、シシィがチーズの塊を差し出して、これも食べたいと目で訴えてきたので、適当に切って皿の端に乗せた。
「それ便利だよなぁ。ナイフいらずで」
「魔装って言うんだって。結構レアな技能だってオルナダ様が言ってたよ」
「へぇ! 強いのか?」
「違うんじゃないかなぁ。魔力消費が激しすぎるって話だったし。手入れがいらないのは便利だけど」
「なんだ……。パーティの火力が強まったかと思ったのに……」
シシィは貴族の生まれなのに、僕と組んで冒険者になることが夢だった。家から金品を盗んでまでイラヴァールにやってきたところを見るに、相当本気の夢なんだろう。イラヴァールである程度の能力を身に着けたら、どこか近くの国の冒険者ギルトに登録して旅に出るつもりらしい。故郷にいた頃はよく「一緒に世界を回ろうぜ!」と目を輝かせていた。
僕は冒険者という職にはあまり魅力を感じないし、ヒューマーのシシィがそんな危険な職に就くのは、あまり賛成できなかった。もしもシシィが本当にイラヴァールを出るようなことになったら、オルナダ様が許してくれる範囲で同行するつもりでいるけど、正直、思い留まってくれることを祈っていた。
「で? なんかあったのか?」
背中を向けて鹿肉と野菜がゴロゴロ入ったブラウンシチューをかき混ぜていると、シシィはもちゃもちゃとハムを噛み締めながら、ここへ連れてきた理由を尋ねてくれた。
僕は申し訳ない気持ちになりつつ、振り返り、首の後ろを掻いた。
「えぇと、なんて言ったらいいのかな。今朝の式典の準備のとき、恩恵を還元しなきゃとか、色々衝撃的な話を聞いて……」
「は? オル様の犬に選ばれた恩恵なんて、どうやったって返せなくね?」
「だ、だよね! 僕もう、莫大な借金を抱えちゃった気分で……」
「オル様はなんて?」
「それがオルナダ様は、元気で幸せならそれで良いって……。あとは、どうしても還元したいなら自分のやりたいことでしなさいとか……」
「かーちゃんかよ」
「いや、母さんは厳しかったから、僕的には神様が実在したらこんな感じかなって思ったけど……」
「言い過ぎだろ。あー、いや、でもあの人、魔王だし、こんな家ポンとくれるんだもんな……」
シシィは人差し指で眉間をぐいぐい押した。
「もしシシィだったらどうする? 還元ってどうしたらいい?」
「んー、自分のしたいことでってことだし、私ならまず冒険者ランクを上げるかな。オル様がスポンサーならヒューマー向けの全自吸式装備も買えるだろうし、かなり高ランクも夢じゃないはず。んで、私と同じように冒険者したいヒューマーに還元してくかな。ノウハウを伝えたり、装備の研究開発に投資したり、それから……」
答えを用意していたかのように語るシシィに、僕は目を丸くした。
なるほど還元というのはそういうことをいうのかと納得する一方、どうしてそんなことを考えつくのか不思議でたまらなかった。頭の出来が違うのかなと少し落ち込んだ。
「でもさ。本人がそう言ってくれてんなら気にしなくて良いんじゃねーの? ……ってその言い方だと、遊んで暮らせる感じだけど、まさかこれから訓練とか全部免除なのか?」
「……あ、ううん。必須の訓練は全部受けないとダメ。でも働くのは禁止で、今までみたくお役所から仕事もらえなくなるみたい。オルナダ様からお給料もらうのに、他人の仕事盗ったらダメって……」
「なるほどなぁ。でもオル様は働かせる気ないんだろ? てか給料っていくら?」
「基本給プラス二百万マールって言ってたけど……。イラヴァールの通貨ってデールなのに変だよね?」
僕は眉をハの字にして首を縮めた。
イラヴァールはどういうわけか、銅貨一枚さえ見かけない不思議な都市だった。物を買うときも値札はきちんとついているのに、お店の人はお客がなにも渡さずに商品を持っていっても「まいどあり」と笑顔で見送るのだ。真似をして何度か物を獲ったことがあるけど、怒られたことは一度もない。
もう数ヶ月ここにいるけど、未だに僕はお金の仕組みが理解できずにいた。
そんな僕に呆れたのか、シシィはしばらくの間、あんぐりと口を開け、それからテーブルに突っ伏した。「働かずに月二百って、チートだろぉぉぉ……」と身体を震わせる。
「はぁ~。あのな、市民登録のあと説明されたこと、覚えてないのか? イラヴァールの通貨は、デール、マール、イェールの三種類で、価値は同じだけど、一日、一月、一年って有効期限が違うんだろ?」
シシィは何度か深呼吸してから、じっと僕の顔を覗き込んだ。
「あ~……、ほら、僕あのとき、魔力の匂いで酔っ払ってて……」
僕が目を泳がせると、シシィは右手で目元を覆い「ここでも魔香酔いかよ」と天井を仰ぐ。
僕は半分人狼の血が流れているため、魔力の匂い『魔香』を嗅ぎ取ることができる。ただもう半分はヒューマーなので、取り込んだ魔香がお酒のように作用して、酔っ払ってしまうのだ。魔力量の多い人間の集まるイラヴァールでは、その匂いは猛烈な濃さになる。最近はオルナダ様が体内の魔力濃度を濃い目に保つことで対抗できると教えてくれたおかげで、ほとんど改善されたけど、来たばかりの頃は常に泥酔状態だったのだ。
「あー、もー……。んじゃあ、ステボのこととかも、まるで覚えてないってことか……」
シシィは首をかしげる僕を疲れ果てた顔で一瞥すると、右手を上げてため息交じりに「ステータスオープン」と呟いた。シシィの右手の前に、四角い青色の光が現れる。続く「コマンド、秘匿一時解除」の言葉で、青い四角が、今朝オルナダ様とユミエールが使っていたスピーチ原稿のような、文字の羅列に変わっていく。
ぽかんと見ている僕にシシィが「やってみ」と、光を出したときと同じように右手を上げてみせた。言われるまま同じようにやってみると、僕の前にも文字の羅列が現れる。こんな魔法は習得していないはずなのにとても不思議だ。
『使用者を認識しました。ステータス収集を開始します』
どこからともなく、聞いたことのない無機質な声がした。驚いて周囲を警戒するけど、人の気配はない。
「今のはステボのアナウンス。つーかマジで一回も起動してないのな」
「ステボ、さん……?」
「正式名称はステータスボード。通称ステボ。いろんなものを数値化して見せてくれる便利な魔術だ。今みたいになにか知らせることがあったら、頭に直接話しかけてくれたりもする」
「魔術なの? でも術器なんて……」
「市民権もらったとき、身体のあちこちに小さい粒みたいの入れられたろ? って、それも覚えてないのか……」
「いや、それはなんとなく……」
針がついた謎の道具で、胸やら肩やらを突き刺されたのが怖かったので、記憶に残っていた。
「まぁとにかく、コイツが魔導圏での必須アイテムなんだよ。ほらここ。八千デール、二百万マール、零イェールってあるだろ、これがお前の所持金。その下の日時は直近の有効期限な。つーか、今まで買い物とかどうしてたんだよ?」
「ドキドキしながら人の真似をして……」
シシィは信じられないという顔で肩を落とす。
僕は「今教えてもらえて十分助かったから」とシシィを宥めて、しっかり熱の入ったシチューを器に装う。続いて魔装の爪でパンを切り分け「熱いから気をつけて」と何事もなかったかのようにテーブルに置いた。
シシィは呆れ顔でシチューに浸したパンを口に放って、ステータスボードの他の機能についても説明してくれた。現在の能力や状態を数値化してくれること。特定の言葉やジェスチャーで、魔力消費なしでちょっとした魔術が使えること。一般的な知識なら、質問すれば答えてもらえること。罪になる行為を行いそうな場合に警告をしてもらえること。お互いのステボに名前を入れておくと、遠く離れていてもステボを介して話ができること。などなど、非常に便利な機能が満載らしい。
こんな大事なことを忘れていたのかと、自分がものすごく残念に思えた。
「僕、還元どころか、オルナダ様の犬、失格かも……」
「確かにかなり危うい気がするな。でもこれかららしくなればいいだろ。とりあえず、なんかしたいことで、役に立つ技能伸ばせよ」
「うーん……。僕のしたいことって、身の回りのお世話とかオルナダ様の役に立つことくらいしかなくて……。でもそれはいらないって言われちゃったんだよね……」
「気の毒なんだか、羨ましいんだか……。まぁ一応、飼い犬の推奨技能でもチェックしてみたらいいんじゃないか?」
また知らない単語が出たことで、僕はまたもう一段階落ち込んだ。
シシィは「教えてやるからしゃんとしろ」と椅子ごと僕の隣に移動して、僕のステータスボードを覗き込んだ。シシィがボードの上で指をすいすい動かすと、ボードの文字がスルスルと移動し、僕の基本ステータスを出してくれた。
名前 フューリ
職業 飼い犬(オルナダルファウルス) LV99
所持金 8000D 2000000M 0Y
PP 48 累積 48
MP ――
LUK 5290824
INT ――
PER ――
EXP ――
WIS ――
DEX ――
ST ――
AGI ――
CON ――
STR ――
僕には見方がさっぱりわからないけど、シシィは「なるほどなぁ……」と困ったように頭を掻いた。
「や、やっぱり僕、失格かな? 捨てられちゃう?」
「ん~、この職業の横のLVって、普通はもっと低い数字が出るんだけど……」
「高いと悪いの!?」
「うんにゃ、高いほうが良い。ちなみに99が最高値な」
「僕、名犬!?」
「いや、職業LVって、その職についてる全員を1~99段階に分けてランク付けしてんだけど、オルナダ様の飼い犬ってお前一人だから、自動的に99になるんだと思う」
「良いか悪いかわかんないってこと?」
「そ」
全身から力が抜けた。気持ちの乱高下の疲れ半分、安心半分、がっかり半分みたいな気持ちだった。
「まぁまぁ、そう慌てんなって。ここをこうしてっと……」
シシィは得意げにまたステータスボードを操作して、リストを出してくれた。
【推奨技能(飼い犬(総合))】
基礎教養
礼法
自己美化
対人洞察
給仕
・
・
・
シシィがリストの上で人差し指をすっと上に上げると、リストはまるで巻物を高速で巻き取ったみたいに、項目が下から上に滑っていた。
「たぶんこれが一般的な飼い犬に求められる技能。上が基本的に習得しとくべきって技能で、下に行くほど専門的で高難易度って並びになってる」
「す、すごくいっぱいある……」
「飼い犬って冒険者並みに幅広いみたいだからな。ほとんど奴隷って仕事から、執事とか参謀とか騎士とかの仕事まで色々らしいし。まぁまずは上のほうからちょっとずつLV上げてけばいんじゃね?」
「わ、わかった。……今のLVって見れないの?」
「ステボって起動してから持ち主の能力を測定し始めて、ある程度集まってから表示するから、まだ出ないだろうな。ほら、さっきの基礎ステータスもLUKしか出てなかったろ」
「そっか……」
最初の説明のとき泥酔していたことが、ますます悔やまれた。
「あるいは上げやすいとこから上げてくのも手だと思うぞ。ステボが基礎ステータスを元に、推奨職業出してくれるから、それ見て上げる技能を決めるって流れが一般的だし。ってか、ステボ使ってそういう上げ方できるのが、魔導圏に来る最大のメリットって言われてんだぞ。ほら、成長チートってヤツ」
「ふーん」
なにがどうチートなのか、よくわからないけど、シシィが興奮気味に語っているのだから、きっとすごい機能なんだろう。
「まぁ、まずはこの飼い犬向けのを身につけるようにするよ。僕、飼い犬だし」
「そか。でも冒険に役立ちそうな技能も上げといてくれよ。ここの護衛術の系統とかさ」
「了解。教えてくれてありがと」
きっとまだ当分の間、僕はオルナダ様に相応しいとは言えない飼い犬だろう。でもとりあえず、どうしていけばいいのかはわかった。ほっとした僕は、しっぽを揺らして、シシィにお礼を言った。急に食欲が湧いたので、一杯目のシチューを平らげ、おかわりをした。
「あとでちゃんとステボにステータスの見方聞くんだぞ。それからPPは五十超えたら役所で処理してもらたほうが良いぞ」
「え。あと二点で五十だけど、なにかあるの?」
「魔導圏って、ちょっとしたことがみんな罪になるだろ。他人をジロジロ見たり、デカい声だしたりとかさ。でもそんなのでいちいち裁判ってわけにいかないから、やらかしたら問答無用でPPが付与されんだよ。で、百P超えたら罰金ってことが多いから、五十ぐらいになったら自主的に役所に行って、問題のあった行動について注意を受けて、チャラにするってわけ」
「それであんまりジロジロ見られないんだ! すごい!」
僕は納得するとともに、PPの仕組みに感銘を受けた。
僕の外見には、ヒューマーに獣の耳としっぽが生えている異質な特徴がある。その上、身体が大きい。故郷では全身をシーツで覆い隠していても、町を歩けばジロジロと敵意のある目で見られたものだった。魔導圏に来てからは視線自体、感じることが少なくて不思議に思っていたけど、これで謎が解けた。
「普通はめんどくせってなるとこなんだけど……。まぁ良かったな」
シシィがカップを持ち上げたので、カツンと音を立てて乾杯した。ぐっと飲み干して、ハムを口に放り込む。ミードとハムの風味が口の中で溶け合って、コクがありながらも爽やかな香りとなって鼻孔を満たした。
不安なことも多いけど、なんとかやっていけそうな、そんな予感がした。僕はイラヴァールへ行こうと誘ってくれたシシィに深く感謝して、いつか恩返しをしようと誓った。
「ところで、金の使い道はどーすんだ? 二百ってヤベー額だけど。お袋さんこっちに呼んだりするのか?」
「あー……。いつかはそうしたいけど、まだちょっと……。飼い犬になったなんて言ったら、オルナダ様を狙撃しかねないから……」
「確かに、やりそう……」
「だよね……」
僕らは顔を見合わせて、力なく笑うと、気を取り直して再度乾杯した。
第三話公開しました。
世界観の説明が長すぎていないか心配ですが、続きます。
ちなみにステータスの各項目の設定は以下のようになってます。
MP:魔力量。
LUK:幸運度。どのくらい恵まれているかの値。
INT:知能。頭の良さ。学習の理解力、論理的思考力。
PER:知覚力。五感の鋭敏さ。
EXP:専門知識。
WIS:知識から解決策などを見出すことが出来る頭の良さ。INT、PER、EXPを基準に算出される。
DEX:器用さ。
ST:スタミナ。
AGI:敏捷さ。素早さ。
CON:体力(肉体的な強さや健康状態)。防御力的なニュアンス。
STR:筋力・力の強さ。
EXP以外は、訓練を受けていないエルフの平均値を1万として算出されます。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!