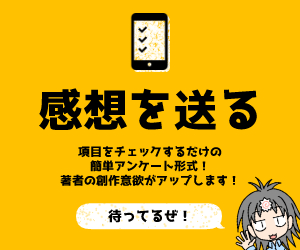ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第二話の続きになります。
第二話までのあらすじは以下のような感じです。
オルナダの飼い犬であるということの重大さを思い知らされたフューリは、友人のヒューマー、シシィに助言を求めた。そこで魔導圏の標準装備である、ステータスボードの存在を初めて知ることとなった。シシィはフューリにステータスボードの使い方と飼い犬の推奨技能を教え、フューリは飼い犬の推奨技能を上げていくことを決めた。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下三話です。
【シシィ 一】
イラヴァールには、王宮ってもんがない。
そのため、オルナダを始めとした、都市のお偉方が集まる会議は、もっぱら中央区のど真ん中に建つ、鐘塔で行われる。ということを私は今日始めて知った。
どういう訳か、オルナダから直々に、招集命令を賜ってしまったためだ。
私はただでさえ冷えるイラヴァールの秋の夜に、鐘塔内の寒々しい階段を降りて、指定された地下の会議室のドアを叩いた。魔術で施錠されたドアが発光とともに開いて、黒毛の人兎が顔を出した。人兎は私にステータスボードを見せるように言って、表示を確認すると短く「名札のところに座れ」と言って再びドアを閉めた。
地下にある会議室は当然、窓ひとつなく、装飾されていない壁は、積み上げた石がむき出しになっていた。照明に使っている光石に送る魔力を抑えているのか、室内はかなり薄暗い。中央の大きな長テーブルには、険しい顔をした人々がずらりと並んでいた。緑目にブロンドのエルフ、肌が赤く角がある巨体のオーガ、小さくて全身毛むくじゃらの毛虫みたいなドワーフ、狼・熊・牛など動物にしか見えない獣人、手のひらほどの大きさで虫のような羽の生えた妖精と、みんなそれぞれの種を代表するような容姿をしていて、生まれの良さからくるものだろう「私、気位高いですよ」オーラを放っている。黒、赤、緑、紺と、着ている制服の色は様々だが、みんないかにもお偉方といった雰囲気を醸し出していた。
中に入るや、そいつらが一斉に「なぜこの場に青服のヒューマーが?」という目でこっちを睨むもんだから、私はますます居心地が悪い。「なぜここに?」ってそんなのこっちが聞きたいっての。まぁ、心当たりがないわけじゃないけどさ。
「よぅし、全員揃ってるな」
私が椅子に腰掛けると同時に、入り口のドアがバンと開き、紅いマントを靡かせたオルナダが入ってきた。
「正統の魔王、オルナダルファウルス・ギルオウーフ・レ・ギルオウーフ・ヴェンダリオン・ラウ・ガルダーフ陛下、ご出座っっっ!! 一同、起立っっっ!!」
オルナダが入室すると、ドアのところにいた人兎が、ビシッと号令を掛け、一同は立ち上がり、キビキビとした動きで頭を垂れる。私もワンテンポ遅れてそれに倣った。
「ブゥプ、それ毎回やらんでもよくないか? 型番入れると俺の名前クソ長いし。お前らもめんどくない?」
「「「「「滅相もございません」」」」」
「そうか、言うだけ無駄か」
一同は最大限の敬意を示す姿勢を崩さず答え、オルナダは呆れた顔をする。この国王らしからぬ態度がこの人の魅力の一つなのだろうが、配下の人間はさぞ苦労することだろうと、私は内心苦笑いをした。
「さて、今日集まってもらったのは……。ん? シシィマールはどこだ?」
ブゥプと呼ばれた人兎が一礼をして退場すると、オルナダはテーブルに両手をついて話し始めたかと思ったら、きょろきょろと私の姿を探した。おかげでその場の視線が再び私に集まる。やめてくれと叫びたくなった。
「なぜ端っこにいるんだ? 前に来い。お前には色々と意見を出してもらいたいからな」
いやここで十分です。ていうか呼ばないでほしかったっす。
なんて拒否する間もなく、椅子ごと魔法で持ち上げられ、お偉方の頭上の通って、オルナダのすぐ横に降ろされた。背中に突き刺さる視線が痛い。
「おほん。今日集まってもらったのは、他でもない俺の飼い犬、フューリのことについて、意見を募るためだ。まぁ、楽に聞いてくれ」
私が呼ばれた時点でそんなことだろうとは思ったけど、こんな会議を開いてまで意見を募りたいこととは一体なんだ? あいつなにかやらかしたのか? 私は固唾を呑んで、続く言葉を待った。
「驚くべきことだが、フューリのヤツは、つい先日ステータスボードの存在を知ったようでな。「すごく便利な魔術ですね~」とあのクソキャワなしっぽをブンスカしてたもんだから、話の流れでちょろっとステータスを覗かせてもらったんだが、これがまた……」
オルナダはステータスの項目をひとつひとつ上げて、フューリの能力が想像以上に高くて感心したという話を延々と続けた。親バカならぬ、飼い主バカというヤツだ。私を含めその場の全員が、一斉に疲れた顔になる。
「オル、みんな忙しいから、要点だけ言ってくれる?」
止めどなく続く飼い犬自慢を、長髪のエルフが穏やかな口調で遮った。この人の名前は流石に知っている。ユミエールだ。噂によると、オルナダの右腕的な存在で、イラヴァールを実質的に牛耳っている人物らしい。オルナダがしぶしぶ語るのを止めたところを見ると、まんざら嘘でもなさそうだ。
「まー、要するに、あいつは類まれなる戦闘力の持ち主に成長するから、皆で協力して徹底的に鍛えてほしいということだ。そのための案を募りたい」
オルナダはどうだとばかりに胸を張るが、集められた人々はぽかんとしていた。
そんなことで呼び出されたのかと呆気に取られているのか、はたまた、どんな案を出せばいいのかわからずにいるのか、みんな口を閉じて俯き、室内は静寂に包まれた。
「オル、それは育成方針についての意見がほしいってこと?」
「いいや」
「フューリちゃんに本当に素養があるか、みんなにも見てみてほしい?」
「素養はある。推定最大値を見たから間違いない」
「あなた、それ違法だって……」
「本人に了解を取ったから問題ない。それより誰も提案はないのか?」
小言を一蹴し、オルナダはみんなを見回した。ユミエールは頭痛がするのか、額に手を当てている。
「あのね、だから、どんな案を求めてるのかをちゃんと言わないと……」
「あいつが自分から進んで戦闘系の技能を高めたくなるよう、上手いこと誘導する案を出せと言ってるんだ!」
「あなたが一言、戦闘系の技能を高めろと命令すればいいだけでしょう!」
「んなことできるか! 俺あいつに「健康で、しっぽブンブンしてれば、それでいい」って言っちゃったもん!」
ヒートアップした二人は、怒鳴り合い、ふーふーと息を吐き出し睨み合う。誰も口を挟むことはできず、くだらないからと席を立つこともできず、身じろぎもせずに成り行きを見守っている。
つーか「言っちゃったもん」ってなんだ。駄々っ子か。
魔族はステータスボードやらなんやらの仕組みを維持するために、魔力と知能の大部分を吸い取られていると聞くけど、本当なのかもしれないと私は思った。
「つまり、あなたがカッコつけで有望な人材を役立たずにしたツケを私たちに払えってこと? あなたがこのままカッコつけていたいから?」
「そのとおり! それでこそ俺の右腕!」
オルナダがパッと表情を明るくして、両手で指を鳴らした。ユミエールは目を閉じ、何度か深呼吸をする。
「あー、でも役立たずは言い過ぎだぞ。あいつはそのままでも……」
「フューリちゃんはあなたにもらったお金と時間を使って、今なにをしてるの?」
「ぬ? あぁ、そりゃもう、思いっきり勉学に励んでいるぞ。あいつは真面目だからな。ステボをフル活用してものすごい勢いで……」
「な・に・を・し・て・る・の?」
「主に使用人に求められる技能を習得している……。今は美味い茶の淹れ方と、花の活け方あたりを……」
「目を見て話せないようなことを自慢げに言わないでくれる?」
ユミエールは満面の笑みを浮かべてオルナダに詰め寄る。こんなにも恐怖を感じる笑顔を見るのは初めてだった。
フューリに飼い犬の推奨技能を教えたとバレたら、あれをこっちに向けられるかもと思うと寒気がする。ここは勇気を振り絞って口を挟み、話を別の方向に持っていかないと。
そう思ってタイミングを見計らっていると、先に赤い制服を着た老齢のオーガが口を開いた。
「私は反対ですな。陛下の飼い犬という立場を得ながら、自ら進んで使用人の道を志すなど、如何に戦闘力が高くとも、戦士の器足り得るとは思えませぬ」
言ったーーー!! という空気が室内に満ちる。
おそらく全員、同意見なんだろう。ある者は口をモゴモゴとさせて「確かにもっともだ」と呟き、ある者は腕組みをしてうんうんと頷いている。
フューリは身体は大きいが、それでもオーガほどではなく、劣等種とされるヒューマーとの混血で、表情も態度も自信なさげだ。数日前の式典では、オルナダ様が魔法で止めるまで、ずっとしゃっくりをしていて、一言も話せず、話し出してからもつっかえつっかえで、頼りない印象を与えまくっていた。あの様を見てはあいつの戦う姿なんて、とても想像が出来ないだろう。
だけど私は知っている。あいつが竜さえも、おやつ代わりに狩って食うことを。
「ふふん。これを見てもそんなことが言えるか、お前ら?」
オルナダは不敵に笑い、自分の横に緑の大きな四角を出現させた。そこに映し出されたステータスに、全員が釘付けになる。
名前 フューリ
職業 飼い犬(オルナダルファウルス) LV99
所持金 0D 1267898M 0Y
PP 6 累積 62
MP 20077
LUK 5292673
INT 16482
PER 200041
EXP 7308
WIS 40505
DEX 25407
ST 803226
AGI 51669
CON 32089
STR 107304
「ヴァカな!! STR十万だと!? オーガ兵並ではないか!!」
「それよりMPだ! ヒューマーが二万などありえん!」
「INTも平均を上回っている。これは成長が早いぞ」
「そ、それに、このCONと異常なSTなら、通常の何倍もの肉体訓練に耐えられる……!!」
お偉方が驚愕の表情でどよめく。
ステータスの値は、訓練を受けていないエルフの平均値を一万として算出される。つまりフューリの値は、専門知識の量を示すEXP 以外全てにおいて、平均を大きく上回っているのだ。半分ヒューマーでこの値では、驚くのも当然だろう。私も想像を遥かに上回る数値に、身体が震えた。
「言っておくが、推定最大値はこんなものではないぞ。漏洩禁止情報だからここでは伏せるが、鍛え上げれば、俺の遊び相手も務まるほどの数値だったとだけ言っておく」
オルナダは満足そうに微笑んで「では意見を聞こう」と両手を広げた。
「その飼い主バカを止めて、戦闘訓練に励むよう命令しなさい」
「それはダメだと言ってるだろう! あと、俺は飼い主バカじゃない!」
「これだけバカ丸出しにしておいて、なに言ってるの!」
バンッと机を叩いたユミエールが「だいたいあなたはいつもいつも……」とお説教モードに入る。オルナダは子供みたいに耳を塞いで「あー、あー、聞こえないー!」とやっている。
私はあまりに幼稚なやり取りに、空いた口が塞がらなかった。しかしお偉方からすれば、いつものことなのだろう。「命令せずにとなると、周囲から圧力をかける他ないのではないか」などと、二人を無視して相談を始めた。その意見にオルナダが「いじめたら許さんぞー!」と口を挟むので、一同は皆、むーんと腕を組み、眉間にシワを寄せる。
地獄絵図な惨状が面白くなってきた私は、一人笑いを堪えて、その光景を眺めた。
「お前はなにか良い案を出せるだろう。共通の友、シシィマール」
オルナダが唐突に、私の名前を口にした。両耳に指を突っ込んだまま、ひょいと顔を覗き込んでくる。
またしてもその場の視線が、全て私に集まる。共通の友ってなんだよ。フューリの友で、オルナダの友ってことか? マジでやめてほしい。視線が痛い。
「あー……。フューリとは一緒に冒険者になる約束をしているので、どこかで討伐案件を受注して連れてくってことくらいならできるかもですけど……」
オルナダが友とか言ってくれちゃったので、しれっと自分の希望を織り交ぜた案を言ってみた。
飼い犬になったフューリを、どうやって冒険に連れて行こうか悩んでいたところだし、オルナダがなにか適当な理由をつけて後押ししてくれたら都合が良いと思った。ついでに冒険者ギルドも誘致してくれたりなんかしたら、もう万々歳だ。
オルナダは「冒険者かぁ。冒険者なぁ……」と今一つな反応だったが、ユミエールはなぜかキラリと目を光らせた。
「そういうことなら、前から計画してたダンジョン建設プロジェクトを進めたら良いんじゃない?」
ぽんと両手を合わせると、オルナダが出現させたフューリのステータスをついっと部屋の隅に追いやり、代わりにイラヴァール周辺の地図となにかの数字を表示させる。
「知っての通り、イラヴァールの南は果てしない荒野になっています。環境が厳しく、魔物も強力なこの地域は、居住に適さないために、これまで開発されてきませんでした。しかし、ダンジョンならどうでしょう?」
ユミエールは大仰な手振りをつけて、ハキハキと語りだした。
イラヴァールの南一帯には、パラスケキュアの背と呼ばれる岩石砂漠が広がっている。燃える棘の鱗を持つ神話生物の名を冠したこの砂漠地帯は、ユミエールの言う通りの危険な場所で、住むどころか、通ることも避けられる危険地帯だった。
そのど真ん中にダンジョンを建設しようというのが、このプロジェクトだそうだ。そんなとこにあるダンジョンに誰が行くのかと思うが、ユミエールが言うには十分実現可能らしい。
砂漠の危険は主に環境と魔物だが、地上の魔物はダンジョンに近づかない習性があり、ダンジョンの魔物は地上に出ない習性があるので、作ってしまえばダンジョンの入り口周辺は理論上魔物が出現しなくなる。ダンジョンまでの道中については、魔物の出ない日中のみ移動を許可し、火傷や砂嵐を避けられる街道を整備すれば、Dランク程度のパーティーでも安全にダンジョンに辿り着けるようになるそうだ。
「事前の地質調査では、黄魔鉄鉱石、青炭、橙色光石、炎銅鉱石を始めとしたレートの高い鉱物の埋蔵が確認されており、緑黒鋼鉱石と命名した新種も発見されています。維持にかかる費用の見積もりはこのようになっていますが、これは黄魔鉄鉱石の年間産出量が二十タンほどであれば十分に賄え……」
「儲かるのはわかるが、ダンジョン作るともれなくスタンピードがついてくるからなぁ……」
オルナダがユミエールの言葉を遮って、長テーブルの上に仰向けに寝転んだ。あまり乗り気ではないらしい。
スタンピードはダンジョンから魔物が大量に溢れ出す現象で、その群れが都市を襲えば大災害となる。そのためダンジョン近郊の都市は、スタンピードに対応できるだけの防衛力を求められるのだけど、その維持には莫大なコストがかかるのだ。
しかもイラヴァールは元々災害が多く、魔物に竜巻、山火事、風水害、地震、噴火、雹などが年がら年中続く。市民全員に訓練を義務付けることで凌いでいるが、ここにスタンピードが加わるとなると、今の防衛力で対応しきれるのかはわからない。おそらくオルナダはそれを懸念しているのだろう。
だがそこは「さすが右腕」と言わしめるユミエールだ。「順を追って説明するから」と収支についての説明を終えたあとで、ダンジョンを作ることで増やせる市民数や、増額可能な防衛費、訪れる冒険者の数と、それ傭兵にした場合の戦力比やコストなど、いくつもの試算を示しオルナダを納得させた。
「それと、もう一言付け加えるなら、このダンジョンはそれなりの難易度になると予想されるから、攻略を訓練メニューに加えれば、今後何度でもフューリちゃんを強制的に実戦に放り込むことができるでしょ?」
「ふむ。それもそうだな。んじゃ、ちょっと掘ってくるか」
オルナダはその場からパッと姿を消し、ユミエールは「じゃあ早速準備にかかりましょう」と何人かにこの後残るようにと、満足そうな笑顔で告げた。
私は事のデカさに、唖然としていた。
ほん少し後押ししてもらえたら、あわよくば冒険者ギルドを誘致してもらえたらと言った一言で、まさかダンジョンが誕生することになるとは夢にも思っていなかったのだ。つーか、夢にでも思うやつがいたら出てこいや! って感じだ。
「とりあえず、三十層くらいまでにしといたぞ。まずは調査隊を送らないとな。そうだ、シシィマール。調査隊の公募出すからフューリを誘って参加してくれ。あとガルガシール、お前の孫も参加するよう言ってくれ。他はユミエールが適当に調達する」
一分とかからず戻ってきたオルナダが、まだ呆然としている私と、先程異議を唱えたオーガを指差す。
「おお……。ははぁっ! もちろんでございます! ぐふふ、我が孫は陛下から見ても見どころがありますか! がっはっはっ」
「あいつイチイチ纏わりついてきて、鬱陶しいからな。シシィマールはどうだ? 上手く誘えそうか? 誘えないと困るぞ?」
椅子から崩れ落ちそうになっているガルガシールをよそに、オルナダは私に期待の目を向けた。
私はオルナダがダンジョンを一分で作ってきたことにも、それについて誰一人ツッコミを入れないことにも、ドン引きしていた。ヒューマー圏と魔導圏の間に、大きな差があることは知っていた。でもその差がどれほどのものかは、まるでわかっていなかったのだと思い知らされた。
魔族ヤベェ、マジでヤベェ、思ってた百億倍ヤベェ!
それにそんな魔族を唸らせるフューリのステータスもヤベェ! しかもここから鍛えられていくなんて、最終的にはどうなってしまうんだ! 百人力どころの話じゃないぞ!
頭の中の小さな私が絶叫して走り回る。
まぁでも、もうイラヴァールに来てしまったのだから、こんなことにショックを受けていても仕方がない。今は思惑が遥か斜め上の方向で上手くいったことを喜ぼう。
私は任せてくれと胸を張り、すたこらと会議室をあとにした。
第四話公開しました。
異世界モノのステータスボードの仕組みがいつも気になっていたので、魔族が構築運用していることにしました。ステータスボードのお陰で便利は便利ですが、実は中国も真っ青な超監視社会だったりもします。
それはともかく、オルナダ様がバカやってると、とても楽しい。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!