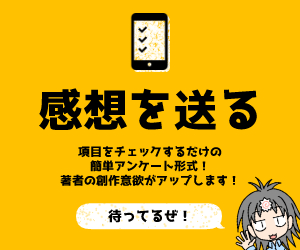ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第十一話の続きになります。
第十一話までのあらすじは以下のような感じです。
ダンジョンから帰還したフューリはオルナダの匂いを追って地下室を訪れるが、そこではオルナダ、ティクトレア、ヒーゼリオフの三人が頭から布団を被って震えていた。魔族は本能的に雷が苦手らしく、フューリは三人を抱っこして一晩過ごすことになる。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下十二話です。
【シシィ 二】
私らがイラヴァールに帰還したのは、調査終了日翌々日の昼だった。当日は明け方まで続く雷雨に足止めされ、その後は砂嵐に見舞われてこの時間になってしまったわけだ。
竜車を降り、日当を確認して、とりあえず風呂屋に行って汗を流したら、みんなでパーッと酒でも飲もうかなんて話していると、ティクトレアとヒーゼリオフが突然目の前に転移してきて、なにも聞かずに一緒に来いと強引に私を連れて、どこかへ転移した。
そんなわけで私は今、どこかもわからないゴージャスな客間につれて来られていた。室内は白を基調とした一見シンプルな内装だけど、あちこちにお高い木材や金での装飾が施されていて、天井もアホほど高い。明り取りの窓の位置も完璧に設計されていて、光の演出が見事だ。置かれている家具も見るからに最高品質のものばかりで、かなりランクの高いVIPルームであることが見て取れる。
私は転移と同時に上等なテーブルクロスが敷かれたティーテーブルに座らせられた。ティクトレアが「突然ごめんね」と左隣に座り、ヒーゼリオフが「別に悪いようにはしないから安心しなさいよ」と右隣に座った。正面にはティクトレアの飼い犬のケイシイが座っていて、緑の制服を着たエルフが運んできた、上品な香りの紅茶ぐびぐび飲んで、薔薇をモチーフにしたデザインのケーキスタンドに乗ったお菓子や軽食をパクパクと摘んでいる。
制服のヤツがいるならイラヴァール内のどこかなんだろう。この部屋の感じからして南側地区にある金持ち旅行者向け高級宿の一室といったところだろうか。どこだとしても魔族二人がかりで連れてこられた場所だ。嫌な予感しかしない。
「このヒーゼリオフ様のおごりだから、じゃんじゃん食べなさい! えーと、ジェミーベール?」
「あーっと、シシィマールですね。響きの感じを覚えててもらえて光栄です」
「よろしくね、シシィマール。シシィくん、で良いかしら? オルからフューくんのお友達だって聞いたんだけど、あってる?」
「あぁ、はい。その通りですね」
またフューリ絡みかよ! だろうと思ったけど、あいつ今度はなにやらかしたんだ!? 内心冷や汗をかきつつ、私は努めて笑顔で質問に答えた。
「で、どのくらいの仲なわけ? フューについて知ってることを洗いざらい吐きなさい!」
「えー……。まぁ、同郷で子供の頃からの付き合いなんで、幼馴染みとか、マブダチってトコですかねぇ。洗いざらい話すのは良いんですけど、なにを聞きたいんです?」
「そ、それは……」
「そのぅ……。なんというか、ねぇ?」
「好みのタイプとかそういうのを知りたいらしいっすよー」
「「ケイシイ!!」」
「へぶっ!!」
回答がなされると同時にティクトレアとヒーゼリオフがバンッと両手をテーブルに叩きつけ、ケイシイが食べていたお菓子が爆発した。顔面をクリームまみれにされたケイシイが「だってそう言ってたじゃないっすかぁ」と情けない声をあげると、二人は「黙れ黙れ!」と魔法でケイシイの鼻にクリームを突っ込む。魔族がこんなことをしたらPPがエライことになるんじゃないかと思ったけど、私が考えるべきはそこじゃない。じゃあなにを考えるべきかと言われても困るけど、とりあえずそこじゃないことだけは確かだ。つーか、フューリのヤツ、マジでなにをやらかしたんだ!?
「えーと、つまり、お二人は、なんというか、あいつとこう、あれこれをそれこれしたいってことですか?」
あまり具体的に言うとケイシイの二の舞になりそうなので、とことんぼかして尋ねてみた。二人は「ま、まぁ、そういうことね」と頬を赤らめつつ肯定する。日に三度も不特定の相手と寝る魔族がなんて顔してんだ。ヤメロ。いや、待て。ぼかしまくったせいで本当にそういう意味で言ってるのかはまだわからない。ひょっとしたらオルナダもビックリな高スペックのあいつを引き抜く手段を探してるってだけかもしれない。そうであってほしい。
「えー、確認ですが、あれこれの部分を具体的に言うと……?」
「ま、まぁ、強いて言うなら、親密度ってトコね」
危うい! けどまだセーフだ。引き抜きにも親密度は関係するだろう。
「じゃあ、それこれのところは?」
「そうねぇ。高めていきたいって感じかしら」
よしよし、セーフ、セーフ。なんか二人がモジモジしてる気がするのは気のせいだ。
「それはどのくらいまで高まれば良いんでしょう?」
「「そ、それは、その……、せ、性的に交われるくらいまで……、きゃあ、言っちゃった!」」
「きゃあ、じゃねぇよ」
嘘でしょ? と言おうと思ったけど、先に本音が出てしまった。誤魔化すために私は、ぶぉほん、げぼんと、人生で一番激しい咳払いをした。
一体どうしてこんなことに!? マジでなにした、フューリ!! お前そんな美形じゃないし、コミュ症の人見知りで、こんな出会って間もないヤツなんか、口説くどころか会話もままならないはずだろおおおおお!! 私の頭の中は大混乱だ。
「そ、そっすか。へぇ。でもあいつのどこがそんなに良かったんすか?」
混乱しつつも聞かずにはいられない質問をぶつける。自分からは特になにもしていないであろうフューリが、わずか数ヶ月の間にオルナダを含めた三人の魔族を立て続けにたらし込むなんて、なにかよっぽど気に入られるポイントがあるに違いない。私は努めて穏やかな笑顔を作り、答えを待つ。
「いや、どこがって別に……」
「ぜ、全体的に~、みたいな~」
「見た目がドストライクらしいっす」
「「ケイシイ!!」」
「ぶほっ!!」
回答がなされると同時に以下略で、またしてもケイシイはお菓子の残骸にまみれることになった。どうもこいつは相当な〝懲りないヤツ〟らしい。魔族相手によくやるものだとある意味尊敬した。
まぁそれはさておき、見た目という回答はかなり意外だ。
フューリはカワイイヤツだけど、この世界における外見の美しさは、基本的にどの地域でも、いかに〝エルフらしいエルフ〟に近いかで決まる。目は大きく、瞳の色は緑、鼻が高く、耳はシュッとした笹耳、髪は長く美しい直毛のブロンド、身長は百七十センチを超える程度で、手足が細長く、胴体に凹凸の少ない、すらっとしたスリム体型が望ましいとされている。知っている顔で例を出すなら、ユミエールあたりが理想的な美人だ。
そこへいくとフューリは、目は大きいが、瞳の色は金色で、鼻もそんなに高くないし、耳はあの通りのケモ耳だ。顔立ちもヒューマー側の母親が顔面偏差値高めなおかげで、パーツは望ましい位置についているが、人狼側の母親の影響か、それぞれのパーツが犬っぽく、愛嬌はあるが美しいかと言われるとそんなことはない。髪だって綺麗ではあるけど、どうにも奇抜な青色だし、くせっ毛だ。背は二メートルを超えててデカすぎるし、手足は長いけど細くはない。胸も尻もデカくて全体的に肉付きがよく、むっちりとまではいかないが、決してすらっとはしていない大肉大背って感じの体型だ。美人の基準からは結構外れているはずなのである。
それを見た目ってどういうこと? それも二人揃って? なぞは深まるばかりだぜ?
「な、なんなんすかもう! あいつを見てからずっと「あの耳としっぽがたまんない」って、職人に付け耳と付けしっぽを作らせ……、ぐはあああああ!! ちょ、ちょちょちょ!! ギブギブギブ!! あつあつあつ~~~!!」
「永遠に黙らせてあげても良いのよ~~~」
私の疑問は解消されたが、余計なことを言ったケイシイは、大きな手に握られているみたいに気を付けの姿勢で宙に浮いて、ミシミシと骨を軋ませ叫んでいる。その上、頭からポットに入った紅茶をぶっかけられている。
返答をミスったら私もああなるのかもしれない。私は下手なことを言わないよう、ケイシイへのお仕置きが済むまで、黙々と出された食事を食べることにした。
「くっ……。バレたからにはしょうがないわ。でもそれにはやむを得ない理由があるってことだけは忘れないでよね!」
「はい」
「その通りなの。一応、説明すると……」
「や、しなくても大丈夫ですよ」
「わたくしたち魔族は魔力を糧として生命活動を維持しているのだけど……」
「これは魔族の原種である古代魔族も同じだったのよね。違うのは、地底や天空で暮らしていた古代魔族は魔力を自然や動物から吸収してたってトコ」
「あ、説明したい感じですね。聞きます」
語りだすティクトレアとヒーゼリオフを止められるはずもないので、私は余計なことを言わないよう口を閉じて聞くことにした。
「だから古代魔族は動植物が大好きな生物になったんだけど、やがて別の種族の人間たちと出会うと、そっちも好きになって可愛がるようになったの」
「で、まぁ、姿形が似てるから、そのうちそういうことを試す連中が出てきて気付くのよ。「あ、動物なでなでするより、こっちのほうが魔力吸収効率良いじゃん」ってね」
「そう。そして古代魔族は多種族とじゃんじゃん交わって、段々と薄まっていったわ。その結果、誕生したのが今の魔族なんだけど、古代魔族の頃の動植物大好きって性質は今も色濃く残っているの。だから……」
「はぁ。つまり、あいつの犬っぽいトコが、たまんないわけですね」
「「そうなの!!」」
ついポロッと口を滑らせたのがまずかった。
それまで歩き回って大きく手を広げたり拳を握りしめたりして大げさに語っていた二人が、目をギラつかせて鼻息荒く私に詰め寄った。
「多種族は大抵エルフっぽい見た目が好きだけど、魔族的には獣人が至高って感じなのよね!」
「でも獣人さんはこう、ちょっといろんな点で〝食事〟の相手としてはどうかなってところがあるんだけど、フューくんはそのいろんな点がないじゃない!?」
「でも耳としっぽはある!!」
「どっちもふさふさ!!」
「しかも! 耳は先っぽがへにゃってなってる! なんなのよアレ! 反則でしょ!!」
「しっぽの先が白いところもチャーミングよね! 感情がダイレクトに出るのもキャンワイイわ!」
「フューリたん、ぐうかわ?」
「「それな――――――――――!!」」
身悶えしながら絶叫する二人に、復活したケイシイが合いの手を入れる。よくもまあ懲りずに絡むなと呆れるけれど、それ以上に魔族らの暑苦しさにドン引きだった。
オルナダのときも思ったけど、魔族って実はみんなアホなのか? 「ぐうかわ、ぎゃんきゃわ♪」歌いながらラインダンスをするな。挙げ句「きゃわたんたん♪」てなんだ。あんたら支配種族だろう。もっと威厳のある存在でいてくれよ頼むから。
私が顔を引きつらせて、ポットから注いでいるお茶をカップから溢れさせていると、不意にティクトレアがぐうかわダンスをピタリと止めて、全身からドス黒いオーラを立ち上らせた。ティクトレアの周囲だけが一段階暗くなり、黒い靄のようなものが揺らめいた。
「そしてそんなゲロッかわなフューくんを、オルはわたくしから奪い去ったのよ……」
ティクトレアから放たれる猛烈な負の波動に、部屋の空気がビリビリと震えた。私の身体はすくみ上がり、完全に動かなくなった。お茶を注いだ状態で硬直したので、カップから溢れたお茶がソーサーを満たし、さらにテーブルクロスへと広がって、びちゃびちゃと床に溢れた。
「ティッキー、抑えて抑えて。また黒いの出ちゃってるよ~」
ケイシイはこの黒オーラに慣れているのか、これまで通りのヘラヘラとした調子でティクトレアを宥める。
「だってだって、わたくしが先に目を付けていたのよ? 面談会が始まったときから、この子は絶対確保しようって決めてたのに!」
「誰も声掛けないようにさせて、終了間際に颯爽と現れて採用しようなんて企むからっすよ」
「あなたが提案したんじゃない!!」
「あ~~~……、そ~~~おぉ……? 全然記憶にないなぁ~~~……」
面談会ってのは飼い犬になりたいヤツが、飼い犬を欲しがってるヤツと顔合わせをする場だ。飼い主側が目ぼしい相手に声を掛け、互いに条件が合えば採用となる。言ってみれば、檻と商人がいない奴隷市だ。
そんなことより誰か早くティクトレアを止めてくれないだろうか? もうポットが空になるぐらいの間固まっているんだが? つーか、あんな邪悪なオーラをまとう相手を抱きしめてよしよしするとか、ケイシイのヤツ、一体どんな神経をしてるんだ?
「ていうかオルって、飼い犬持たない主義じゃなかった? なんでその日に限って現れたのよ?」
「前日の相手に〝あたって〟体調崩したから、普通の魔族と同じく、安全な相手を側に置きたくなったらしいっす」
「オルさえ来なければフューくんはわたくしのものだったのに、わたくしにしっぽブンブンしてくれたのに、悔しいいいいい――――――――――――――――――――!!」
悔し涙を流して絶叫するティクトレアは、ドス黒オーラをますます強めて、私は失神しそうになった。これまでの人生の主要なエピソードが脳裏に蘇る。
冒険者に憧れて、家を抜け出して野宿して死にかけたり、知識もないのに野草を食って死にかけたり、フューリと一緒にフューリの母ちゃんのサバイバル訓練受けて死にかけたり、いろんなことで死にかけたなぁ。
ってこれ、走馬灯ってヤツじゃね? こんなバカ話に付き合ったせいで死ぬのか私!? となったところでやっと、異変に気付いたヒーゼリオフが私の周りに留まるティクトレアのオーラを払った。
正気に戻ったティクトレアが私に治癒系の魔法を掛けて、ようやく私は呼吸をすることができた。『技能「魔力波耐性」を検知しました。技能LVを計測します』とステータスボードのアナウンスが頭に響く。ってか耐性つくってことは、毒攻撃みたいなもんってことだろ、FU・ZA・KE・N・NA☆
「ごめんね。思い出したらつい、ムカムカしちゃって……。話を戻すと、わたくしたち二人共、フューくんと仲良くなりたいんだけど、どうするのが良いのかをあなたに相談したかったの」
「その前に死ぬトコだったんすけど!?」
「まぁまぁ、シシィ氏。ティッキーくらいの魔族になると、死んですぐなら生き返らせられるから落ち着いて。ボクも何度か経験あるから保証するっすよ」
「あんたに至っては実際死んでんのかよ!!」
とんでもない事態にキレ気味にツッコミを入れると、ケイシイがさらにとんでもない発言をしたので、私は命を守るため、深呼吸して必死に平静を取り戻した。こんなとんでも種族相手に下手を打つのは危険すぎる。口を慎まなくては。
「…………ふーーーぅ。……まぁ、仲良くなるっていうなら、普通に遊びに誘ったりすれば良いんじゃないすかね」
「「あ、遊びっていうと、パーティとか、お風呂屋さんとか、そういう?」」
「頭湧いてんすか?」
飯とか、飲みとか、そういう普通の遊びです。と言うはずが、また率直な気持ちが口をついて出た。
でも死にかけた上に、二人揃って「ムッハー!」とか叫び出しそうな表情でそんなことを言われたにしては優しい言い方だったと思う。セーフだ。そうであってくれ。つーか早くここから逃げないと!
「おっふん、おっふん! てか、サクッとアレに誘っちゃえば良いんじゃないすか? 結局目的ソコなんすよね? なら最短距離で突っ込むほうが早くないすか? 魔族の人はそういうの得意でしょうし」
これ以上こんな話に付き合ってたら、本当に殺されるレベルの発言をしてしまうかもしれない。私は早々に話を切り上げるべく、極論を述べた。フューリには悪いが、あいつの場合は最悪オルナダがなんとかしてくれるだろう。
祈るような気持ちで二人が「そうね、そうする!」と言ってくれるのを待ったが、出てきたのは超絶ロングなため息だった。
「そうしたいところなんだけど、シシィくんはフューくんの就任式のこと、覚えてないかしら?」
「オルのヤツ「フューリはまだそういうのに慣れてないから」とか言って、誘うのもダメって言うのよ! 街中に御付令まで貼っちゃってさ。絶対、独り占めしたいのよ! ま、まぁ、ヒーゼリオフ様は誘う気なんて全然ないけどね! そういうのは向こうから来るべきだし!」
「そうなのよね……。無視して誘ってオルにバレても面倒だし……。だからフューくんのほうから誘ってほしいんだけど……」
「それで好みのタイプを知りたいと……」
「「そうそう。わかってくれて嬉しいわ」」
二人はにっこり微笑んで、期待を込めた目を向けてくる。この問題が超が百個くらい付く難問であることをわかっていないらしい。下手な助言をするたびに殺されたら、何千回と死ぬことになりそうだ。
「で、でも……、あいつ別にチクったりしないと思いますし、魔族に誘われてOKしないってヤツもなかなかいないんじゃないっすか? ここは思い切ってサクッと……」
「そう思うのも無理はないんだけどねぇ……。ふぅ……」
「実際のところ、魔族ってそんなにモテないのよ……。はぁ……」
なんとかこの方向でゴリ押せないかと再度勧めてみたが、二人はカクンと肩と頭を落として、哀愁を漂わせだす。
「番制の文化圏からすると、なんの制約もないから、好きなように相手を変えて楽しめるように見えるのかもしれないけど、自由というのはなかなかに過酷なものなのよね……」
「その通りよ。番制なら一対一だから、しょうもないヤツでも相手をゲットできるけど、そういう縛りがなくなると、途端にモテるヤツが独占しちゃうんだからね。ま、誰だって、イケてないヤツとの十回より、イケてるヤツとの一回のほうが良いからしょうがないけど」
「それに多種族の子たちは、わたくしたち魔族と違って、性行為に食事の意味合いがないから、そもそもそんなにしたがらないしね」
「あなたのことは好きだけど、日に三度は多すぎるわ! みたいなね。実際それでフラれる魔族も多いのよ。魔族ってだけでお断りされることさえあるし」
「嫌々相手をされると、こっちが食あたりを起こしちゃうから、無理強いもできないしね」
「ボクならいつでも何度でもウェルカムっすけどね~」
「そうね。あなたは素敵な非常食よ」
ティクトレアはケイシイに貼り付けたような笑顔を向ける。
ラインダンスをしていたときのテンションはどこへやら。今やティクトレアとヒーゼリオフはまるでお通夜にでも来たような顔をしている。魔法で大抵のことは思い通りにできるはずの魔族もいろいろ大変らしい。
まぁ腹が減るたびに〝食料〟を口説かなきゃいけないんだから、面倒くさいったらないだろう。それにそこまで需要が高いとなると、ウザがられることもあるだろうし、足元を見られてハードな要求をされることもあるかもしれない。飼い犬という意味不明な高待遇職が存在するのも、安全な〝食料〟を手元に置くためなんだろう。普通の魔族は何十人と飼い犬を囲うものらしいし。
しかしこうなってくると、サクッと誘ってみる路線でゴリ押すのは難しいということになる。私はうんざりしつつ、あのオルナダ命状態のフューリを口説き落とすプランを考えることにした。
「えーと、じゃあ、ひとまず、普段相手を口説くときどうしてるか教えてください」
「「当然、餌場作りね。それか既存の餌場に入れてもらうわ」」
考えることにしたものの、さっぱり案が浮かばないので、参考までに尋ねると、まったく意味不明の答えが返ってきた。
「ええとね、まず街とか国とかを適当なところに作って人を集めて、それで「ここにはこういう魔族がいるから〝食事〟の相手になっても良いよって子は声を掛けてね」とか、「もし魔族から〝食事〟の相手を求められて少しでも嫌なら即断ってね」とか、そういう魔族の扱い方を教育して、お互い気軽に誘えるようにするの。シシィくんもここに来たとき説明受けたでしょ?」
「それは口説くとは言わねぇ!!」
あれってそういうことだったのか! と思いつつ、スケールと常識の壊れっぷりに絶叫した。「え? そうなの?」とでも言いたげに目を丸くするのが腹が立つ。
イライラしつつも話を聞くと、どうもこの手のことに関しては、徹底的に待ちのスタイルを取るのが魔族流らしい。不特定多数が魅力を感じるような立場に立ち、寄ってくるヤツの中からその日の相手を選ぶ。そのほうが楽だし安全だってことみたいだ。ティクトレアの言う「魔族はそれほどモテない」は、モテ度が自分の要求レベルに達していないってだけの話で、他種族に比べると桁違いにモテるってのが本当のところらしい。
てなわけで、お魔族様は一般的な口説き方ってヤツさえご存知ない。
最悪なのは、さっきの発言で魔族二人が私の思う口説き方について興味を持ってしまったことだ。「ヒューマー圏ではどんな風に相手を口説くの?」と期待を込めた眼差しを向けてくる。
んなこと知るか! こちとら一応、貴族生まれで、誰かに言い寄るなんてしたことないわ! むしろ言い寄られて迷惑しとったわ! と言えたら良いのだけど、それを言ったらさっきのケイシイみたく、宙吊り熱々紅茶ぶっかけの刑に処されるだろう。
無事に帰るには、なんとか適当なテクニックをでっち上げて納得してもらうしかない。私はこれまで読んだ冒険小説の中にあった、おまけ程度の恋愛要素を必死になって思い返した。
「そうですね。最強なのは、パンを咥えて走って意中の相手にぶつかることなんすけど、お二人はもう出会いはすませちゃってるんで、別の方法を考えないとっすよね……」
「なっ……!! 最強の手札はもう切れないってこと!?」
「ま、まぁ、何事も先手必勝じゃないっすか。そういうアレですよ」
「なるほど……。勉強になるわね……」
「モテテクならボクも興味ありますよ~」
魔族たちは真剣な表情でウンウンと頷き、ケイシイまで目を輝かせている。自分で言っといてなんだが、こんなデタラメ、怪しまれないことが驚きだ。でもこれなら多少変なコトを言っても大丈夫だろう。
「出会ったあとは、相手にさり気なく自分の〝イイトコ〟を見せます。例えば、馬車や竜車が行き交う街道をわたりたいお年寄りを手助けするとか、雨の中、罠にかかった子供の魔物を逃してやるとか……」
「そんなのどうやってさり気なく見せんのよ!」
「雨って必要なのかしら? 天候を操る魔法は基本禁止なのよね……」
「イイトコがない場合はどうしたら良いんすか?」
うん。やっぱり全然大丈夫だ。
「今のはあくまでも例なんで、他のコトでも全然良いっす。ない場合はまず見つけといてください。あとは……」
自力で頑張ってください。と手を振って立ち去ろうと思った。でも仮にそれで、この場は解放されたとしても、この感じだと今後も度々呼び出されて、助言を求められる羽目になるんじゃないか? だとしたら適当なことを言って酷い目に合うより、しっかり助言して恩を売り、将来的にパトロンとかになってもらえるように仕向けたほうが良いかもしれない。どうせ身の危険を感じることになるなら、少しでも利益を得られるように動くべきだろう。怖えぇけど。でもこんなところで日和ってたら冒険者なんか務まらない。
「……あとはイイトコを見せる機会を増やすために、なるべく近くにいることっすかね~。パーティを組むとか、師弟関係を結ぶとか、ライバルなんてのもアリっすけど、まぁ、とりあえず仲良くなることを目指していくのが良いと思いますよ。私がフューリを誘うんで、まずは何度か一緒に飯を食うってのはどうっすかね?」
「それはいいアイディア!」
「アンタなかなかやるじゃない!」
竜巣に入らずんば、竜卵を得ず。思い切って仲介役を申し出ると、二人は喜んで飛びついてきた。
フューリと一緒とはいえ、この二人と食事なんて、確実に寿命が縮む。んなことタダでやる気はない。私は食事に行くだけでもいくらかの利益を得る方法を考える。
「ん~、お二人とではただ食事ってのも変なんで、なにか口実があったほうが良いと思うんすよね~。今回の調査を見学して、私らのパーティに将来性を感じたから投資をしたくなった~、ってのはどうっすか?」
こうしておけば、この二人が私の働きに報酬を出す気にならなかったとしても、いくらかの援助は受けられる。
さあ、二回目の「それはいいアイディア!」よ、来たれ!
と思っていたら、ヒーゼリオフが途端に呆れた顔をして「それは無理があるでしょ」と肩を竦めた。
そこは乗って来いよ、おい!
「フューは単独のほうが圧倒的に良い動きしてたわよ? パーティのときはメンバーのお守りに徹してて、全然実力を発揮してなかったじゃない。あんな人材をわざわざパフォーマンスが下がる環境に置くなんてバカな真似、誰がするのよ?」
まったくもってその通りだが、これについては完璧な理由を答えることができる。
「フューリは富にも名声にも力にも興味がなくて、オルナダ様の側にいられれば幸せ~ってヤツなんで、好き好んで冒険に出たりしないんすよ。だから私が誘って始めて重い腰を上げてくれるってわけなんです。それかオルナダ様に命令されるかっすね」
「つまり、フューくんになにか頼もうと思ったら、シシィくんかオルのどっちかを経由する必要があって、それならシシィくん経由のほうが頼みやすいってことね。そしてパーティを強化することで、フューくんが実力を発揮できる機会を増やして、魔族からの依頼もこなせるように育てようという目論見をわたくしたちがしているということにすると。それなら定期的に成長度合いの確認名目で会えるし、指導するポイントを見つけて鍛えるうちに師弟関係に発展しするし、体術なんかを教えるならボディタッチも自然にできる。そういうわけね」
「そういうことっす!」
私の回答は私経由のほうが頼みやすいってところまでだったけど、ティクトレアが妄想を膨らませて、勝手にこの作戦に乗るべき理由を解説してくれた。おかげでヒーゼリオフは鱗が落ちた目で私を見て、私は二回目の「アンタなかなかやるじゃない!」をいただけた。
こいつら、かなりチョロいかもしれない。
「けどなんか気の長そうな作戦っすね~。ボクはパンのテクを使わせてもらおうかな。それなら肝心のアレもすぐできるってことなんすもんね?」
「ソコは相手次第っすね。肝心なのは誘ったときに確実にOKしてもらえるレベルまで、好感度を高めておくことで、テクってのはそれを効率よく上げてくための手段ですから」
チョロいという確信が私を饒舌にさせた。ここまで乗り切ってきたのだから、もうなにを言われても自信たっぷりにデタラメを並べれば、それっぽく見えるはずだ。
あとはこの立場をどれだけ上手く活用するか。私が今後考えるべきはそこだけだ。
「まぁ、お二人はフューリから誘うように仕向けたいってことなんで、とにかく好感度上げに集中してください。間違っても逆に誘ったり、アピールしたりしないようにお願いします」
「えぇ~~~? 気があるアピールしたほうが好感度高くないっすか?」
「多種族の文化圏ではどうだか知らないっすけど、ヒューマー圏では気のない相手からの誘いやアピールはキモいしウザいんすよ。だからその前に好感度を上げるんす」
「ケイシイ。あなた今の言葉、しっかり頭に刻んでおいたほうが良いわよ」
「んん? どゆこと?」
ティクトレアがケイシイの頭をつつき、ケイシイは目を白黒させた。
「てかそれって、フューがこのヒーゼリオフ様に対して気がないってこと? 流石にそんなワケなくない?」
「いや、それ以前の問題なんですよ。フューリってヤツはヒューマーの町で恐れられながら育ったんで、無意識に気を持つこと自体避けちゃうんすよね。「どうせ怖がられて話もできないし」みたいな感じで。今だって「友達を作りたい」って言いながら、出会いの場に出かけることもしないですし、「殿下~」って寄ってこられるだけで、ビビってしっぽ巻いて、しどろもどろしますしね」
「あらぁ~……」
「ふ、ふーん……」
私の説明に、二人はうっとりと虚空を見つめる。二人の妄想の中のフューリが相当カワイイことになっているらしい。そういえば調査中も、時々こんな風にフューリを見てたっけ。陰キャが好きって人もいるもんなんだなと、私は目を天井に向けた。
「まぁとにかく、そういうヤツなんで、協力はしますが、そう簡単に進展しないってことだけは覚悟しといてくださいね。あいつは自分からそういうアプローチができるようなヤツじゃないし、今は飼い主にぞっこんっすから」
「う……。ま、まぁ、そうよね……」
「オルに飼われてるんだものね……」
「もうサキュバスとかじゃないとダメな身体にされてるかもしれないっすもんね」
「「いや―――――!! それは言わないで―――――!!」」
私はあいつがシャイだとか、番制文化圏で育った影響で目移りはし難いだろうってことを言いたかったのだが、二人が気にしているのは明後日の方向の事柄だった。しかもかなり気が早い。まぁなんにしても、難しいことをわかってくれているのはラッキーだ。
てかサキュバスじゃないとダメな身体ってなんだ。オルナダはスゲーって噂だけど、そんなスゲーのか? そんなの相手しててフューリは大丈夫なんだろうか? まぁ知ったこっちゃないか。
そんなこんなで対フューリ好感度アップ作戦は始動し、私は参謀を務めることになった。逃げられないなら、徹底的に利用しよう。最悪、フューリを通じてオルナダになんとかしてもらえば死ぬことはないはずだ。そういうことにしておこう。
解放された私は、その足で風呂屋に向かった。遊人を捕まえ、金を払い、今後のためにその手のテクニックを徹底的にリサーチした。おかげで調査任務で得た金はすっからかんになってしまったが、先行投資というやつだ。やむを得ない。
絶対に掛けた金以上の支援を引き出してやる。強く心に決めて、私は周辺で一番安い飯屋に入った。
第十三話公開しました。
キレ気味のシシィと、ぞんざいに扱われるケイシイを書くのは楽しいですハイ。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!