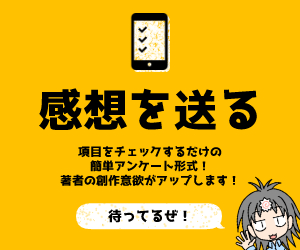ハイエナ設定使用のオリジナルの百合小説です。
Kindleから出版している『ネコサマ魔王とタチワンコ』の続編で、第十九話の続きになります。
第十九話までのあらすじは以下のような感じです。
オルナダと一夜を過ごし、近況報告で色々上手くいっていないことを打ち明けたフューリは、指導を受けて問題点を改善していくことになる。技術交流での生徒が教えたことを覚えてくれない問題は、簡単な助言ですんなり解決したが、次の悩みである力のコントロールや技能の解除については、オルナダが精神魔法で直接フューリの身体を操作する必要があるということだった。契約を交わし肉体を任せたフューリだが、オルナダ本体とフューリの身体を操るオルナダがバトルを始めたので、猛烈に慌てることになってしまった。
【登場人物一覧】
フューリ:元狩人でオルナダの飼い犬。人狼とヒューマーのハーフ。
オルナダ:イラヴァールの国王的魔族。
シシィ:フューリの友人のヒューマー。
ガーティレイ:調査パーティメンバーのオーガ。
ルゥ:調査パーティメンバーの人兎。
ヴィオレッタ:調査パーティメンバーのダークエルフ。
キャサリーヌ:調査パーティの指導教官。オーガとエルフのハーフ。
ティクトレア:イラヴァール大臣的魔族。
ヒーゼリオフ:ランピャンのダンジョンマスターをしている魔族。
ケイシイ:ティクトレアの飼い犬をしているエルフ。
ユミエール:オルナダの右腕的エルフ。
ブゥプ:ユミエールの部下の人兎。
以下二十話です。
【フューリ 十五】
ダメージを完全回復した僕の身体は、筋肉の動きを確かめるようなゆっくりとした動作で、斜め上方向へ向け何度かパンチを打つ。そしてオルナダ様に「この角度で頼む」と告げ、オルナダ様は言われた方向へ幾重もの四角い魔力板を作りだす。
緑色に発光する魔力板の列は、雲の向こうまで並んでいて、正確に何枚あるかはわからない。だけど雲の手前まででも、数千枚はありそうだった。
「この魔力板の一枚一枚は、平均的なエルフの強化無しジャブで割れる程度の強度にしてある。百枚割れたらエルフの強化有りストレート、五百枚ならオーガの強化有りのストレートくらいの威力があると思って良い」
『つまり、これが何枚割れたかで、僕のパンチの威力を計るんですね』
「そうだ。普段のお前でも千枚は割れるだろうが、俺が操作してるから五千は割れるだろう」
『そ、それは、なんだか怖いですね……』
自分の身体にそんな力があるなんて、正直考えたくもない。ただでさえ怖がられやすい見た目をしていて、なにもしなくても近付く人を怖がらせる技能が常時発動していて、オルナダ様の飼い犬だということでまた新しい怖がられ方をするようになってしまったのに、この上、オーガの十倍の威力があるパンチを打ててしまうとなったら、多くの人は僕に近づこうとは思わないだろうし、姿を見るだけで逃げ出すようになるかもしれない。それじゃ故郷の二の舞だ。
「怖いようならやめとくか? さっきと違ってお前に抵抗されるとマジで危ないし」
『……いえ、お願いします』
怖いのは確かだけれど、でもこれで力のコントロールと、技能の制御を身に着けられれば、今よりももっと強くなさそうに見せるのが上手くなるかもしれない。それができたら、念願のシシィ以外の友達作りに一歩近づけるかもしれない。そう例えば、ルゥちゃんとか!
だったら挑戦する価値はあるし、それにオルナダ様に任せればきっと大丈夫だ。
僕が決心すると、オルナダ様は静かに頷いて、腰を落とし拳を構える。
「これからお前の身体で百%の力でパンチを打つ。次は五十%、その次は二十五%と、半分ずつ威力を落としていくから、出す力と威力の関係を覚えるんだ。そうすればやりたいことに対して、どのくらいの力が必要なのかがわかるようになる」
『はい!』
「良い返事だ。だが百%の力を出すってのはリスクが伴うぞ。人間の身体ってのは筋肉や骨の損傷を避けるために最大でも八十%程度までしか力を出せないようになってるからな。俺の制御下で百%を引き出せば、十中八九結構なダメージを受ける。それでもやるか?」
『はい!』
「よし! それでこそ俺の犬だ! じゃあまずは筋力のみの百%からやっていくぞ!」
『は……。え? まずは?』
ちょっぴり嫌な予感がしたが、え? と思ったときにはもう僕の身体は後ろ足を捻って膝を絞り、体重を乗せた拳を放っていた。
うおんと空気がうなりを上げ、空へと続いていた魔力板がパリンと音を立てて割れた。筋肉にビリビリと痺れるような痛みが走る。
『技能「限界突破」を検知しました。技能LVを計測します』
「一〇二五枚。まぁまぁだな」
「よし、次は強化を使うぞ!」
オルナダ様が消滅した魔力板を再生し、僕の身体は再びモーションに入る。
全身の筋肉、筋繊維の一本一本に魔力が巡り、身体が淡く青白い光を放つ。筋肉が内側から押されるような、圧迫感のある痛みが全身に広がる。こんなに強化したら、地面が僕の力に耐えられない。踏み込めば泥濘みたいに沈んで、足の踏ん張りが効かないはずだ。だけど流石と言うべきか、踏み込んだ足の下には魔力板が生成されて、全身のバネが生む力が淀みなく拳に乗る。
「これが、お前が耐えられる限界の身体強化を加えた身体で放つ、全力パンチ!」
『う、うわわわわわわわわわわっっっっっ!!』
パンッ!! と乾いた音がして、魔力板がごっそり消える。雲のすぐ下にわずかに残った魔力板が数枚、遅れて割れて落下し、煌めく塵になって風に飛ばされていく。
「六九九八枚。良いな、想定より多く割れている」
「うははははは。気持ちが良いくらい、魔力乗りの良い身体だな、フューリ! 魔族以外の種でこれほど魔力が身体に馴染む者はそうはいないぞ!」
オルナダ様と僕の身体は上機嫌に成果を褒めてくれるけど、僕は身体の痛みでそれどころではない。魔力系が焼け、筋繊維が断裂し、骨が軋んでいるみたいだ。
『技能「最大拳砲」を検知しました。技能LVを計測します』
「言うまでもないと思うが、この技能は実戦では使うなよ。加減を間違えると、全身に大ダメージを受けるからな」
『み、身をもって実感してます……』
筋力強化は魔力を筋肉にある魔力系に流すことで、筋力を何倍にも引き上げてくれる魔法だけど、魔力量の加減を間違えると筋繊維や魔力系が破裂してしまう。そのためイラヴァールの戦闘訓練では、筋力強化は痛みを感じない程度に留めるようにと教えられるのだけど、オルナダ様は僕の身体が壊れないギリギリのところまで強化を使ったらしい。身体は動かせているので、筋肉が破裂したりはしていないのだろうけど、全身に痛みがこびりついて離れない。
「さて、次が本番だが……」
『ま、まだやるんですか!?』
「まだ魔装を使ってないんだから当たり前だろ」
『で、でも、魔装って力に関係ないですよね? なんというか装備品みたいなものなんじゃ……』
「わはは。それは盛大な勘違いだな」
僕の中のオルナダ様は、僕の身体の筋を伸ばしたり、関節を回したりしながら、愉快そうに笑った。
「魔装ってのは密度を上げて実体化させた魔力を身に纏い、重さのない鎧を着用したかのように攻防力を上げる技だが、その真髄は纏った魔力の操作にある。お前が強力なパンチを打つなら、さっきみたいに筋力を強化して打つだろうが、同じ威力のパンチを強化に耐えられない肉体の者が打つ場合どうすると思う?」
オルナダ様が静かに僕の身体に歩み寄って、顔を見上げて尋ねる。
話の流れからすると、強化は使わずに身に纏った装備を操作して、パンチの動作をさせるということなんだろう。中身が空っぽでも動くフルプレートアーマーの中に人が入っているイメージを思い浮かべると、僕の身体が「正解だ」と笑う。
「鎧のほうを動かせば、強化の限界を超えた動作が可能になる。だが、誰でも簡単にできるってわけじゃないぞ。理屈は単純だが実戦で使うには、それだけのパワーとスピードで鎧を動かせるだけの操作力、その反動から身体を守れるだけの身体強化力、身体の限界を見極める肉体感覚、その他諸々の技術が要求される。それをただでさえ高難易度の魔装を維持した状態で自在に操るとなると、その難易度は天井知らずだ」
静かに語りつつ、僕の身体は体内に魔力を巡らせ始める。筋力強化とは違い、筋肉だけではなく、全身のあらゆる部位に魔力が流れ、身体がふにゃふにゃと柔らかくなるような感覚が沸き起こる。身体強化と言えば皮膚の硬化が定番だけど、この強化はまるで逆だった。
そうして柔らかくなった全身から染み出すようにして、ぬるま湯のような魔力が身体の表面を覆い、その上に魔装が形成されていく。僕がこれまで作り出した魔装に比べ遥かに高密度で生成された魔装は、キンキンキンと甲高い音を立て、まばゆく青い光を放つ。
「ふはは。触れただけで吹き飛ばされそうな密度だな、それが限界か?」
「まだ上げられるが、これ以上は維持が難しい。やってもいいが、見る間に魔力がなくなるぞ」
「ふむ。まぁ、インパクトの瞬間に最大にすれば良いだろう」
「ふふん。無論そのつもりだ」
オルナダ様と僕の身体は、目を合わせ、お互いに口の端を持ち上げた。
「いくぞ、フューリ! 魔力の流れ、身体の流れ、すべて頭に焼き付けろ!」
『は、はい!』
魔装を操る僕の身体は、これまでとはまったく異なる動きをみせた。
全身脱力してどこも動かしていないのに、身体がとてつもない速さでパンチを打つ。足の下の地面にまで範囲を広げた魔装によって、しっかりと踏ん張りを効かせた動作で拳を振り切る。拳が魔力板に触れる直前、全身の魔装に回していた魔力が、渦を巻くようにして脚から腰、腰から腕へと流れ込む。身体の回転と突き出す拳が急加速する。今度は叫ぶ暇もない。
「これこそ魔装の真髄!! 正真正銘、お前の全力全開パンチだ―――――!!」
ズガドンガシャ―――――ン!!
魔装が一層強く輝き、まるで雷が落ちるような爆音が轟く。魔力版の列が衝撃波を緑色に染め共に掻き消えて、幾重にも重なった放射状の波動が周辺の空気と雲を吹き飛ばす。鈍色の空に円形の青空ができて、僕の全身には身体がバラバラに千切れるような痛みが走った。魔装が解け、ぶわわっと音を立てて、纏っていた魔力が飛散する。ぐるんと視界が天に向いて、後頭部に鈍痛を、耳の奥にはぁはぁという自分の荒い呼吸を、全身に猛烈な倦怠感を感じた。
『ユニーク技能を検知しました。技能LVを構築します。技能の名称を決めてください』
「ふい~~~~~。いやぁ、出し切ったなぁ、もうすっからかんだ……。あ~~~~~、この空っぽ感、たまらんなぁ。魔族の身では味わえない感覚だ……」
ステータスボードが告知をすると、僕の身体は満足そうにつぶやいて、仰向けに倒れ動かなくなった。完全に魔力を使い切ったらしい。鼻から入り込んでくる甘い香りに、頭がぐわんと揺らされる。
「うお。なんかクラ~ン、フワ~ンみたいな感じがするぞ。おぉ、もしかしてこれが、お前の言う魔香酔いか?」
『そ、そうですね。この感じはそうだと思います』
「うはは! お前の鼻で嗅ぐと俺はこんなに良い匂いなのか! しかも嗅ぐと気持ちよくなるとかヤバイな! お前は俺のことを好きすぎると思ってたが、これじゃ俺の虜になって然るべきってもんだな! わははははは!」
『おわかりいただけましたか! そうなんですよ、しょうがないんです! えへへ!』
僕と僕の中のオルナダ様は、オルナダ様の香りに酔って、すっかり気分が良くなってしまった。たぶん酔って紅潮しているだろう僕の顔を、オルナダ様がちょっぴり呆れたような顔で見下ろした。
「おいおい、俺が酔っ払ってどうする……」
「別に良いだろ、楽しいぞ! しっかしこうしてみると、やっぱ麗しいなぁ、俺。そうだ、酔いを覚ましたいなら魔力をよこせ、チューだ、チュー! ん! ん!」
僕の身体は寝転がったまま、にゅっと唇を尖らせて口付けをねだる。元よりそのつもりだったのか、オルナダ様はふふっと鼻を鳴らして、僕の横に膝をつき、長い髪を耳にかけて唇を落とした。唾液がとろりと舌を伝い、口内に流れ落ちてくる。普段は口の中に甘い香りが広がるように感じられるのだけど、今は魔力が空になっているせいか味まで甘い。粘度の低い蜂蜜みたいだ。
美味しくて、もっと飲みたくて、オルナダ様の舌にむしゃぶりつきたくなるけど、身体の操作をしているのは僕の中にいるオルナダ様なので、思うようにはならない。けれど、いつもしているより気持ちが良い。唇と舌の動かし方、吸い方、絡ませ方、どれもがお互いにしてほしいことをわかっているみたいに息が合っている感じがする。オルナダ様同士なんだから当たり前なのかもしれないけど、僕は酔いが覚めるに従い「僕ってば飼い犬なのにキスも満足にできてなかったのか!」と落ち込んでくる。そしてさっきの魔装パンチより深く、舌と唇の使い方を頭に刻み込もうと意識を集中した。
「ふはぁ。どうだ、回復度合いは?」
「ふーむ、八分の一ってところだな。汁すするだけで回復するのは便利だが、唾液じゃこんなもんか……。次は半分でやるから八割くらいにしてから望みたいが……」
『え。ま、まだやるんですか? 全パターンで?』
「そうだ。終わる頃にはなににどのくらいの力が必要か、身体がふんわり覚えるはずだ。あとは自分で反復練習だな。まぁまずは回復だ。おい本体、上に乗れ」
『え!?』
「はぁ……。見た目はフューリでも、中身が俺だと可愛くなくなるもんだな……」
オルナダ様はため息を吐いて指を鳴らし服を消す。僕は「自分のパワーなんてあんまり知りたくないし、結局最後は反復練習になるなら、ここでやめても良いのでは?」と思ったけど、黙ってオルナダ様におまかせすることにした。
回復後、五十%を三種類打って、また回復して二十五%を打つ。さらに半分、また半分と威力を下げて、途中から魔装や強化は使わなくなり、普通のパンチだけになった。
「で、一枚だけならこのくらいだ。どうだ? 大体掴めたか?」
『は、はい! えへ、えへへ……』
「おい……、そろそろシャキッとしろ。次は自主練のやり方な」
僕の中のオルナダ様は嗜めるように言って、この訓練に使っていた魔力板の作り方を教えてくれる。
魔力というものは、密度を上げることで実体化し、それなりの強度を持った物体になるそうで、魔力板もその性質を利用して作っているらしい。原理を解説しながらオルナダ様は僕の身体を操り魔力板を作り出し、さっきまで割っていた魔力板がどの程度の密度で生成されているかを実践してくれた。使用する魔力はだいたいオルナダ様を六人同時に浮かせる程度の量だった。
『技能「魔力盾」を検知しました。技能LVを計測します』
「魔力板はこうして魔力を集めて生成するが、聞いての通り、通常は盾として利用する場合が多い。より多くの魔力を集め密度を上げることで強度を増すことができる。だが一定以上の密度になると魔力同士が反発して離散するから、そうならないギリギリの密度で生成するんだ。だいたいこのくらいだな」
僕の身体はすっと左手を上げて、すぐ割れる魔力板の隣に、最大強度の魔力板を生成する。形状は変わらないけど、色味が濃く放つ光も強いし、若干厚みが増していて、見た目にもこちらのほうがより強力だとわかる。生成に必要な魔力は、さっきの千五百倍よりちょっと多いくらいだろう。
「この密度なら大抵の攻撃は防げるが、足りない場合は枚数を重ねるんだぞ」
『密度を上げるのはダメなんですか?』
「離散しようとする魔力を留めておくのは、困難な上に無駄に魔力を消費するからな。単に魔力板を作るだけなら限界強度のをたくさん作るほうが効率が良いんだ。ちなみにそうやって無理矢理、魔力を留めて密度を限界以上に上げる技が魔装な。自覚がないんだろうが、並の制御力では実現できない技なんだぞ」
『え。魔装ってそんなに難しいんですか?』
「まがい物を数秒程度なら誰でも作れるが、実用に耐えるレベルとなると、かなりの難易度だな。ともかく魔力板は足場に防御にと応用の幅が広いから、力加減の練習用だけじゃなく、実戦で使えるものもパッと作れるようにしておけよ」
『は、はい!』
「ん。あとは『捕食者の気配』だったか? あれはこうするか、あるいは、こうすれば一時的に消えるぞ」
僕の身体はそう言うと、身体の周りに漂っている冷気のようなものを感知して、半分を魔力で包んでみぞおち辺りに圧縮し、残りの半分を魔力で弾き飛ばしてみせた。力のコントロールや魔力板の説明に比べるとあまりに短い。でもそれで十分再現できそうなほど単純な操作だったし消費魔力も微々たるものだった。
『こ、こんなに簡単だったなんて……』
このままじゃ一生、シシィ以外に友だちになってくれる人なんてできないんじゃないか。と本気で悩んだ時間はなんだったのか。身体の操作権があったら地面に手をついていただろうというくらい、僕は脱力してしまう。
「わはは。知らないって損だろう? もう少し魔法を学んだほうが良いぞ」
『……そうします』
僕の身体はケラケラ笑って、空中に生み出した水を口に放り込んだ。
魔法はまったく得意じゃないけど、今後は基礎訓練以外にも魔法の実習をとるようにしようと固く誓った。
「さてと、最後はヒーゼに言われてたお前の寂しんぼ対策だが、そんなの必要か?」
『必要です! すごく必要です! むしろそれが一番必要ですから、それだけはなんとかお願いします!!』
オルナダ様が僕の身体に歩み寄って、聞き捨てならない発言をしたので、僕は真剣かつ必死に訴える。
「そ、そうか……。しかしヒーゼの話じゃ、古くなった野菜みたいに萎びてるはずだが、お前、どう見てもツヤッツヤしてるぞ?」
『それは今、オルナダ様と一緒にいられているからです! 昨日まではカラッカラでしたよ! それはもう、前日に焚いた薪みたいでしたから!』
「それじゃ〝萎びてる〟じゃなくて、〝燃え尽きてる〟だろう。ふーむ……。しかしなにをしてやったら良いか……、ずっと張り付いているわけにもいかないし……」
『そう、ですよね……』
わかってはいたけど、ガックリしてしまう。ほとんど国王のような立場のオルナダ様が、いつまでもランピャンに居てくれるわけがない。きっと僕の悩みをさくっと解決したら、さらっとイラヴァールへ帰ってしまうんだろう。それを思うと途端に寂しい気持ちがぶり返してきた。
「こういうのはどうだ、本体」
顎に手をやるオルナダ様に、僕の身体が腰のポーチから取り出したスライムシートを広げて見せた。オルナダ様は「なるほど、流石は俺」とつぶやき、スライムシートに施された魔術を解いて、元のスライムに戻す。
くるみほどのサイズの小さなスライムは、僕の身体に身体の端をつままれ、そこから逃げ出そうと、うねうねもがく。オルナダ様は暴れるスライムの体内に、魔法で紐状にした足元の砂を次々と送り込んでいく。スライムは砂を吸収するにつれ大きくなり、オルナダ様の背丈ほどの大きさになる。
「このくらいで良いか。そうだフューリ、身体返すぞ。しっかり立ってろよ」
『へ? おっ、とと……っ』
唐突にオルナダ様は僕の中にいたオルナダ様を回収して、僕の身体は一瞬力を失い、ガクンと崩れそうになった。僕はなんとか転ばないように踏ん張って、なにか魔法を発動させようとしているオルナダ様を見る。
なにをしているのかはわからないけれど、きっと高度な魔法を使っているのだろう。オルナダ様の周りには、赤く発光する複雑な模様の魔法陣がいくつも浮いている。魔法陣はゆっくりと回転しながら、時折一部の文字や図形が高速で変形し、次々と別の魔法陣に変わっていく。さっきまで僕の身体がつまんでいたスライムが宙に浮き、その内部に流し込まれた砂が球体になり固まった。球体はスライムに吸収されず、内部に留まる。
オルナダ様は「こんなものか」と魔法陣を眺め、パチンッと指を弾いた。魔法陣がスライム内部の球体に吸い込まれていく。目を開けていられないほどの強い光がスライムを包み、そして弾けた。スライムが浮いていた場所には、裸のオルナダ様が浮いていた。
「うむ。ばっちりそっくりだな。コレがあればお前の寂しんぼも紛れるってもんだろ」
「は? え? えええ!?」
オルナダ様が二人いる。ひとりは本物のオルナダ様で、もうひとりはスライムから作った人形なのだろうけど、あまりにそっくりで僕は混乱した。そしてそんなものをポンと与えてくれるということにも。
確かにこんなにそっくりの人形を側に置けたら、多少は寂しさも紛らせられるだろうけど、さっきまで周り浮いていた魔法陣の数から察するに、きっとまた国宝級なんて言われるようなとんでもないアイテムに違いない。
「見た目だけじゃなく、質感もかなり実物に近づけてあるから、さほど違和感はないはずだ。核もここで作れる最高強度に仕上げてあるから、かなりの衝撃にも耐えられる。ただしスライム製だから火気厳禁な。……って、おい、早速使う気なのか? どすけべめ」
「? と言いますと?」
僕が浮いてるオルナダ様型スライムの前で上着を脱いでいると、得意げに説明していたオルナダ様が急にニタニタとした。
「照れるな照れるな。ここまでそっくりだと、今すぐ試したくなるのも当然だ。俺も遊んでみたくなるくらいの出来だしな」
オルナダ様はわっはっはっと空を仰いで笑うけど、僕にはイマイチ言葉の意味がわからない。このまま裸で浮かせておくわけにもいかないので、僕はオルナダ様型スライムにさっと上着をかけて自分の魔力で浮かせ、イラヴァールにある小屋へ移すために転移ロープを準備した。
「んむ? なんだ、持って帰るのか? 使うならここで使うと良いぞ。せっかく作ったし、お前がそれに盛るところを見たい」
「えぇと、でも……。元がスライムとはいえ、オルナダ様の形をしているものを、こんな砂漠の真ん中で裸にしておくわけにもいかないですし……。というか、その〝使う〟というのは……?」
「うん? そりゃあ×××××を×××××に×××××で×××××とか、×××××を×××××させて×××××に×××××だりとかだろ」
あっけらかんとしたオルナダ様が語る言葉に、僕はぐぶふっっっと噎せてしまう。
「ぶほっ!! げほっ!! じ、じゃあこのスライムって、その……。そういうところまでそっくりに……?」
「うむ。まぁ汁は出ないから、油かなんか使う必要あるけどな」
聞き間違いであってほしかったけど、残念ながら、おかしかったのは耳ではなく言葉のほうだった。ボッと頭が火の玉みたいになって、思わず顔を覆った。
なんてものを作るんだこの人は。そして僕になにをさせようとしているんだ。しかも目の前で〝使え〟なんてそんな、とんでもないにも程がある。
「…………て、ください……」
「うん?」
「見た目をもっとスライムっぽくしてください!」
「んなにぃ? おま……、ここまでそっくりにするのがどれだけ難しいか……」
「本っ当に申し訳ございません! 僕もきっとそうだろうなとは思っていたんですが、元がスライムとはいえ、こんなにオルナダ様にそっくりでは〝使う〟なんてとても無理なので……」
「はぁ? なぜだ!」
「だってこのスライム製のオルナダ様人形は、話しかけても返事をしてはくれないんですよ? ということは、僕がマッサージをしたくなったりとかしたとしても、
「脚をお揉みしてもよろしいですか?」
「…………………………」
「……今日は冷えますから、毛布をお持ちしますね。おやすみなさい」
みたいな感じになって、僕は本物のオルナダ様にも、スライムのオルナダ様にも触れられずに、枕に噛み付いて眠ることになるんです! そうに決まってます!」
「メンドクサイ上に、気色が悪い!!」
オルナダ様型スライムを魔法で操作して小芝居をする僕に、オルナダ様はつばが飛ぶほどの激しいツッコミを入れる。
でもそう言われても仕方がない。オルナダ様人形は喉から手どころか、全身が生えて強奪に走りそうなほどほしいけど、こんなにそっくりに作られていては、鼻と頭でスライムとわかっていても、スライム扱いなんてできるはずがない。もらって帰るなんて、とてもできないのだ。
僕は「お願いします」とオルナダ様に、努めて真剣な眼差しを向ける。オルナダ様は不満そうに唇を尖らせつつも、すっと手のひらを人形に向けてくれた。人形は作られたときと同じように強く光り、ひと目でスライムとわかる、青い半透明の身体に変わる。しかし細部の再現度は健在であるため、まつ毛や髪の毛の一本一本まで、綺麗にスライムっぽく塗った本物のオルナダ様のようにも見える。
「これで良いんだろ? まったく、俺の渾身の作品が気に入らないなんて。ぷいぷい」
「あ、いや、決して気に入らなかったわけではないんです。むしろ素晴らしすぎてとても頂けないというか……。もしもらってしまったら、一日中眺めて過ごすことになって、部屋から出られなくなったりとかしそうで……」
「む。確かにあの出来では、そういうこともありうるか。それは困るな」
僕が正直なフォローを入れると、オルナダ様は多少機嫌を直してくれた。
「ふむ。残念だが仕方がないということだな、残念だが。まぁ、だいぶスライムにしたし、もう大丈夫だろう? 持って帰って良いぞ」
「は、はい……」
「なんだ? まだなにか不満があるのか?」
「い、いえ、そんな、不満なんて……。ただ、お召し物をどうしようかと思って……」
「んなモンいらんだろ。スライムだぞ?」
「いりますよ! そんな、裸で置いておくなんて、とんでもない! オルナダ様に相応しい、快適で高級感のある衣類が絶対に必要です!」
オルナダ様には言えないけれど、今の状態でもまだ僕にはスライムというよりオルナダ様に近いように見える。持ち帰るなら、きちんとした服を着せて、居心地の良い祭壇を作ってお祀りできるようにしなくては。
「ったく。意外と注文の多いヤツだな。ほら、これでどうだ?」
「は? え? えええ!?」
オルナダ様はパチンと指を鳴らして、スライム人形にイラヴァールの黒服を着せてくれた。それは良いのだけど、今まで着ていたものを着せて、自分は裸になってしまうものだから、僕は面食らってしまう。
どうしてこの人は、こうも気軽にポンポン服を脱ぐのか。僕は急いで人形に掛けていた上着を取って、オルナダ様に駆け寄った。オルナダ様は僕の意図を察したようで、またパチンと指を鳴らして服を元通り自分に着せる。当然人形のほうは裸になってしまうので、僕はくるりと踵を返して上着を掛けに行く。するとまたパチンと音がして人形に服が着せられ、振り返るとオルナダ様が裸になっている。オルナダ様へ駆け寄ると人形が裸になり、人形に近付くとオルナダ様が裸になる。僕は二人の間を上着を持って、おろおろと行ったり来たりする羽目になった。遊ばれていると気付いたのは、二十往復もしてからだった。
「…………僕で遊ばないでほしいです……」
「ぶはは。そんな面白い行動をするほうが悪い」
唇を噛み締めて訴えると、オルナダ様は愉快そうに笑って、ようやく両方に服を着せてくれた。無駄に疲れた僕は、ふぅと息を吐いて上着を羽織り人形を抱きかかえる。人形が着た服からはオルナダ様の匂いがした。ドキリとしつつ転移ロープをくぐってイラヴァールにある小屋へと人形を連れ帰り、取り急ぎ台所にある椅子をスライムシートで拭いて、そっと座らせた。
眠っているオルナダ様を青い塗料で塗ったようなスライム人形は、まるで眠っているみたいにだらりと腕と頭を下げる。そのままでは首が痛そうなので、テーブルに伏せた姿勢に替えて、顔にかかる髪を避けてやる。スライムとはいえ、その横顔がとても綺麗なものだから、服から香るオルナダ様の匂いも相まって、なんだかイケナイことをしているような気分になってしまう。
というか、勝手にしたらいけないようなコトをしてしまいたくなる。
「いやいや! オルナダ様にそんなコトしたらダメだぞ、僕! あ、でもスライムだから、スラナダ様、かな?」
ぷるぷると首を振るも、甘い香りに誘われて振り返ってしまう。
ほっぺにチュウくらいなら、許されるだろうか? そろそろと上から顔を覗き込んで、恐る恐る唇を寄せた。ぷるりとして冷たい、完全にスライムの感触だったけど、なんだか本物にするよりも気恥ずかしい気持ちになって、僕はさささっとスラナダ様から離れる。服の残り香も嗅ぎたかったけど、それはやめておくことにした。
「帰ったら綺麗に拭いて、寮のベッドに移しますから、しばらくはここで我慢してくださいね」
そう声を掛けて、そそくさとオルナダ様の元へ戻った。すぐに戻ったはずなのに、オルナダ様はニヤニヤとして「どうだった?」とスラナダ様についての感想を求めてきた。どうしてバレてるんだろう? と思いつつ、僕は小屋でやらかしたことを打ち明ける。
「それだけか? 無欲、いや、照れ屋なのか? もっと色々して良いんだぞ?」
「う……。じ、じゃあ、今度は匂いを嗅がせてもらいます……」
「匂い? あぁ、服のか? あの制服は自浄効果があるから、匂いなんかすぐなくなるぞ?」
そういえば、イラヴァールの制服には様々な魔術が施されていて、丈夫で体温調整に優れるだけでなく、汚れにも強いのだった。聞くところによると、年単位で洗わずにずっと着ていても臭わないらしい。清潔な身体で数時間着ただけの残り香なんて一瞬で消してしまうのだ。僕はさっき制服を思い切り嗅いで来なかったことを激しく後悔した。
「人狼とか犬系の獣人は、飼い犬になると飼い主の匂いに快感を覚えるようになるらしいが、お前もそうなのかもな。パンツや靴下が特に好まれるという話だが……」
「パ!? いや、その、それはさすがに……」
「ん? さすがに下着じゃ匂いがキツすぎか?」
「そ、そうではなくて、その……。ヒ、ヒューマー圏では他人の下着に盛るのは忌み嫌われる行為なので……、なんというか道徳的にアウトと言いますか……」
「そうか。まぁそこは魔導圏も同じだが、となるとなにをくれてやったら良いか……」
「えと……、そんなことで悩まれると申し訳ないので、あの……。あ! そ、そういえば、相談事を解決していただいたので、僕はそろそろみんなと合流しないといけないと思うんですが……」
真剣な表情を浮かべるオルナダ様に、なんだかいたたまれない気持ちになった僕は、強引に違う話題をねじ込んだ。幸いにもオルナダ様は「そういえばそうだったな」と頭を切り替えてくれた。
「うーん、今どの辺だ? おぉ。ちょうどヒーゼのダンジョンに入るところのようだぞ。良いタイミングだな」
こめかみに指を当てたオルナダ様が、表情を明るくして反対の手の指を弾く。目の前にあった砂漠の光景が、巨大な白い塔に変わった。
第二十一話公開しました。
魔力の性質はだいぶ悩んで作っています。
「魔装は高度な技である」という設定のために高密度になると分散しようとするって設定にしたので、必然的に、螺旋丸なら使えるけど、かめはめ波は、難易度が高い上に効率も悪いから誰もやらない技みたいになってしまったりしています。フューリのかめはめ波はやらせたい気もするんですけどね。
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!