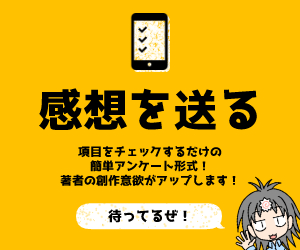沖ノブ(ノブ沖)で評判の良かった、同タイトル小説のオリジナルリメイク版です。
完成したら表紙付けてkindleで出版する予定。プライスマッチが通ったら無料、通らなかったら99円になると思います。
ハイエナ適用で性別のない世界観になっている点だけご注意を。
沖ノブ版はこちらへ。
あらすじ
ある事件をきっかけに、大の仲良しだった和田と疎遠になってしまった中学生、槙田。
人気者ぶりに磨きのかかった和田を遠くから眺める日々の中、熱中症でダウンしていたところを和田に助けられ、恋心を自覚してしまい…。
以下から本編です。
五
練習が終わり、部室に鍵をかけて、剣道場を後にする。私も含めた剣道部員たちは、制汗剤の匂いを廊下に振りまきながら、昇降口へ向かう。
途中、部活をサボった岡村が、生徒会の仕事で部活を休んでいた、{坂上|さかがみ}先輩と立ち話をしているのが見えた。声をかけて駆け寄った。それとなく、例の指輪についての話を聞いてみようと思ったのだ。ところが、私が話し始めるよりも先に、後ろにいた先輩たちが、大きな声で二人を茶化しだした。
「お前らー、二人でサボってデートかー?」「ちゃんと告白したんか、岡村ー?」「どこまでいったんじゃー?」
「じゃけぇ違ぇー言よーじゃろうがー!!」
岡村が、バッと私の横を走り抜ける。先輩たちは笑って岡村を囃し立てながら、バラバラの方向へ走り去った。岡村は一瞬迷ってから、そのうちの一人を追いかけて走り出す。後には、坂上先輩と、私と、後輩の{楠家|くすいえ}が残された。
岡村と坂上先輩は、いわゆる幼馴染。家が近所で、登下校も一緒なためか、よくこの手のネタでからかわれていた。岡村がいつも、真っ赤になって怒り出すのが面白いからという理由もあるだろう。
ただ仲が良いだけなのに、こんな風にからかわれる二人を、私は少なからず気の毒に思っていた。「災難でしたね」という私に、先輩は「まぁ、いつものことだからね」と苦笑いを返した。
「さっさと付き合ってるって言っちゃえば良いのに、岡村先輩があんなだからこうなるんですよね」
隣にいた楠家が、ずいぶん見当違いな発言をした。私たちはまだ中学生だし、岡村は小学校の頃と変わらず、悪ガキ然としている。落ち着いている坂上先輩はともかく、岡村はレンアイなんて大人なものとは、縁遠い。ここは、たしなめた方が良いだろうか。私が一瞬悩んだ間に、「あれもカワイイところのひとつだから、僕は待つつもりだよ」と、先輩が優しい笑みを浮かべた。
ん? あれ? 言い回しがちょっと引っかかる。
「え? あの……、その……、ふ、ふたりって、本当に……?」
遠慮しつつ聞いてみると、先輩ははにかんで頷いた。
「気付いてないの、槙田先輩だけだと思いますよ」
口を開けたまま固まった私に、楠家が呆れたみたいに言う。さらに「槙田先輩が気付かないから、岡村先輩も隠せてる気になってるんだと思うんですよね、私は」と続けた。え? なにそれ? 私が悪いんですか? 先輩に目を向けると、困ったみたいに笑われた。
衝撃的な事実を知ってしまった。私は呆然としたまま家に帰った。
なにがショックなのかはわからないが、とにかくショックだった。
だって岡村は、ロップや私と一緒に、バカな遊びやイタズラをして回った時となにも変わっていない。そりゃあ、背は伸びたし、胸が膨らんできたりもしてる。でもそれは、私だって同じだ。私はあの頃と大差ない。変化らしい変化といえば、剣道を始めて少し体力がついたことと、ロップと遊べなくなったことくらいだ。それなのに岡村は、レンアイを覚えたばかりか、相手が坂上先輩なんて。確かに、一般的には、私たちはそういうことに興味を持ち出す年頃だけど、一体なにをどうすればそんなことになるのか、さっぱり理解できなかった。
ひょっとすると、変わってないのは私だけで、他の子たちはどんどん変わっていってるのかもしれない。それは、たぶん、ロップも。
「ロップにも、付き合ってる子とか、好きな子とか、いたりするんでしょうか……?」
なぜだか急に、悲しくなった。
自室のベッドに転がって、柴犬のぬいぐるみを抱きしめる。
昔のロップは、どこに行くにも一番に私を誘ってくれた。だけど今は、おしゃべりすることさえない。今日はたまたま保健室で話せたけど、あんなのは滅多にないことだ。今のロップには、昔よりもずっと沢山の子分とファンがいるし、バンドのメンバーともすごく仲が良さそうに見える。ロップの一番の仲良しは、私だったはずなのに。
目がじわっとした。それもこれも、五年生の時の、あの事件のせいだ。
私は、校庭にドッジボールをしに行くロップの背中を追いかけて、階段から落ちた。
正確に言えば、落とされたのだ。今日、クラスメイトの一人が言っていた、階段から突き落とされたファン、というのは私のことだ。おでこを何針か縫うことにはなったけど、体感的には大したことはなかった。だけど、ロップはすごく怒って、大人も手がつけられないほどだったらしい。相手の子は病院送りになるほど殴られた。同時に、とてつもなく恐ろしい脅しをかけられたとかで、家族で夜逃げ同然に街を出たそうだ。
私が階段から落ちなければ、後ろの気配に気付いていれば、押してやろうと思われるようなひ弱な存在でなければ、こんなことにはならなかった。あの後しばらくロップが一人きりになったのも、今のロップがあんな風に振る舞うのも、きっときっと私のせいなのだ。
ギッとおでこの傷跡に爪を立てる。
全部なかったことになって、元通りになれたらいいのに。ずっとそう思っていたのに、現実は戻るどころか進んでいる。あの岡村に恋人がいるのだ、ロップにもいたって不思議じゃない。不思議じゃなけど、でもすごく嫌だった。胃がザラザラとする。
もう元には戻らない。そんな気持ちを振り払いたくて、私は今日の保健室でのことを思い出す。
今日のロップは、以前と変わりないように思えた。華奢で小柄なのに、どことなく貫禄があって、頼りになって、優しい。私を軟弱者扱いするけど、その代り、ヘバったときにはいつも、抱っこやおんぶで運んでくれるし、頭を撫でてもくれる。こんなことは他の子にはしない。中学生になってからも、他の子にしているところは見たことがない。
「…………うん、見たことない。ないですとも!」
記憶をひっくり返して、見たことがないと確認すると、ちょっとだけ自信が湧いた。
やっぱりロップの一番は私だ。きっと今だってそうだ。だから保健室に連れて行ってくれたし、おでこで熱も計ってくれたのだ。
私はぬいぐるみを抱いたまま起き上がって、自分を納得させるように、うんうんと頷いた。ふと、ロップのおでこと手の平の感触が蘇り、口元が緩む。話すのも久しぶりだったけど、ああいうのはもっと久しぶりだった。あんまり久しぶりだったから、変な感じがしたっけ。雷に打たれたような感覚というのは、ああいうのをいうのかな。
と、ここまで考えて、あれ? となった。
そういう感覚というのは、ショックを受けたときに起きるもののハズだ。でもアレにショックなところなんてない。ショックというなら、岡村と坂上先輩が付き合っていたことの方がショックだ。じゃあアレはなんだったんだろう? レンアイ的な衝撃でも起きるらしいけど、私にはそういうのはまだ早いから、それはないだろう。いや、岡村に恋人がいることを思うと、早くはないか。むしろ遅れをとっているわけだし。いやいやいや、早いか遅いかは関係ない。大事なのは、私がロップに対して、そういう気持ちでいるわけじゃないということだ。第一レンアイ的なものだったら、こう、心臓がドキドキしたり、顔が熱くなったり、といった反応があるはず。知らないけど、レンアイはそういう風になるらしい。私は単にちょっと、ビリビリしただけ。大丈夫、大丈夫。ロップは私にとって、ただ一番大好きな――。
「……………………え?」
頭の上に、雷が落ちた。
でなければ、スタンガン的なもので攻撃された。
そうとしか思えないほどの、光とも、音ともつかない、強烈な衝撃が、全身を駆け抜けた。身体の芯から外側へ、じわじわと熱が伝わり、胸を突き破るんじゃないかと思うほど、心臓が脈打つ。頭は勝手に、ロップとの思い出を、超高速でジグソーパズルのように並べて、一枚の絵を組み立てようとする。
だめ。いやだ。やめて。
止めようと思っても遅かった。パズルは一瞬で組み上がってしまった。
私は、ロップが好きなのだ。
違う、違う、そうじゃない。そう言い聞かせてみても、ロップとのあの時やこの時が、ぐるぐるぐるぐる、頭を駆け巡る。色んな遊びをした山歩き、並んで食べたアイス、公園のタコでの雨宿り、繋いだ手の温もり、くすぐり合いっこ、そんな楽しかった日の思い出から、今日のロップまで。どんな記憶も、心拍数と体温を上昇させた。中でもひときわ私を困惑させたのは、今日の、保健室での記憶だった。ロップはタオル代わりに、自分のシャツを私にくれた。シャツを脱いだロップは、黒いスポーツブラをしていて、胸はもう、真っ平らではなくて、白い素肌は……。
「わぁーーー!! やめ、やめ……!! というか、なにしれっと服脱いでるんですか、ロップのバカァ!!」
わー、ひゃー、きゃー、となって、ぬいぐるみを壁にぶん投げ、ジタバタ転げ回ってしまった。暴れすぎて、壁に足をぶつけた。「{悠里|ゆうり}! うるさい!」、隣の部屋の姉から、苦情の声が上がった。
寝転がったまま、自分の膝を抱きしめて丸まる。頭の中は、半裸のロップの身体と、触れられたときの感触、それから、熱を計ろうと近づいてくるロップの顔でいっぱいだ。思い返したシーンは、まるで、キスでもされそうなイメージになっていて、「なんてことを、してくれたんですか!!」と、叫びたくなった。一体、明日からどんな顔をして過ごせば良いんだろう。ちらりとカバンを見て、余計なことに気がついた。中に、もらったシャツが入っているのだ、と。
世の中には、好きな子の縦笛を舐めたりする子もいるらしい。マンガやアニメなら笑えるけれど、現実には、控えめに言って気持ちが悪い。私はそういう子たちが、なぜそんなことをするのか、さっぱり理解できなかった。さっきまでは。だけどもう、わかりたくないけど、わかってしまった。今、私は、あのシャツに、ちょっとくらい、ロップの匂いが残ってるんじゃないかと期待している。もちろん、そういうつもりで持って帰って来たんじゃない。普通に、本当に普通に洗って返そうと思っただけだ。でも、アレに顔を押し付けたら、そう思うとドキドキしてしまう。
私はガバッと起き上がって、カバンを持って洗面所へ走り、シャツを洗濯機に放り込んで蓋を閉めた。すごく、すごく、惜しいことをした気がした。けど、もしさっき頭に浮かんだことをやってしまったら、あの猿みたいなクラスメイトたちと同じになってしまう。そんなのは、ロップに申し訳なさすぎる。
その晩、私は一睡もできずに、あー、とか、うー、とか唸りながら、回想と、妄想と、ロップのシャツへの思いに悩まされ続けた。
六
それから数日、私はボロボロだった。夜はあまり眠れないし、起きている間は、四六時中ロップのことで頭がいっぱい。半分眠っているような、夢の中にいるような、フワフワした感覚が続いて、部活にも、授業にも集中できない。いつも無意識に辺りを見回して、ロップの姿を探してしまう。探すくせに、見つけると、心臓が破裂するかと思うほど、激しく高鳴るので、その度、早く視界から消えてほしいと祈ることになる。ロップが誰かと一緒だと、それに、胃と肺を一緒に握り潰されたみたいな痛みがプラスされる。そしていなくなると、今度は寂しさに襲われる。その繰り返しだった。
「ため息多いのー。便秘かー?」
「……食べてるときにやめてくださいよ」
昼休み、お弁当に箸をつけられずにいると、岡村に声をかけられた。
「全然食っとらんじゃろー。あれか? 都会のもやしっ子特有の夏バテっちゅーヤツか? おかずの処分、てごしちゃってもええぞー」
「……おかずタカるなら、坂上先輩にタカればいいんじゃないですかー?」
「んな……っ! あ、あいつは関係ねーじゃろ……」
調子に乗って、おかずに手を伸ばす岡村が鬱陶しかったので、坂上先輩の名前を出してみた。絡まないでほしかっただけだったのだけど、想像以上に効果があったらしい。岡村の顔は、真っ赤になっていた。先輩たちが、岡村をからかう理由が、ちょっとわかった。
岡村も今の私みたいな、メチャクチャな気持ちを味わったのだろうか。そんな感じは全くしなかったけど、岡村が先輩と付き合っているなら、そういう気持ちがあったということになる。ひょっとして、この気持を沈める方法を、知っていたりしないだろうか。私は、相談を持ちかけようか悩む。
でも岡村に、私がロップを好きだなんて話したら、きっと死ぬほどからかわれるに違いない。そればかりか、そのままロップに伝わってしまう可能性もある。私は岡村の後頭部を睨みつつ、唐揚げを齧った。
そのとき、開け放した教室のドアから、他のクラスの子が数名、コソコソと岡村に近づいてきた。
「おぉ、新しいの入っとるぞー」
その子たちが机を取り囲むと、岡村はポケットからカードケースを取り出した。中身を机に並べると、きゃーっ、と悲鳴のような歓声が上がる。思い思いに長方形のフィルムを手にとって、岡村に千円札を渡す。昼休み恒例、バンドのチェキ販売だ。ここ数日、チラチラ覗いて見たところでは、衣装もポーズもバッチリ決まっている物から、隠し撮り風の物まで、いろいろあるようだった。物によって値段も違うらしい。
こんなの、売る方も買う方もどうかしている。どうしてロップの写真なんかを買う人がいるんだろう。ずっと疑問だったけど、最近ようやく、その謎が解けた。ロップは、並外れて顔が良いのだ。ロップのバンドのメンバーが、並んで写った写真を見るとよくわかる。メンバーたちは、みんなそれなりに美形だったけど、ロップはずば抜けていた。それに、この土地での知名度や、音楽活動や、ファンサービスを加えれば、ご当地アイドルのようになってもおかしくはない。
じっと机の上のチェキを見つめていると、視線に気付いた岡村が振り返った。
「……なんじゃ、槙田。また商売にケチつけよんのか?」
私は度々、チェキの販売について苦言を言っていたので、またか、と思われたらしい。
でも、今日は違う。
「いえ、その……、そこの、うどんのヤツ、買おうかなって……」
顔をしかめた岡村に、机の上を指差して言った。
岡村は、目をまんまるくする。
「え、なんじゃ、お前も若さまのファンになりよったんか?」
「違いますよ。ただ、おかむーとも、ロップとも仲良かったのに、写真、学校行事のと、卒業アルバムくらいしかないなって思って……」
私はよどみなく、連日考え抜いた言い訳を述べてみせた。半分ウソだけど、半分は本当だ。真実味はあったはず。
岡村は、なるほどな、という顔をして、私が指さしたチェキを手に取る。
「千円」
「高っ! まけてくださいよ」
「んなことしよったら、わしが売上ちょろまかしたー思われるじゃろ」
岡村は、ずい、と手の平を上向きにして、突き出してくる。私は唇を尖らせて、千円札を乗せた。引き換えに、チェキを受け取る。フィルムには、学食でうどんを食べているロップと、岡村が写っていた。一秒だけ、しっかり目に焼き付けてから、生徒手帳に挟んでポケットにしまう。手が冷たくて、少し震えていた。
なんだか、ロップとおかむーの二人を裏切ってしまったような気分だった。でも、それでも私は、今のロップの写真がほしかった。
大丈夫、このくらいならまだ、友達の範疇に収まる、はず。そう自分に言い聞かせて、お弁当の残りを無理矢理口に押し込んだ。
続きは書き溜まり次第公開していきます。
元の話にないシーンばかり書いています。プロットでは五のあたりまでが一幕だったので、この感じだと完結まで5万字くらいは書かないといけない気がして戦慄です。元は2万字だったので倍以上ですね……。
始めっからラブな設定で書いていればこんなに長くならなかったかもしれないのに、なんで気付くシーン作ったプロット作ったときの自分!書いてて楽しかったけども!
まぁ、前のよりも読んでて楽しめるようなら幸いです。続きも頑張ります。
ハイエナ??という方はこちらを参照してください。
ハイエナ設定解説
この他のオリジナル百合小説はこちらへ。
オリジナル百合小説目次
ちょっとでもいいなと思ったら、記事下のソーシャルボタンから拡散していただけるとありがたいです!